はじめに
東京の前身である江戸の町。幕府が開かれてから約260年、東京と名が変わってからの時間を合わせると400年以上、日本の首都として繁栄してきました。今でこそ高層ビルが立ち並ぶ大都会ですが、江戸時代には背の高い建築物はありませんでした。
江戸城の天守閣はたしかに高く、江戸の町を見下ろせるほどでしたが、土台を入れても80メートルほど。今の新宿にある高層ビルの3分の1の高さしかありません。しかも、明歴3年(1657年)の「明歴の大火」で焼け落ちたのちは再建されることがありませんでした。
つまり、1657年から幕末まで、江戸の空は広く、現代人には想像できないほど見晴らしがよかったということになります。春や秋に空を見上げれば、市中でもハクチョウをはじめとするカモ科、そしてタンチョウなどのツル科の鳥たちが飛んでいく姿が見えました。
徳川時代の江戸は、今以上に緑にあふれる土地であり、周囲にも野や畑、林が広がっていました。市中の神社仏閣はもちろん、武士や大商人の屋敷の庭にも木があり、そこにも野鳥の飛来がありました。たとえば江戸の後期に神田明神下にあった曲亭馬琴(滝沢馬琴)の家の庭にもウグイスが飛来し、巣を作っていたことを馬琴の日記等から知ることができます。
また、江戸城のあった土地(本丸台地)の南方は、幕府が江戸に置かれる以前は海で、入り江(日比谷入江)が大きく入り込んでいました。現在の東京23区南方の広いエリア、すなわち千代田区南東部以南は埋め立てによってつくられた土地です。かつて市場のあった築地のあたりも海であり、「築地」は埋め立てて造られた土地の意味から「地を築く」の漢字をとって「築地」となったことが知られています。
そんな自然豊かな江戸の町には、はるか昔から多くの鳥が生息していました。東京になっても変わらない生活をするものがいる一方、大きく暮らしを変化させた鳥たちもいます。かつては特定の季節に飛来していた鳥が、いまは留鳥(りゅうちょう:季節による大規模移動を行わず年間を通じて同じ地域に住み続ける鳥のこと)となって一年中見られるようになったケースもあります。逆に、かつては身近だった鳥が、いつのまにか見られなくなっている例もあります。
この連載では、江戸時代と現代の江戸・東京、および周辺の土地の鳥を比較して、変わらぬ様子や変化した様子を紹介していこうと思います。
連載タイトルの「大江戸八百野鳥」はもちろん、江戸の町の広がりを示す「大江戸八百八町」(おおえどはっぴゃくやちょう)からいただいたものです。
オナガは江戸の鳥
白い先端を除いた長い尾の大部分と、畳んだ状態の風切羽は水色。黒い頭部はベレー帽をかぶったよう。肩から背中、腹部はグレー。細身のおしゃれな鳥、それがオナガです。
その姿を「貴族のよう」と形容した漫画家もいましたが、いい得て妙です。
オナガは、今も昔も西日本には生息していません。京や大坂といった上方はもちろん、名古屋圈の尾張や三河にもいません。つまり、西ではなじみのない鳥でした。オナガの生息域は、静岡県の天竜川付近を縦に切った線の東側に限定されていて、北限は青森県。北海道にも生息していません。
筆者は中学高校を岩手で過ごし、当時から野鳥も追いかけていましたが、そのころオナガは一度も見たことがありませんでした。今も昔も、関東から信州東部にかけて多く分布する鳥だったようです。寺島良安の『和漢三才図会』(正徳2年/1712年成立)にも「関東の山中に多い」とありますが、そのとおりです。オナガが西に勢力をのばそうとしたことも過去に幾度かありましたが、最終的にはもとの生息地に押し戻され、西に定着することはついぞありませんでした。
尾の長い鳥は日本でも何種か知られていて、そうした鳥たちの略称はオナガとおなじ「おなが」や「おながどり」でした。輸入された中国産のサンジャクや夏に渡ってくるサンコウチョウなども、同じ名で呼ばれた記録が残っています。そんな鳥たちとの混同を防ぐために、また、関東中心に生息する鳥であることを強調するために、ときにオナガは「くはんとうおなが(関東尾長)」と呼ばれることもありました。宝永7年(1710年)に刊行された鳥の飼育書『喚子鳥(よぶこどり)』(蘇生堂主人)でも、「くはんとう尾なが(関東尾長)」の名で紹介されています。明治時代に田中芳男によって編集された『錦窠禽譜』のオナガの絵にも、「関東オナガ」の名が見えます。

江戸では冬鳥
現代に生きる私たちにとって、オナガの尾は「水色」ですが、江戸時代に生きた人々にとっては「浅葱色(あさぎいろ)」でした。浅葱色は平安時代から日本人が馴染んできた水色系の色です。音の響きとしては、「水色の鳥」というより「浅葱色の鳥」のほうが、少しだけ優雅な気もします。

オナガは今も、東京・神奈川でよく見かけます。仕事場の窓からも、ときおりその姿を見ます。筆者がとくに好きな鳥でもあることから、第一回に登場してもらいました。
今でこそ一年中見られるムクドリは、江戸時代の江戸には秋になると飛来する鳥でした。じつはオナガも、当時は冬になるとやってくる鳥で、夏場は山寄りの土地で繁殖をしていたようです。先にも紹介した飼育書『喚子鳥』には、「冬、出る」と記されています。
オナガ最大の災難
オナガは何千年も何万年も日本列島で平和に暮らしてきましたが、昭和のある日、その平和が崩れます。1970年代になると、カッコウがオナガの巣に托卵するようになったからです。そして、それは瞬く間に広がりました。
カッコウの仲間(杜鵑類:トケン類)の托卵は、『万葉集』が編纂された奈良時代には知られていました。和歌の中にも、ホトトギス(もしくは近縁)の托卵を詠んだ作品が残っています。江戸時代、カッコウの主なる托卵先はホオジロでした。モズやオオヨシキリなどにも托卵をしましたが、オナガに托卵することはありませんでした。理由は明確で、両者には生活圏の重なりがなかったからです。
しかし、半世紀ほど前、もともと深山の鳥だったカッコウは平地の森や林にも進出し、オナガは逆に平地の森や林から山地にも生息域を拡大させたことで、両者の生息圈が重なります。これがオナガに重大な事態をもたらすことになりました。一時、特定の地域でかなり生息数を減らすことになったのも事実です。今もオナガとカッコウの攻防は続いていますが、異種の子を育てていると気づき始めたオナガの自衛も始まっていて、卵が自身のものであるかどうかを見きわめる目も鋭くなってきたようです。
個人的な印象ですが、近年(20世紀の末くらいから)、都会に暮らすオナガが増えたように感じています。カッコウが来ることがない「都会の安全性」に気づいた可能性があるのでは? と考えています。
ただ、東京や神奈川では、増えてきた緑色のワカケホンセイインコ(スリランカなどを故郷とするホンセイインコの亜種)がオナガの生活圏に侵入してきて、追い払う様子も見られるようになりました。一難去ってまた一難ではないですが、オナガの受難は続くようです。
イベリア半島と東アジア
イベリア半島西部から中央部のポルトガルとスペインにまたがるエリアに、オナガそっくりな鳥が生息しています。古い鳥類図鑑では、オナガは日本をふくめた極東とイベリア半島に分かれて棲んでいて、イベリア半島のものは亜種と書かれています。
オナガに近い、おなじカラス科のカケスやカササギは、広くユーラシアに分布しているため、ユーラシアの両端に暮らすオナガも同様と考えられてきました。しかし、詳しくDNAを解析したところ、何万年もの遺伝子の隔たりがあり、別種と認定されました。

イベリア半島のオナガ(Iberian Magpie)は日本や中国、朝鮮半島のオナガよりも数センチメートルほど体長が短く、尾の先端が白いアジアのオナガ(Azure-winged Magpie)とは違い、先端まで水色です。氷河期に東西に分断されたと考えられていますが、このような極端な分布になった正確な理由は、まだ解明されていません。
【参考文献】
『馬琴日記』滝沢馬琴
『吾仏乃記:滝沢馬琴家記』滝沢馬琴
『とりぱん』とりのなん子(講談社)
『和漢三才図会』寺島良安
『喚子鳥(よぶこどり)』蘇生堂主人
『錦窠禽譜』田中芳男
【執筆者】
細川博昭(ほそかわ・ひろあき)
作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュする。おもな著作に、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥を識る』『人と鳥、交わりの文化誌』『鳥を読む』『人も鳥も好きと嫌いでできている』(春秋社)、『江戸の鳥類図譜』『江戸の植物図譜』(秀和システム)、『知っているようで知らない鳥の話』『江戸時代に描かれた鳥たち』(SBクリエイティブ)、『身近な鳥のすごい辞典』(イースト新書Q)、などがある。
【編集協力】
いわさきはるか
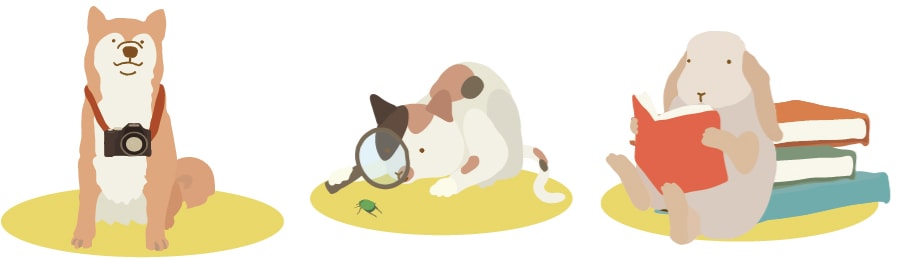

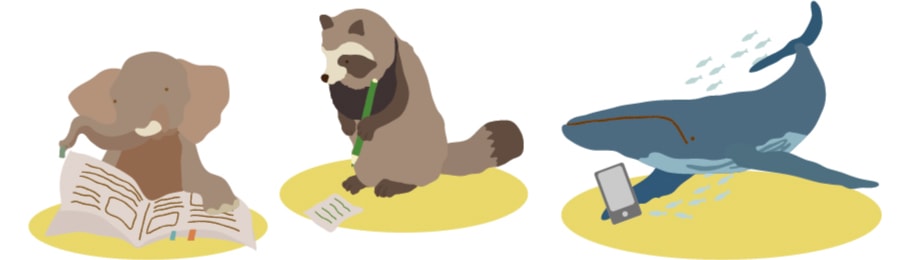














IMG_1773.jpg)
