アホウドリの命名
この鳥が、「アホウドリ」というあまり好ましいとは思えない名前で呼ばれるようになった理由は2つあります。
ひとつは、江戸時代には多くの名があり、ほかの鳥のような統一された名称がなかったこと。土地ごとにさまざまな名で呼ばれたアホウドリの異名は、数十にものぼります。
日本の鳥名の原点は江戸の図譜にあります。江戸時代の中期から後期は本草学(ほんぞうがく:植物や動物の性質や効能を研究する学問)が盛んだった時代で、日本独自の本草学が花開きました。図譜は、いまでいう動植物の図鑑です。
大名・旗本などが自ら本草学を学び、もしくはお抱えの本草学者に命じて鳥の図譜を作った際、それまで多くの名が存在した鳥たちの名が整理され、統一化が一気に進みました。
一方で鳥は、当時の江戸の人々の最大のペット。鳥屋と飼育者のあいだの売買も盛んで、人気の鳥は名称を統一しないと両者のあいだで上手く商売が成立しないこともあり、統一化を求める圧力は市場にも存在していました。
しかし、そんな江戸時代においても、アホウドリの名前の統一は行われませんでした。
太平洋の洋上を悠々と飛び回っていたアホウドリの繁殖地は概ね海洋中の小島で、事故でもないかぎり日本本土に降りることはなかったからです。各地の漁師とは接点があったものの、一般的な日本人にとって馴染みのある鳥ではなかったことも、名が統一されなかった大きな理由でした。
IMG_1773-1.jpg)
飯島魁の功罪
明治時代、欧米に追いつくように学術研究にも力を入れ始めた日本でしたが、学術雑誌でこの鳥を紹介するときに困りました。正式な和名が決まっていなかったからです。誌上で英名の「アルバトロス」が使われたのも苦肉の策でした。
「アホウドリ」をこの鳥の名として選んだのは、日本鳥学会の創設者である東京帝国大学理科大学教授の飯島魁(いいじまいさお)です。必要に迫られて行った名づけの際、「『バカドリ』ではあまりに問題だが、『アホウドリ』くらいなら許容範囲では?」と考えたといわれます。これがもう1つの理由です。
地上では不格好にノタノタとしか歩けず、簡単に捕獲できたことから、江戸時代の初期にはすでにアホウドリ、バカドリとも呼ばれていました。明治時代に乱獲され、一時は絶滅宣言が出たこともよく知られたとおりです。鳥の特徴、呼ばれ始めた時期も考慮して、この大型の海鳥は「アホウドリ」と命名され、日本での正式名称となりました。
アホウドリのさまざまな名前
江戸時代までアホウドリは、「沖の太夫」や「沖の尉」、「信天翁」など、現代人から見ても格好良く思える、響きのよい名で呼ばれていました。
「沖の太夫」の読みは、「おきのたゆう」または「おきのたいふ」。「沖の尉」は「おきのじょう」。江戸時代後期、伊予地方などでは、「おきのぞふ(おきのぞう)」と少しだけ響きを変えた名前で呼ばれていたこともわかっています。
「嵐のとき、アホウドリが難を逃れるように止まった船は難破することなく嵐をくぐりぬけられる」という伝説があったことから、「沖の太夫」や「沖の尉」はアホウドリを「幸運の鳥」と見做し、尊んでつけられた名前でした。
「信天翁」はそのまま「しんてんおう」と呼んだほか、この字のまま「らい」と読まれることもありました。「信天縁(しんてんえん)」という呼び名もありました。いずれも由来は漢名です。なお、「らい」は筑紫地方の当時の呼び名でした。
「あほうどり」は、江戸時代の初期に丹後地方などで呼ばれていた名前です。「あねこどり」もアホウドリの異名ですが、こちらの由来はよくわかっていません。
図譜の中のアホウドリ
あらためて江戸の鳥の図譜に目を向けてみましょう。そこには多くのアホウドリの絵があります。河野通明ほかが描いた『奇鳥生写図』のアホウドリには、「ダイナンカモメ」の名が見えます。漢字にすると「大灘鴎」。「大灘」は山の見えなくなる沖合の意味で、陸地から遠い海のこと。「大灘鴎」は、はるか沖合にいるカモメの意味となります。

編纂者不詳の『水禽譜』のアホウドリの絵にも「ダイナンカモメ」の名が見え、別名として「シラブ」という名も記されています。仙台藩主伊達宗村の八男にして、近江堅田藩主の養子となった堀田正敦が編纂した『禽譜』にも、これとおなじ絵があります。そこから『水禽譜』の作者は、堀田正敦に近い大名のだれかだったと推察されています。製作はともに1830年くらいと考えられています。
日本近海では、成鳥になると白が目立つアホウドリとコアホウドリ、成鳥になっても黒いクロアシアホウドリが生息しています。アホウドリの若鳥は成鳥とちがって黒い羽毛をしています。シラブは体の下面が完全に白い羽毛となったアホウドリの成鳥を指す言葉であり、クロブはアホウドリの幼鳥やクロアシアホウドリを指す当時の言葉だったようです。

アホウドリとして描かれた図譜には黒い鳥が多く見られます。顔と足がアップで描かれた伊藤圭介(伊藤錦窩)の『錦窠禽譜』(明治5年/1872年に編纂)には、「アネコドリ」と「アホウドリ」、「大灘カモメ」の名が並記されていました。

クロアフブと記された熊本藩主細川重賢の『鳥類図譜』(1775年写)のアホウドリもおそらく幼鳥です。

作者不明の『啓蒙禽譜』(1830年頃)のアホウドリ。こちらも黒。「信天翁」ほか、いくつかの名前が紹介されています。

江戸のアホウドリ
旗本毛利梅園が、天保三年に江戸の小石川馬場付近に落ちてきた黒いアホウドリの絵を寸法つきで描き、自著の図譜『梅園禽譜』(1840年頃)に残しています。おそらくこれも幼鳥です。この鳥は江戸城に献上される予定でしたが、城に届けられる前に死亡したと記録されています。
アホウドリは関東では少ないと当時の本草書には記されていましたが、このように、まれに江戸に舞い降りることもあったようです。このような大きな鳥が舞い降りてくる様を見た江戸の人々は、とても驚いたことでしょう。現代では想像もできない事件です。
かねてから指摘されていたように、明治以前は日本近海にも非常に多くのアホウドリがいて、近海をふくめた多くの島で繁殖をしていたこと、また十分な飛翔力のない若鳥が風に流されるなどして日本本土などの陸地に飛ばされることもあったことが、ここからわかります。『梅園禽譜』のアホウドリもそうやって飛んできたものと考えられています。
尾張藩の本草学者であった水谷豊文の『豊文禽譜』(1830年頃?)には、文政13年4月に阿州津田浦(現在の徳島県徳島市、吉野川河口南部)に死体が漂着した旨が記されています。絵には名のわからない鳥とありますが、現在はアホウドリと同定されています。この鳥も幼鳥だったことがわかります。

梅園禽譜に描かれた黒いアホウドリ

[参考文献]
『アホウドリからオキノタユウへ』長谷川博
『奇鳥生写図』河野通明ほか
『水禽譜』作者不詳
『錦窩禽譜』伊藤圭介(伊藤錦窩)
『鳥類図譜』細川重賢
『啓蒙禽譜』作者不詳
『梅園禽譜』毛利梅園
『豊文禽譜』水谷豊文
【執筆者】
細川博昭(ほそかわ・ひろあき)
作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュする。おもな著作に、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥を識る』『人と鳥、交わりの文化誌』『鳥を読む』『人も鳥も好きと嫌いでできている』(春秋社)、『江戸の鳥類図譜』『江戸の植物図譜』(秀和システム)、『知っているようで知らない鳥の話』『江戸時代に描かれた鳥たち』(SBクリエイティブ)、『身近な鳥のすごい辞典』(イースト新書Q)、などがある。
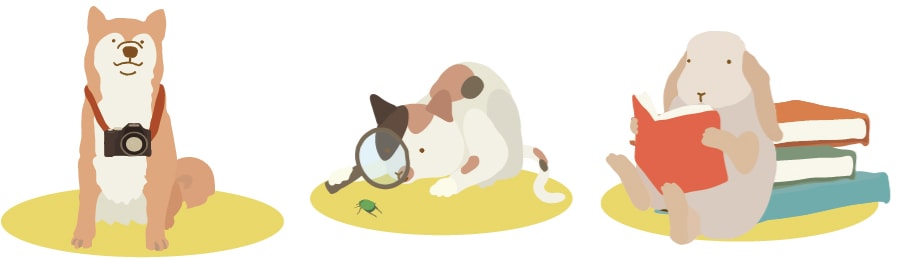

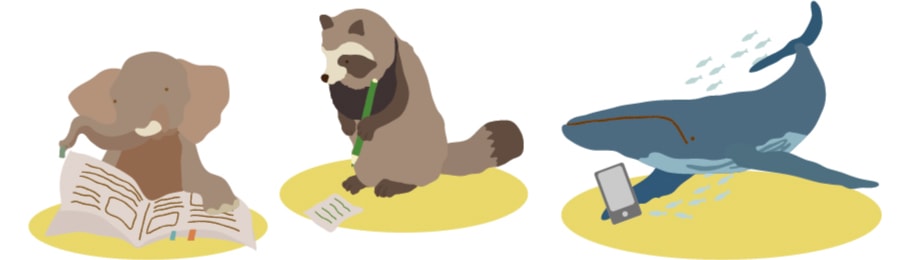














IMG_1773.jpg)
