潜水が得意なウ
上野恩賜公園内、不忍池(しのばずいけ)にある小さな島に黒い鳥が集団で暮らしています。この鳥がカワウです。ウの仲間は日本に4種類がいますが、ふつうに陸地で見られるのはカワウのみです。
カワウの嘴の先端から尾の先までの長さ(=体長)は平均で81センチメートル。アオサギなどの大型のサギとならんで、都市部で見られるもっとも大きな鳥のひとつです。ウは魚を主食とする水鳥で、潜水して獲物を捕ります。その潜水能力は30メートルを超えます。
営巣地や夜に眠る塒(ねぐら)は、川や海に近い林などにあります。このような生活のため、水辺から遠い町中で見かけることはほとんどありません。東京の真ん中にありながら周年でカワウが暮らす上野はきわめて例外的で、鳥に関心をもつ海外の人々からも注目される場所となっています。


江戸で一番数の多い鳥
カワウが不忍池で暮らすようになったのは、昭和中期にこの場所に放鳥されたことがきっかけですが、カワウ自体は江戸時代から、江戸城の堀を中心に江戸近郊のさまざまな土地で見られた鳥でした。
江戸はもともと、今の日比谷あたりまでが海であり(日比谷入り江)、江戸時代の初期にそこを埋め立てて造成されたのが町の南側の土地です。また、江戸城を取り囲むように掘やそのほかの水路が整備され、東京湾に流れ込む川とも繋がれて物資を運ぶ舟運(しゅううん)の軸としても活用されていました。
「溜池」の名が残っている土地も、当時はその名称どおりの「溜め池」でした。江戸城の堀はいまよりも広く、冬場にはカモやハクチョウが渡ってきていたことも知られています。つまり当時の江戸は今よりもずっと「水」が豊富であり、多くの水鳥が暮らしていた土地でした。カワウもまた、そんな鳥の一種だったわけです。

江戸時代はまだ、ウミウとカワウが区別されていません
明治時代の初頭、政府に招かれて東京に滞在したイギリスの測量技師C・A・マクビーンは、「江戸鳥学覚書(Notes on the Ornithology of Yedo)」において、江戸・東京でもっともたくさん見られる鳥はカワウであると書き綴っています。
当時、カワウは複数の場所で繁殖していましたが、江戸城の堀には大きなコロニーがあり、そこで数千羽が営巣していたようです。「夕方、ねぐらに帰ってくるときの声の騒がしさは、四百メートル離れていても聞こえるほど」と、マクビーンは同書に記しています。
登城する人は圧迫感も感じた?
ウはカラスよりも大きな鳥ですが、積極的に人間に近づこうとはしないため、暮らしの中で「恐い」と感じることは、ほとんどありません。逆に、川のふちなどで翼を広げて羽毛を乾かしている姿には、ほのぼのした印象さえ受けます。
だだしそれは、少数でいる場合でのこと。大集団になると印象が大きく変わります。江戸城の堀に集まる千羽を超えるカワウの集団を、日々目にしていた武士や商人は、圧迫感のようなものも感じていたはずです。黒く大きく、騒がしい鳥の大集団に恐怖をおぼえた人もいたかもしれません。
また、ウがたくさん集まる木は短期間で枯れてしまいます。酸性のフンが悪影響を与えるためです。不忍池の島の木はある時期、枯れたり腐ったりしない人工物(擬木)に置き換えられましたが、江戸時代は木が枯れた場合、植木屋を呼んで植え替えるのが常だったはずです。そこにどのくらいの費用がかかったのかは、想像もできません。
鵜飼は日本各地で
ウといえば、よくイメージされるのが「鵜飼」。かがり火のもと、舟上の鵜匠によって操られたウが川に潜って鮎を獲る姿を脳裏に浮かべる人も少なくないでしょう。
鵜飼に関心をもつ人々に「鵜飼が見られるのはどこ?」と尋ねると、「岐阜県の長良川」という返答も返ってきます。「鵜飼=長良川」もまた、現代人に強く刷り込まれたイメージであるように感じられます。
そうした背景から、“見せること”を目的とした長良川タイプの鵜飼が「鵜飼の標準形」と思われがちですが、明るい昼に行う鵜飼、舟を使わず漁師が水に入ってウに魚を追わせる鵜飼、紐でつながず自由に潜らせて魚を獲るタイプの鵜飼など、過去にはさまざまななかたちで鵜飼が行われていました。日本における鵜飼の形は、実はひとつではありません。
目的もさまざまで、観光が主体の鵜飼もあれば、レクリエーションやスポーツ的に行われた鵜飼もありました。純粋な漁業としての鵜飼ももちろんありました。
江戸時代の鵜飼は実は、漁業として行われていたものが多かったという事実もあります。それは、藩や幕府によって支援されてもいました。明治時代になって地方の多くの鵜飼が途絶えたのは、国の政治体制が大きく変化し、地方(藩)や幕府の補助が打ち切られたことが大きく影響したという事実もあります。
日本の鵜飼の主役はウミウ
日本の鵜飼はウミウが主体です。日本の鵜飼には1300年を超える歴史がありますが、過去においても、多くの場所でウミウが使われてきました。といっても、カワウがまったく使われなかったわけではありません。たとえば江戸時代に、多摩川、相模川、荒川などの江戸近郊の河川で行われていた鵜飼において使われたのはウミウではなく、カワウです。

釜無川と笛吹川が合流して富士川となる「鰍沢(かじかざわ)」において、岩場から水面に紐をのばす漁師。鵜飼の図、投網の図どちらか不明とされるが、釜無川、笛吹川、富士川のいずれも紐でつながれたウを使った鵜飼が行われていたことなどから、筆者は鵜飼の様子を描いたものと考えています。
現在、鵜飼が行われている国は日本と中国だけですが、過去にはインドのブラマプトラ川や、ベトナムのメコン川でも鵜飼が行われていました。古代のエジプトや紀元前の南米ペルーでも、鵜飼が行われていたことを示唆する絵が壁画や土器の表面に残っています。
日本で徳川幕府が始まったのとちょうど同じころ、ジェイムズ一世統治下のイングランドでもスポーツ的な感覚でカワウを使った鵜飼が行われており、その鵜飼はやがてフランスなどにも伝わりました。ヨーロッパで行われた鵜飼は、中国の鵜飼を参考にして始められたものと考えられています。
なお、日本と中国の鵜飼には千数百年以上も接点がなく、始まりにおいて関係があったかどうかもはっきりしていません。そうした状況から、どちらかにルーツがあるのではなく、それぞれ独自に始まったものと考えるべき、という主張もあります。
古代のエジプトや南米でも実際に鵜飼が行われていたとしたら、各国の鵜飼は独自に始まったものと考える必要があります。つまり「鵜飼」は、時間的にも空間的にも大きな広がりをもっていたことを否定できないということになります。
ウの増減
はるかな過去より日本の生態系の一部であったカワウ。江戸時代~戦中・戦後を通してよく目にする鳥でしたが、現在に至るまで一定して数が多かったわけではありません。昭和の一時期、東京はもちろん、全国で劇的に数を減らしたことがありました。
数が激減したのは、有害物質などによる環境汚染が深刻化した、いわゆる「高度経済成長期」で、この時期、関東では営巣地がほぼすべて消滅し、カワウが暮らしているのは不忍池のみという状況にも陥りました。コンクリートで固めた河川改修も環境汚染とともにウの生活に悪影響を与えていました。
昭和中期、日本のカワウは実質的に絶滅が危惧される状況にありました。
状況に改善が見られるようになったのは1980年代のこと。住環境が改善され、積極的な保護も行われたことで、カワウは爆発的に数を増やします。2000年代になると逆に、漁業関係者から被害に関するクレームがつくほどになりました。
近年は、強い酸性のフンによって、営巣や塒として使う林の木があっというまに枯れてしまう被害「枯損(こそん)」も増え、改めて対策も協議されるようになっています。

[参考文献]
『華鳥譜』服部雪斎
『江戸鳥学覚書(Notes on the Ornithology of Yedo)』Colin Alexander McVean
『富嶽三十六景』葛飾北斎
【執筆者】
細川博昭(ほそかわ・ひろあき)
作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュする。おもな著作に、『インコ・オウムの心を知る本』(緑書房)、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥を識る』『人と鳥、交わりの文化誌』『鳥を読む』『人も鳥も好きと嫌いでできている』(春秋社)、『江戸の鳥類図譜』『江戸の植物図譜』(秀和システム)、『知っているようで知らない鳥の話』『江戸時代に描かれた鳥たち』(SBクリエイティブ)、『身近な鳥のすごい辞典』(イースト新書Q)などがある。
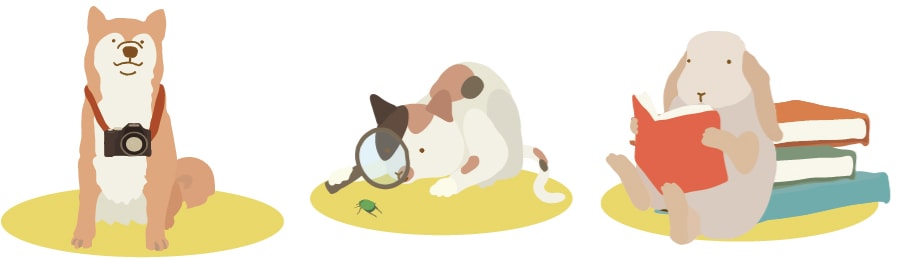

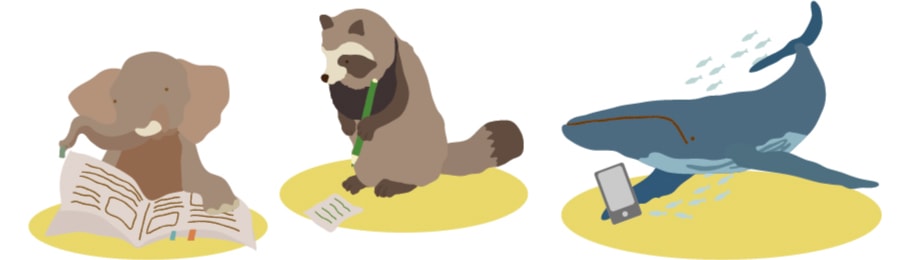














IMG_1773.jpg)
