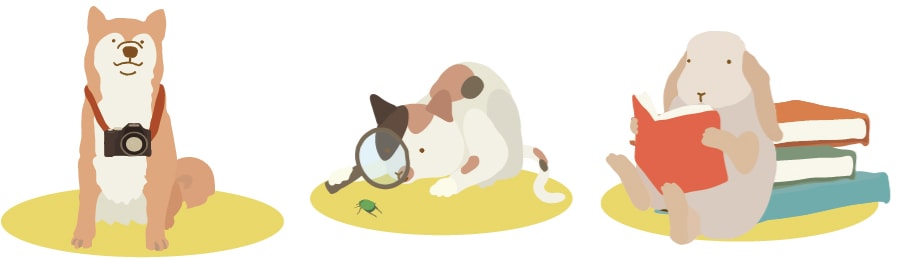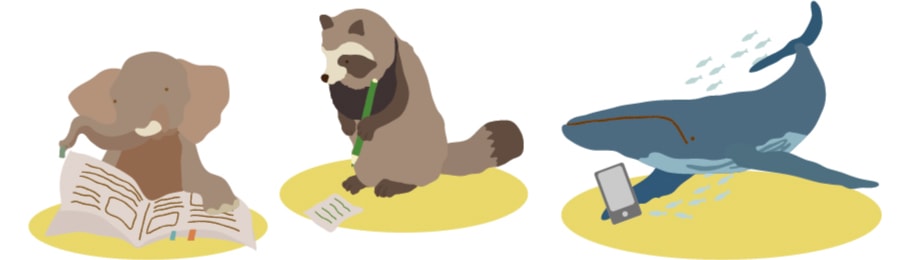『枕草子』における可哀想な犬
『源氏物語』のような平安時代のかな文学には、自然や動物がたくさん描かれているイメージがあるかもしれませんが、本当に描かれているのかと考えたとき、必ずしもそういうわけではありません。和歌の中でたくさん詠まれる動物の場合、動物そのものが描かれていると言いにくいものが多いからです。例えば、水面に浮かぶ水鳥に、「浮き」と「憂き」(つらい)をかけるような、掛詞や縁語などのレトリックによって、詠者(和歌を詠んだ人)や登場人物の感情が喩えられます。
和歌表現にあまり用いられない動物が登場する場合、現代の感覚からすると可哀想な話が多く、動物好きにとっては読んでいて辛いものがあります。有名な『枕草子』の翁丸の話も、いい話としてまとめていますが、どう読んでも動物虐待です。人事と重ねて描いているらしいのですが、そんなもののネタに犬を使わないでほしいです。
『枕草子』の翁丸の話
【翁丸の話】
「命婦のおとど」と呼ばれて帝にたいへん大切にされている猫がいた。その猫が縁先で日向ぼっこをしており、いくらお世話係の馬の命婦(みょうぶ)が入ってと言っても寝たふりをしてなかなか入らない。困った馬の命婦が「翁丸、命婦のおとどに食いつきなさい」と言ったものだから、犬の翁丸は真に受けて命婦のおとどに走りかかり、命婦のおとどは慌てて中に飛び込んだ。それを帝がご覧になって、たいへんご立腹で、翁丸を打擲(ちょうちゃく)させて「犬島」に流させた。
3、4日経った頃、犬が激しく鳴くのでどうしたのかと思っていると、「犬を蔵人(くろうど)2人で打擲していた。犬島に流したのに戻ってきたので、そうしているのだ。きっと死んでしまうだろう」と御厠人(みかわやうど:便所の世話などをする身分の低い宮中の女官)が言ったので、止めに人をやったものの、犬は鳴き止み、「死んでしまったので陣の外に捨てた」と報告された。
その後、とても体が腫れてひどい状態の犬がやってくるが、「翁丸」と名前を呼んでも反応せず、物も食べないので、別の犬だろうということになる。ところが翌日、中宮が鏡を見ながら翁丸への同情を口にすると、その犬は涙を流してぷるぷると震えた。その犬は翁丸だったのだが、昨晩は隠れて我慢していたのだ。帝もその話を聞き、翁丸は許された。
この話において翁丸は、やってはいけないことを脅しで口にする愚かな人間の命令を律義に聞いてしまったことで、追放の憂き目にあいます。最初から人間の言葉を理解していたにもかかわらず、言語外の意図を読み取れずにひどい目にあうのです。犬は人間の言葉を話すことはできませんので、言葉が分かっていることを示すためには命令に従うしか方法がありません。
猫が怪我でもしていたら大ごとですが、慌てて中に飛び込んで無事ですので、命令者の当初の目的は達成できています。「痴れ者」はどう考えても人間のほうですね。翁丸は、追放されても死なずに戻ってきて、戻ってきても虐待されて、わざと名前がわからないふりをしてから涙を流すという高度な文脈読解を披露して、ようやく許されたのです。それまで人間を信頼していたのに虐待されて、どんなに辛かったでしょう。
『源氏物語』の大切にされる猫
そんな可哀想な動物たちの中で、特権的に大切にされているのが猫です。
翁丸の話でも、猫は大切にされていて無傷です。当時の猫は、中国から輸入された貴重で高級なペットであったようです。もちろん動物医療は今のように進んでいませんが、猫に関しては、残酷だとか可哀想だとか思って辛くなるような展開は多くありません(火事で邸宅とともに焼けてしまった、『更級日記』の猫くらいでしょうか?)。

『源氏物語』にも溺愛される猫が登場します。『源氏物語』は、源氏が栄華に到達するまでの第一部、表面上の栄華とはうらはらに登場人物たちが内面に懊悩を抱える第二部、源氏死後の物語を描く第三部に大きく分けられます。猫が登場するのは、このうちの第二部です。
女三の宮の垣間見
源氏は六条院と呼ばれる四季を模した大邸宅を造り、それぞれに女君を住まわせていました。
第二部の冒頭で話題になるのが、源氏の兄朱雀院が出家するのに際し、鍾愛の娘である女三の宮を誰と結婚させるか、ということでした。源氏のかつてのライバルであった頭中将(この時点では太政大臣)の長男である柏木は、女三の宮との結婚を強く望みます。源氏の長男である夕霧なども結婚候補にあがりましたが、最終的には朱雀院のたっての願いにより、女三の宮は源氏と結婚することになります。源氏は幼い女三の宮の様子に落胆しますが、表面上は何ごともない日々が続いていました。

ある春の日、源氏は夕霧や柏木ら若君達を呼んで蹴鞠を催します。夢中になって毬を蹴っていた夕霧と柏木が階(きざはし)の上で一休みしていたとき、走り出してきた猫の綱(当時は猫をつないで飼っていた)が絡まり、御簾が持ち上がります。
【猫の登場場面】
唐猫のいとちひさくをかしげなるを、すこし大きなる猫おひつづきて、にはかに御簾のつまより走り出づるに、(中略)。猫は、まだよく人にもなつかぬにや、綱いと長くつきたりけるを、ものに引きかけまつはれにけるを、逃げんとひこしろふほどに、御簾のそばいとあらはに引きあけられたるを、(中略)。
几帳の際すこし入りたる程に、袿姿にて立ち給へる人あり。(中略)御衣の裾がちに、いと細くささやかにて、姿つき、髪のかかり給へるそば目、言ひ知らずあてにらうたげなり。(中略)。猫のいたく鳴けば、見かへりたまへるおももち、もてなしなど、いとおいらかにて、若くうつくしの人や、とふと見えたり。(中略)、猫の綱ゆるしつれば、心にもあらずうち嘆かる。ましてさばかり心をしめたる衛門の督は、胸ふとふたがりて、(中略)。わりなき心地の慰めに、猫を招き寄せてかき抱きたれば、いとかうばしくて、らうたげにうち鳴くも、なつかしく思ひよそへらるるぞ、すきずきしや。(若菜上、3巻296~297頁)
〈解説〉
可愛らしい小さな唐猫を少し大きな猫が追いかける。小さな猫は綱を長くつけており、物に引っ掛けて逃げようとするうちに、綱を引っ掛けて御簾が持ち上がってしまう。御簾のそばにいる人々も、怖がってそれを直すことができない。そして几帳の際から少し入ったところに立っている女三の宮が垣間見られる。人々は蹴鞠に夢中になっているために、中の様子があらわになっていることに気づかない。夕霧が咳払いすると、女三の宮は中に入り、人が御簾を直した。残された夕霧は少し残念に思い、柏木には強い執着が生まれる。
柏木が心を慰めるために猫を招き寄せると、猫には女三の宮の移り香のよい香りがした。可愛らしく鳴く様子も、女三の宮に重ねて感じられる。

「ものに引きかけまつはれにけるを、逃げんとひこしろふ」という表現からは、猫が何かをひっかけてしまってパニックになっている様子が目に浮かびます。人々がスムーズに御簾を直すことができないのも仕方ありません。
女三の宮の姿が語られることによって、猫はすぐに女三の宮の象徴になってしまうのですが、それでもこの場面では、生身の猫の生き生きとした動きが描かれています。
愛される猫
女三の宮に執心していた柏木は、この猫を手に入れたいと思い、画策します。柏木が東宮のところに参上すると、帝(冷泉)が飼っている猫の子どもたちがそこに貰われていました。柏木はそれを見て、女三の宮の猫を思い出し、六条院にいる女三の宮の猫は可愛かったと言います。もともと猫好きだった東宮は詳しく話を聞き、柏木も、東宮が猫を欲しくなるように話すのでした。やがて柏木は、東宮のところに貰われた猫を、すこし預かりたいと言って連れて帰ってしまいます。
【柏木が手に入れた猫を可愛がる場面】
つひにこれを尋ね取りて、夜もあたり近く臥せ給ふ。明けたてば、猫のかしづきをして、撫で養ひたまふ。人げとほかりし心もいとよく馴れて、ともすれば衣の裾にまつはれ、より臥しむつるるを、まめやかにうつくし、と思ふ。いといたくながめて、端近く寄り臥し給へるに、来て、「ねうねう」といとらうたげに鳴けば、かき撫でて、うたてもすすむかな、とほほ笑まる。
「恋ひわぶる人のかたみと手ならせばなれよなにとてなく音なるらむ これもむかしの契りにや」と、顔を見つつのたまへば、いよいよらうたげに鳴くを、懐に入れてながめゐ給へり。(若菜下、3巻313~314頁)
〈解説〉
ついに猫を手に入れた柏木は、夜も昼も猫を可愛がる。猫もすっかり馴れて、柏木の衣の裾にまとわりついたり、そばで寝てしまったり。猫が「ねんねん」と鳴くのを「寝よう寝よう」というのだと柏木は聞いて、「恋い慕っている人のかたみだと思って大切にすれば、お前はどういうつもりでそんな声で鳴くのだ」と詠む。東宮が猫を返すように催促しても、閉じ込めて返さない。
「衣の裾にまつはれ、より臥しむつるる」という表現からは、衣の裾にじゃれついて手でちょいちょいしたり、袖口や懐や夜具に入って寝てしまったりする猫の様子が目に浮かびます。すぐに「恋ひわぶる人のかたみ」(恋い慕っている人=女三の宮に縁のあるもの)と、人に重ねられてしまいますが、ここには確かに、擬人化や人間の心情の比喩ではない、生身の猫の可愛らしさが描かれています。
次にこの猫が登場するのは、ずっと後、柏木が女三の宮の寝所に侵入した場面での、柏木の夢の中です。その時点で猫が生きているのか死んでいるのか、あるいは返されてしまったのか明示されていませんが、ともかく柏木の手許にはおそらくもういません。
柏木の夢に登場する猫は、女三の宮の妊娠を象徴するとかしないとか、過剰な象徴性がまとわりついていて、もう猫そのものとは言えません。
それでも、ことばとことばの間、ことばと象徴の間、そして可愛らしくない私たち人間の間をすり抜ける、猫の温かくモフモフした感触が、『源氏物語』には確かに存在するのです。

[参考情報]
・引用は新日本古典文学大系『源氏物語』(岩波書店、1995年)による。ただし私にて改めた部分がある。
・古典文学の猫や、平安文学の猫について書かれているもので、一般向けの書籍には、以下のようなものがある。
田中貴子『猫の古典文学誌 鈴の音が聞こえる』(講談社学術文庫、2014年)
河添房江『紫式部と王朝文化のモノを読み解く 唐物と源氏物語』(角川ソフィア文庫、2023年)
【執筆者】
西原志保(にしはら・しほ)
東北大学大学院文学研究科助教。
1980年香川県生まれ。2009年3月名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期課程修了。博士(文学)。国立国語研究所研究員、共愛学園前橋国際大学非常勤講師などを経て、2022年10月より現職。専門は『源氏物語』を中心とした平安文学と、近現代文学。恋愛しない女性や、動物、植物、人形表象に注目する。実家の香川県で、捨て犬や野良犬が多かったため、保護活動や里親探し活動を手伝ったことから、動物テーマに興味を持つ。