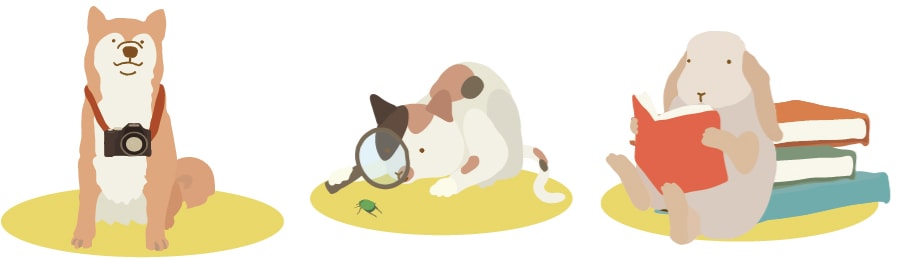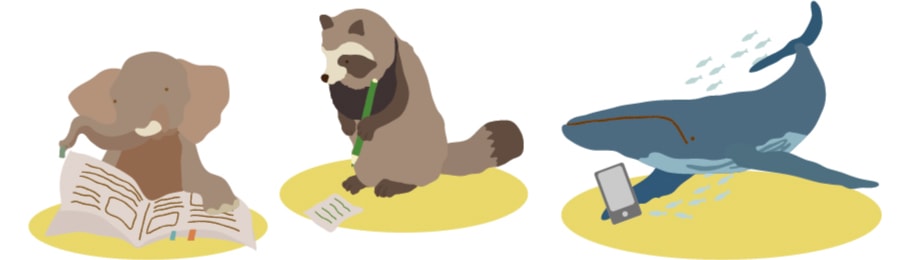インタビュー前編では、幼少期から学生時代、アメリカにおける研究、大学での教育、日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)の設立とその活動などについてお話しいただきました。後編では、猫医学の発展に向けての活動などをお聞きします。
日本の猫医学の発展に向けて
2014年にねこ医学会(JSFM:Japanese Society of Feline Medicine)が設立され、会長としてその活動をけん引されてきました。
猫医療の歴史を追うと、明治時代に遡ります。獣医免許規則が公布された直後、1888年刊行の中央獣医会雑誌1巻4号には猫に関する初期の治療報告がみられます。口腔内に針が刺さった猫に対し、牛用の麻酔薬を使って取り出したという事例です。
この頃の雑誌には、猫に関するアドバイスも書かれていて、「猫は他家の庭を荒らすことがあるため、敷地外に出さないように」と忠告されています。また、猫の臨床経験の少ない獣医師が去勢の方法や注意点を質問し、あるいは「去勢された猫はネズミを取らなくなるか」といった質問も寄せられて、それらに対する丁寧な回答が掲載されています。しかし、この時代から猫の医学が独立したものとして確立されるまでには長い時間を要しました。
戦後、猫に特化した研究と臨床も存在していたことは事実です。しかしながら、獣医大学の教育において猫医学を体系的に教えることはなく、獣医学生は「暴れる猫の扱い」や「ストレスを与えない工夫」といった基本的なことを学んできませんでした。それでも、獣医師は何となく「猫を診る」ことができていたわけです。
もちろんアメリカやヨーロッパでも、犬にくらべて猫医学の発展は遅れていました。それでも、アメリカでは、アメリカ猫医療専門家協会(AAFP:American Association of Feline Practitioners)という歴史ある学会が存在し、猫医学の専門医制度も確立しています。ヨーロッパでも、イギリスの国際猫医学会(isfm:International Society of Feline Medicine)という国際的なチャリティ団体を主体に猫医学は発展してきました。
一方、日本では猫医学が完全に確立されておらず、国際猫医学会のような大規模な組織も存在しなかったため、その整備が必要でした。そこで、猫医学の発展に貢献し、猫とそのご家族が来院しやすい動物病院を普及させるという意志のもと、国際猫医学会の公式パートナーとしてわが国のねこ医学会(JSFM)が立ち上がったわけです。
ねこ医学会としてのこの10年間の活動においては、猫の臨床に秀でた動物病院を増やし、猫の診療環境を改善することを目指した「キャット・フレンドリー・クリニック(CFC)」の普及があります。
また、猫の診療に必要な基礎知識を学び、猫の扱いに熟知した動物病院スタッフを育成するためのプログラム「CATvocate」を推進してきました。CATvocateについては、愛玩動物看護師を中心に、その教育がよい方向に進んだとの評価があります。ただし、獣医師への教育については、さらに進めなければならないと感じています。猫医学への理解や興味をさらに高め、正確な知識を深めることが重要です。そうでなければ、世界や他のアジアの国々に対して後れを取りかねません。
ねこ医学会では、1年に1回「猫の集会」を東京で開催しています。そこでは、獣医師、愛玩動物看護師だけではなく、ご家族を対象とした講演も行っています。




さきほど、アジアという話が出ました。石田先生は今夏にアジア小動物獣医師会(FASAVA)の会長に就任されると聞いています。アジアの伴侶動物医療のリーダーとしてどのような活動を進められるのでしょうか。
今年の7月下旬、マレーシアのクアラルンプールで開催の「第12回アジア小動物獣医師会大会(12th FASAVA Congress 2024)」の総会において会長に就任しますが、アジア各国に最新の獣医学を広めるために、セミナーなどさまざまな教育活動を展開する予定です。セミナーの語源はラテン語の「種をまく場所」ですから、アジア中に種をまくように知識を広めていきたいですね。
以前より、韓国や中国などには頻繁に招かれ、いろんな人と交流し、講師を務めるなどしてきましたが、これからもアジア全体を巡りつつ、最新の獣医学の普及に努めます。コロナ禍で活動が滞った4年分を取り戻すためにも、積極的に動き回りますよ。

特に注目している猫医学の動向
猫医学について、特にどのような分野に注目されていますか。
私個人としては、猫の腎臓病に焦点を当て、今よりも長い寿命を実現するための臨床研究に取り組んでいます。猫の腎臓病の病態への理解が進み、血管が失われ、線維化が進む過程などが解明されてきました。特に、血管の内皮細胞の障害が猫の腎臓病において重要ですので、これに対する治療の可能性について研究を進めています。
一方では、猫の腎臓病に対する誤解や不確かな情報が広まっていることを憂慮しています。たとえば、「猫が30歳まで生きる日」といった情報が広まっています。「30歳まで生きる」とは言い切っていない微妙な表現ですが、誤った方向に導くおそれがあります。腎臓病の治療は簡単なものではありませんし、猫の寿命というものはがんやその他の病気によっても影響されるのです。
われわれ獣医師は科学者としてエビデンスに基づいた真実を伝える責任があります。いっそうの研究を通して、着実に猫たちの寿命を向上させていくべきであると考えています。
最近では、猫伝染性腹膜炎(FIP)についてもさまざまな情報が発信されています。FIPの治療などの進展についてはどのように捉えていますか。
新型コロナウイルス感染症に関連し、FIPについて、特に抗ウイルス薬や特許侵害薬に関する情報などが錯綜しています。しかし、これらの薬剤が入手できるとしても、獣医師は慎重な姿勢を示すべきです。
FIPは単なるウイルス病ではありません。ウイルスが原因でアレルギー反応が起こっている病気です。ウイルスが存在しなくなれば、たしかにアレルギー反応がおさまることもあるでしょう。花粉がなくなれば、花粉症の症状がおさまるのと同じですが、アレルギー疾患そのものは治っていないわけです。
FIPというのは、強毒のウイルスが体内に入ることにより免疫が異常な反応を示している病気です。FIPに対するアレルギー反応には、免疫複合体が血管炎を起こす3型アレルギーと、リンパ球の異常で感染細胞を攻撃できないためマクロファージという別の細胞を活性化して病気を封じ込めようとする、結核結節ができるのと同じ4型アレルギーがあります。いずれも、体を守るはずの免疫系が体に対して害を起こすアレルギーという異常で引き起こされます。
私たちは、FIPは単純なウイルス性疾患ではなく、ウイルスによるアレルギー性の炎症性疾患であると考え、ほとんどの症例においてステロイド他の抗炎症薬も使って、免疫を徹底的に抑える治療を行っています。ウイルスが完全に消えても炎症が残っている例もあります。異常な免疫の活性化が残っているのです。FIPに関連して、異常な貧血が起こる血球貪食症候群もあります。免疫系がマクロファージに誤った情報を伝達し、自己の赤血球を破壊してしまう病気です。これも治療においては高度免疫抑制が必要です。
FIPに対して闘えるようになってきたことは確かですが、まだ完全に解明されていない状況です。異常な免疫をどう制御するかは未解明であり、課題が残っています。免疫を制御するための代表的な薬剤としてシクロスポリンがありますが、これを長期間使用するとリンパ腫になる可能性も示唆されていますので、免疫抑制剤の無制限な使用も慎むべきです。いずれにせよ、FIPの病態を深く理解しないまま治療することは危険であり、「FIPは抗ウイルス薬で治る」と認識するのは理解不足からくるものです。
それから、キプロス島の猫が大量にFIPで死亡するというニュースが昨年入ってきました。これは、FIPはふつう猫から猫に移ることはきわめて稀という従来の認識に反するものですが、ウイルスの突然変異により新たなFIPウイルスが生まれてしまったことがわかりました。非常に病原性の強い犬のコロナウイルスが、猫の体内かどこかで猫のコロナウイルスと組換えを起こして、体の中の多くの細胞に感染できる新たな病原性を持った猫コロナウイルス(FCoV-23)というものが生まれてしまったのです。このウイルスはすでに発症猫とともにイギリスには渡ってしまったようですが、世界中に広まらないように願うしかありません。

猫との暮らしを楽しむために
猫の健やかな暮らしのためには、動物病院との連携が欠かせませんが、依然としてその来院率は犬にくらべ低い状況です。
みなさんが認識しているとおり、猫は動物病院を嫌う傾向にあります。犬の匂いや声などが原因ですが、猫専門病院でもストレスを感じることは多くあります。ご家族は、猫が嫌がる様子から自身もストレスを感じ、そのために通院をやめてしまいます。アメリカの猫は比較的フレンドリーですが、ご家族の傾向はやはり同じです。
では、どうすればよいかといえば、猫を動物病院に慣らすことが必要です。具体的なアプローチとしては、1歳までに月に1回程度動物病院に通うことがよいでしょう。車などでの外出やキャリーケースにも慣れ、動物病院の雰囲気になじむことができます。これにより、猫の健康管理や病気の早期発見が容易になります。家の中で暮らしている猫でも、家族以外の見知らぬものはすべて怖がることがあります。たとえば、郵便配達がくれば怖がることもよくあります。こういった見知らぬものには段階的に慣らしていくという方法で、怖がらない猫を育てることは可能です。
猫を動物病院で診てもらうのは、寿命を伸ばす重要な要素です。たとえば、歯周病の早期発見や治療が、腎臓病の進行を防ぐ助けになります。もちろん、ワクチネーションも重要です。初年度から1歳までの適切なワクチン接種が、猫の寿命を伸ばします。特にパルボウイルスに対する免疫が初年度にしっかりとできると、その後はほぼ一生ものの免疫になります。壮年期以降に毎年1回という過剰なワクチンは、歯周病同様に腎臓を悪くする可能性があるので、タイミングを守った的確な接種が重要になります。
普段の暮らしでも、猫が受けるストレスを減らすように心がけてください。不適切な多頭飼育、周囲の騒音といった問題を改善し、猫にとって安全な居場所を提供しなければなりません。
さいごに、猫の飼い主さん、あるいはこれから猫と暮らしたいと考えている方へメッセージをお願いします。
猫派の人と犬派の人に分かれるのは、両者がまったく異なる性格だからです。犬はピラミッド型の社会構造に適応しているので、その中にきちっとはまっていることが重要です。別にトップでなくとも、上に尊敬するものがいて、下には自分を慕うものがいる、というように、日本で会社組織に慣れている人は犬のことがよく理解できてかわいいでしょうね。ただ、家族の一員のだれかを尊敬して、自分よりも弱そうな子どもを下にみてしまうこともありうる動物です。
一方、猫は上下関係ではなく、同じ目線で接する動物です。ご家族に対する思いも「大きな猫がいるな」といったところです。もちろん動物の世界では弱肉強食が基本ですので、猫間の関係は年齢に関係なく、自分より弱いものはいじめる、強いものにはくっつくこともありえます。指令を出されることを好まず、自己決定権を重視し、自身の好みやスタイルを尊重します。いわば、アメリカ人的な性格ですね。アメリカ人とうまく付き合える人は、猫とも仲良く暮らしていけますよ(笑)。
いずれにせよ、猫や犬が健やかに暮らしていけるようにしなければなりませんが、それは猫や犬のためだけではなく、私たちにとっても同じです。
猫や犬との共生が、人の健康に好影響をもたらすことはさまざまな研究から明らかにされています。動物とふれあうことで心拍数や血圧が下がり、ストレスが軽減します。私も大学教員時代、学内でカーッとなる出来事があっても、自宅に戻って猫の姿をみると、心拍数が落ち着くのがわかりました(笑)。健康的に長生きしたいなら、猫や犬と暮らすべきであり、動物と暮らす人の健康保険料を安くしてもらいたいものです。
赤坂動物病院では「70歳からパピーとキトンと暮らすプログラム」を展開しています。パピー・キトンと謳っていますが、プログラムに登場するのは保護犬や保護猫も多く、ほとんどは成犬、成猫です。犬や猫の平均寿命は16~17歳ほどですから、70歳から一緒に暮らし始めても、日本人女性の平均寿命とおおむね合うんです。
ご家族との面接で、動物に対する医療や福祉の実施など重要事項を確認し、一緒に暮らせなくなった場合の対応などについてあらかじめ決めたりしています。とにかく、飼えなくなったらどうしようか、と躊躇する方が多いのですが、主治医を持って動物と暮らすということが大切で、動物病院が将来的にもきちんと面倒をみるということが大切なのです。
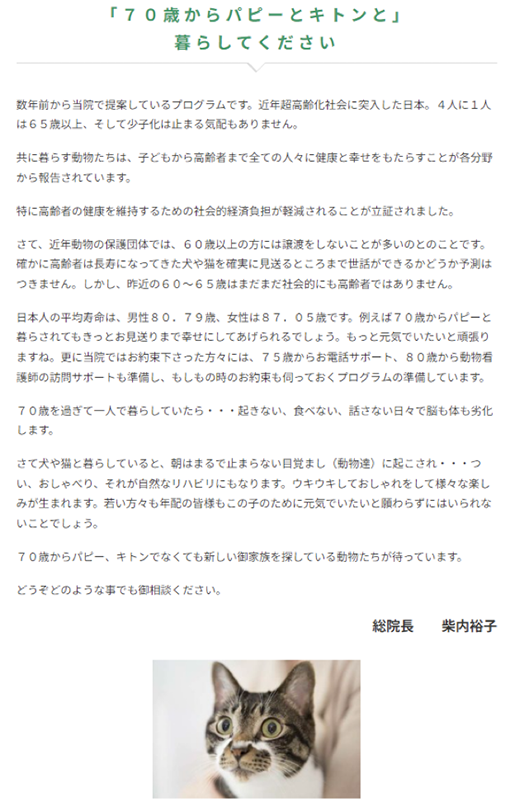
そして、こうした活動を広げていくためには、「動物たちに最良のケアを提供し、ヒューマンアニマルボンド(人と動物の絆)に貢献して、社会をよりよくする」という共通の目標のもと動物病院が協力しあうことが必要です。さまざまな条件にある動物たちに対する責任を共有することが、社会全体の利益につながります。
動物病院の連携には信頼関係の構築が欠かせませんが、それを醸成する場のひとつが、学術集会やセミナーです。これからも、各種学会を主導する立場として、動物病院関係者同士の仲間づくりの場を提供していきます。
ますます旺盛な活動を期待しています。本日はありがとうございました。

石田卓夫(いしだ・たくお)
獣医師、農学博士、赤坂動物病院医療ディレクター。1950年東京生まれ。国際基督教大学卒、日本獣医畜産大学(現・日本獣医生命科学大学)獣医学科卒、東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。アメリカ・カリフォルニア大学獣医学部外科腫瘍学部門研究員を経て、1998年まで日本獣医畜産大学助教授。現在は、日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)名誉会長、日本獣医がん学会(JVCS)会長、ねこ医学会(JSFM)会長、日本獣医病理学専門家協会会員。主な専門分野は、伴侶動物の臨床病理学、臨床免疫学、臨床腫瘍学、猫のウイルス感染症。『伴侶動物の臨床病理学 第3版』、『新 伴侶動物治療指針』シリーズ、『犬と猫の診療基本手技』上・下巻、『犬の内科診療』Part1~3、『猫の診療指針』Part1~3(いずれも緑書房)など多くの獣医学専門書を執筆・監修。