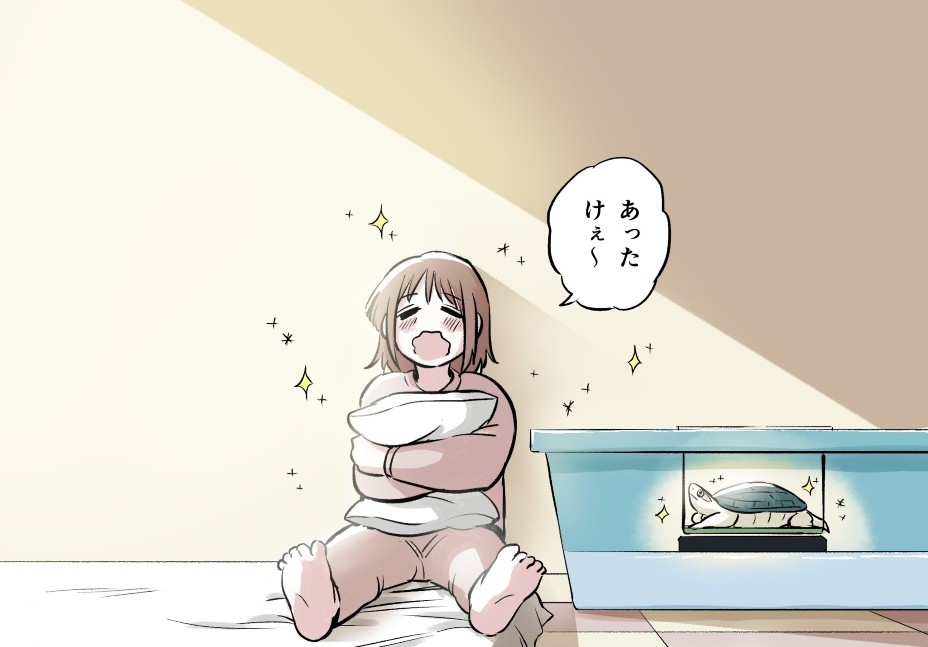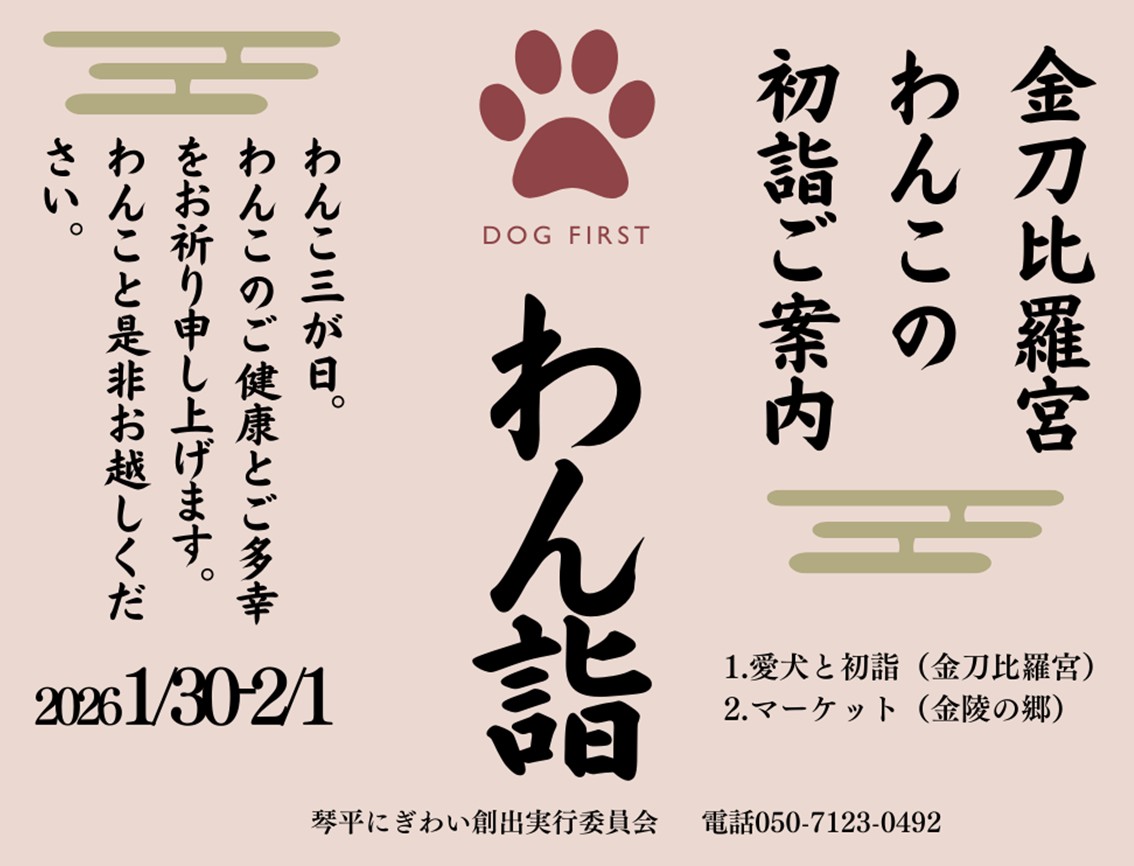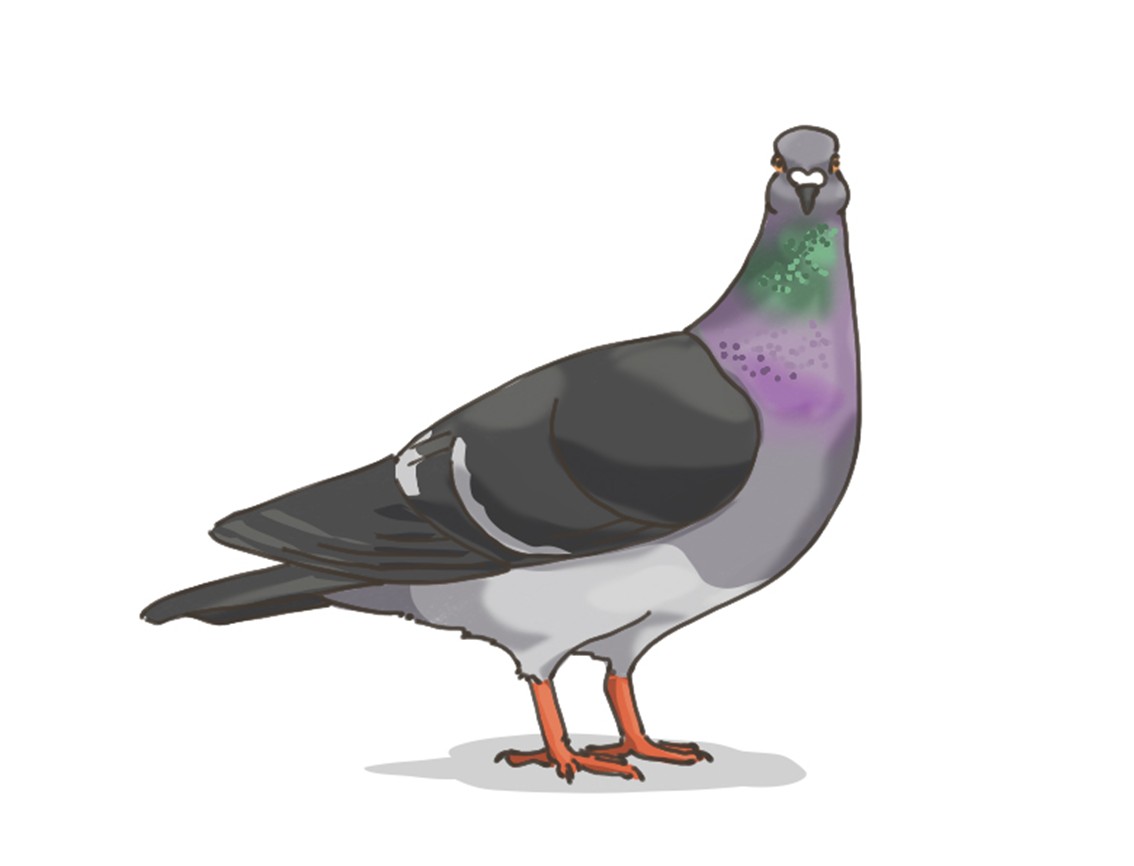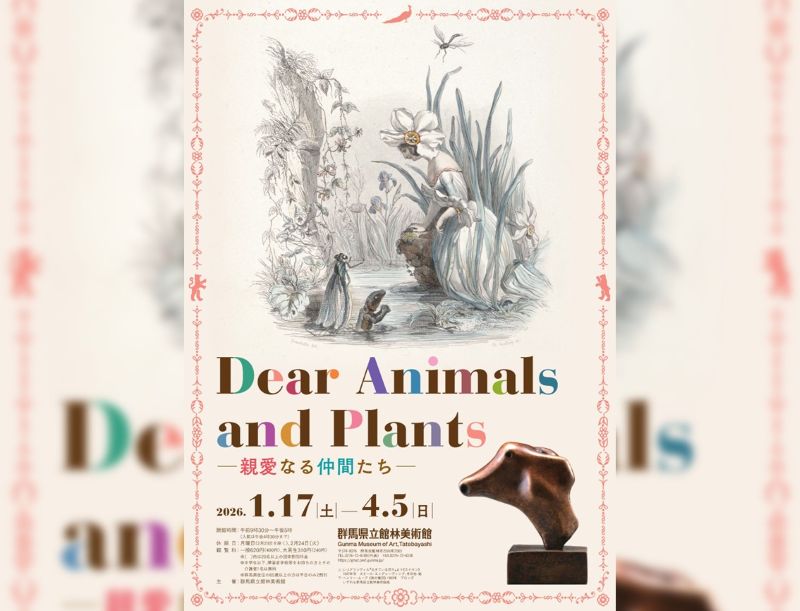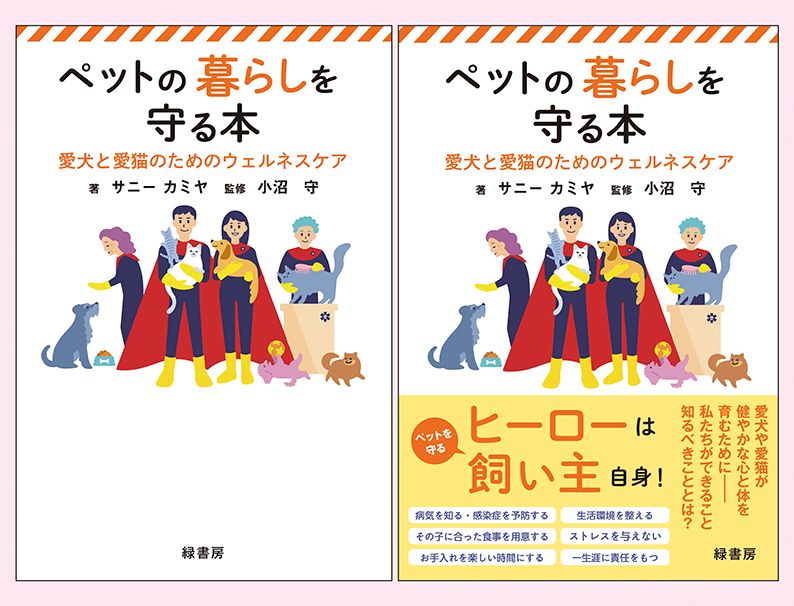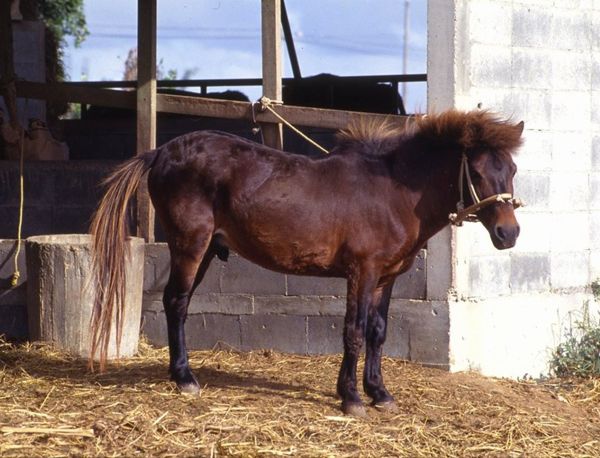ボトルアクアリウムの世界へようこそ ボトルアクアリウムとは?
ボトルアクアリウムは、ろ過フィルターやエアポンプといった大掛かりな機材を使用せずに、手軽なガラス容器でお魚や水草の飼育を楽しむことのできるアクアリウムです。その最大の魅力は、省スペースで場所を選ばない手軽さにあり、水の揺らめきやいきものの動きは、見る人に癒しを届けます。この手軽さが、アクアリウム初心者にとって大きな魅力となり、新たな趣味の入り口として注目されてきました。

しかし、従来のボトルアクアリウムには、その手軽さゆえの難しさが存在しました。ろ過装置を使用しないため、水質が不安定になりやすいという点です。水量が少ないため、魚の排泄物や食べ残しによる水質の変化が急激に起こり、特に初心者にとっては魚を長期間健康に維持することが難しいといわれています。餌の与えすぎや夏場の高水温などの、初心者が陥りやすい行動がトラブルの直接的な原因となり、「簡単だと思って始めたのに、すぐにいきものが死んでしまった」という失敗体験につながりやすい傾向がありました。この根本的な矛盾が、ボトルアクアリウムを挫折する要因となっていました。
ボトルアクアリウムを長く続けるためには、「なぜ水質が悪化するのか」という根本的なメカニズムを理解して、失敗を防ぐ必要があります。
そこで今回は、ボトルアクアリウムの立ち上げやその後のケアについてご紹介します。
立ち上げに必要なアイテムの準備
ガラス容器
好きな形のガラス容器を用意しましょう。園芸用としてもガラス容器は販売されていますが、水を入れることを想定していない容器もあるため、アクアリウム用を選びましょう。
ガラス容器は口が広く、安定した形状のものが適しています。開口部が狭いと、水草を植えることや日々のメンテナンスがしづらくなるため、初めての場合は広いものを選ぶと良いです。
また、水容量は4リットル前後あると扱いやすいです。

底砂
最も重要なのが底砂です。底砂は単なるレイアウト素材ではなく、ろ過フィルターの代わりとなる、ボトルアクアリウムの「生命線」です。魚の排泄物を分解するバクテリアが繁殖するための重要な住処となり、水草の根が張りやすい底砂がおすすめです。
一般的な「砂利(珪砂)」か「ソイル」が選択肢としてあげられますが、初めてのボトルアクアリウムには「砂利(珪砂)」を推奨します。ソイルには栄養分が含まれているものもあり、小さなボトルアクアリウムではコケが生える可能性があるためです。
水草
ボトルアクアリウムの成功の鍵であり主役である水草は、元気が良い水上葉を選びましょう。
もっと手軽に楽しみたい場合は、根を張らずに水中を漂うマツモや少ない光でも育つアナカリス、ウィローモスなどを選んで楽しむこともおすすめです。
元気な水草は、たくさん植えることで見た目の美しさだけでなく、より自然に近い環境を再現でき、酸素供給と水質浄化という生態系を支える重要な役割を担ってくれるのでおすすめです。

カルキぬき
水道水には魚にとって有害なカルキ(塩素)が含まれているため、必ずカルキぬきで中和してから使用しましょう。
いきもの
入れるいきものは、小型で水質の変化や低酸素に強い種類を選びましょう。
あると便利なアイテム
ボトルアクアリウムの維持をより快適にするために、いくつかのアイテムがあると便利です。
・スポイト:底に溜まったフンや食べ残しをピンポイントで取り除くのに非常に便利です。
・ピンセット/ハサミ:水草を植えたり、伸びた部分をトリミングしたりするのに役立ちます。
・LEDライト:水草の育成に必須のアイテムです。直射日光は水温上昇の原因となるため避けましょう。

水槽用のLEDライトを1日8〜10時間点灯させることで水草の光合成を促し、ボトル内に酸素を生み出します。LEDライトは、単なる照明ではなく、ボトルアクアリウムの生態系をまわす「エネルギー源(太陽)」の役割になります。
また、ボトルアクアリウムは水量が少ないため、水温が変化しやすいです。熱帯魚を飼育する場合は、冬場はヒーターを入れてあげましょう。
立ち上げステップバイステップ
水草が主役の環境づくり
ボトルアクアリウムの立ち上げは、一番楽しい時間です。
完成をイメージしながら水草を植えていきましょう。
ガラス容器と底砂の準備
ガラス容器は洗剤を使わずに水洗いをし、底砂はホコリや細かなゴミを取り除くために軽く洗います。容器に底砂を4~5センチメートル程度の厚さで敷きましょう。
水草の植え方
水槽に底砂を入れたら水草を植えてみましょう。植える際は、ピンセットの使用をおすすめします。水草とピンセットを並行に持ち、初めての方は1本ずつ、水草の根本の茎をつまんで底砂に深く植えていきましょう。ピンセットが底に届くように一気に差し込んだ後、ピンセットを握っている手をゆるめてゆっくりと引き抜きましょう。
手前に背の低い水草を、奥に背の高い水草を植えると見た目も整います。

注水
注水はレイアウトを崩さないように慎重に行います。キッチンペーパーを敷いたり、ゆっくりと水を注いだりすることで、底砂が舞い上がるのを防ぐことができます。この際、カルキをぬいた水を入れましょう。
いきものの導入
魚を入れるときは、購入した袋をそのままボトルに浮かべて水温を合わせます。その後、少しずつボトル内の水を袋に加えて水質を慣らす「水合わせ」を必ずしてください。最後に、袋の水は入れずに、魚だけをそっとボトルに移しましょう。
長く楽しむためのボトルアクアリウムのケア
ボトルアクアリウムの維持は、毎日の観察と定期的なケアが鍵となります。
餌の与え方
「餌の与えすぎ」は、ろ過フィルターのないボトルアクアリウムの最大の失敗原因です。食べ残しは水質を急激に悪化させ、酸欠の原因となります。魚が2〜3分で食べきれる量を、1日に2回程度に分けて少量ずつ与えるようにしましょう。
水換え
目に見えない汚れも蓄積するため、定期的な水換えが必須です。基本は週に1回、ボトル内の1/3~半分程度の水を交換します。水換えは、専用の水抜き用品を使うと簡単です。
水を足すときは、レイアウトを崩さないように慎重に行いましょう。ボウルなどを活用してゆっくりと水を注ぐことがおすすめです。

水質変化のサイン
コケの発生は水中の栄養が過剰になったサインです。ガラス面のコケはマグネットクリーナーなどで擦り落とし、水換えを行いましょう。
水面で魚が口をパクパクする「鼻上げ」は、酸欠のサインです。この場合、すぐに水換えを行い、新鮮な水と酸素を供給しましょう。水が白く濁る「白濁り」は、バクテリアのバランスが崩れた初期症状である場合が多く、水換えと様子見で改善を試みます。
日々のメンテナンスは「問題を解決する作業」ではなく「生態系からのサインを読み取る観察行為」として捉えるべきです。この視点の転換が、ボトルアクアリウムを長続きさせる秘訣です。
ボトルアクアリウムにおすすめのいきもの
ボトルアクアリウムに入れるいきものは、小型で丈夫な種類を選ぶのが鉄則です。特に、酸欠に強い魚や、環境の変化に強いエビや貝がおすすめです。
アカヒレ
水質の変化や低水温にも強く、ヒーターなしでも飼育が可能で初心者にもおすすめです。
メダカ
日本の環境に適応しており、丈夫で飼育しやすい魚です。ヒーターも不要で、ボトルアクアリウムにぴったりです。

ベタ
「ラビリンス器官」という特殊な呼吸器を持つため、水中の酸素が少なくても水面から空気を吸うことができ、単独飼育にも適しています。一般的に「ボトルで飼える魚」として知られていますが、排泄物が多く水を汚しやすいため、水換えを週に2回に増やすなどの対応が必要となります。冬はヒーターを入れましょう。

ミナミヌマエビ/ヤマトヌマエビ
ボトル内のコケや他の魚の食べ残しを食べてくれる「お掃除屋さん」です。ミナミヌマエビは繁殖が容易で変化を楽しめるため、初心者にもおすすめです。

石巻貝
コケ取り能力に優れており、水槽のガラス面に付着したコケを効率的に食べてくれます。
おわりに
ボトルアクアリウムは、いきものとのふれ合いだけでなく、自然の営みを身近で学ぶことができます。水の循環や光合成、生物間の相互作用など、教科書で学んだ知識を目の前で観察することができます。
何より大切なのは、失敗を恐れないことです。たとえコケが生えたり、水が濁ったりしても、それは「なぜそうなったのか?」を考えるきっかけになります。いきものの観察を通してその原因を探り、自分で解決策を試す。この過程こそが、ボトルアクアリウムの真の醍醐味であり、自然との付き合い方を学ぶ貴重な経験となります。

※もっと詳しく知りたい方はこちらから!
【執筆】
ジェックス株式会社
観賞魚用品を中心に、犬・猫、小動物、爬虫類用の飼育用品の開発、製造、販売を手がけるペット用品メーカー。
ホームページ:https://www.gex-fp.co.jp/
Instagram:@megreen_gex
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!