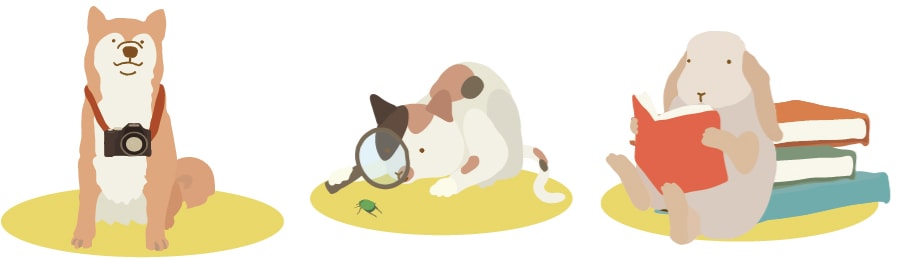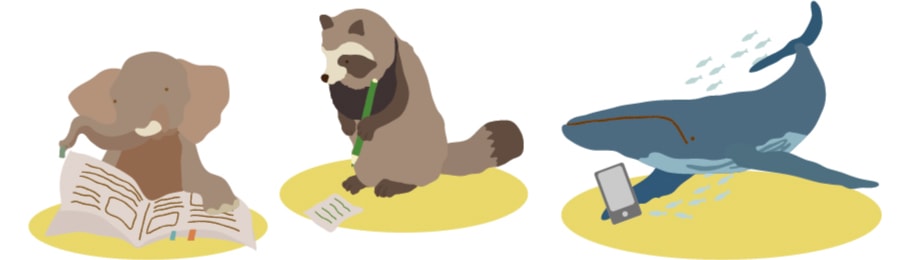カモ類は、鳥のなかでも比較的大きな体をしています。そして湖沼や農地、海辺など開けた場所で観察できるため、よく目立ちます。
目立つということは、いるかいないか、多いか少ないか、が人から見て分かりやすいということです。これは、分布や個体数を容易に把握できることにつながりますから、環境の変化を知るための指標として重要な条件の1つです。
また、カモ類は地球上の水域に広く分布しています。農地で落ち籾や草本類など植物質のものを食べる種から、湖沼や海辺で潜水して水生植物や魚類、甲殻類などを食べる種までいます。広い範囲に生息し、地域の生態系の基盤となっている多様な食物をとっているため、生息地の環境変化の影響を受けやすいのです。つまり、カモ類の変化は、その地域の環境変化を知るための指標になりやすいと言えます。
カモ類からみた湖沼の環境
カモ類は、行動パターンや採食方法に応じていくつかのグループに分類できます。昼間は沼で休息し、夜間に農地で採食する沼外採食性カモ類(マガモ、カルガモ、コガモなど)、昼間に沼で水生植物を採食する沼内植物食性カモ類(ヒドリガモ、ヨシガモ、オカヨシガモなど)、魚類や甲殻類を採食する沼内魚食性カモ類(ホオジロガモ、カワアイサ、ミコアイサなど)などです(写真1)。また、給餌により人の影響を受ける給餌依存種(オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ)もいます。

こうしたグループごとの割合をみることで、湖沼の環境を知ることができます。
たとえば、宮城県北部の伊豆沼・内沼で給餌依存種を除いた3つのグループの占める割合を見ると、マガモやカルガモなどの沼外採食性カモ類が全体の9割近くを占めました(図1)。

沼外採食種:マガモ、カルガモ、コガモ。沼内植物食種:ヒドリガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ。沼内魚食種:ホオジロガモ、カワアイサ、ミコアイサ(嶋田2020より改変)
一方で、水生植物や魚類など沼の食物資源に依存する種は少ない割合でした。すなわち、伊豆沼・内沼では、マガモやカルガモなど沼外の農地で採食するカモ類が優占していて、水生植物や魚類を採食するカモ類にとっては魅力の少ないことが分かります。つまり、それらの食物資源が少ない場所になっているのです。その要因を見ていきましょう。
沼内植物食性カモ類
ヒドリガモなどの沼内植物食性カモ類は、水生植物のなかでも特に沈水植物(写真2)を好みます。しかし、伊豆沼・内沼の沈水植物群落は、水質汚濁などによって、過去30年ほどで著しく衰退しました。ある程度まとまった数の沈水植物(水底に根を張り、水中で生育する植物)は、伊豆沼の南岸の限られた場所にしか生息していません。ハスなどの水生植物は沼を広く覆いますが、ヒドリガモのような沼内植物食性カモ類の好む沈水植物が少ないことが、これらの鳥たちの少なさに関係していると考えられます。

一般的に、水質汚濁は沼の栄養塩類が増加することで生じます。栄養塩類の増加にはさまざまな原因があります。伊豆沼・内沼では、1960年代に大規模な干拓があり、沼の面積が半分ほどに減りました。干拓された場所は、マコモなどの抽水植物(水底に根を張り、一部が水上に出た状態で生息する植物)が多く生えていた浅い水域で、それらが沼へ入ってくる栄養塩類を吸収していました。しかし、干拓されたことで、栄養塩類を吸収する場所がなくなり、沼を浄化する機能がなくなったのです。
また、人のライフスタイルも変化しました。かつて、マコモは牛の食物として、ヨシは茅葺屋根の材料として使われ、魚介類は貴重なタンパク源として食されるなど、人は沼の産物を生活のなかで活用していました。マコモやヨシ、魚介類に取り込まれた沼の栄養塩類は、人によって沼の外へ運ばれることで、その分沼の栄養塩類が減ります。それは富栄養化の進行を防ぐことにつながっていたのです。
沼の栄養状態は、栄養塩類の流入と排出のバランスによって、貧栄養の状態から富栄養の状態まで変化します。伊豆沼・内沼では、栄養塩類を吸収する場所がなくなり、また人為的にも取り出すことがなくなりました。一方、流入河川を通じて、農業排水や畜産排水、家庭排水などが入ってくることで、沼の栄養塩類は排出よりも流入が多くなり、増加の一途をたどったと考えられます。
沼内魚食性カモ類
ミコアイサなどの沼内魚食性カモ類は、外来種であるオオクチバス(通称ブラックバス)に大きく影響を受けました。オオクチバスは他の魚類を捕食するスペシャリストなのです。
伊豆沼・内沼には漁業協同組合(漁協)があります。総漁獲量は1990~1995年までは28~37トンでした。しかし、0.7トンのオオクチバスが漁獲された1996年以降、オオクチバスの急増にともない、総漁獲量が1~2年で約10トンにまで減少したのです。なかでも、絶滅危惧ⅠA類のゼニタナゴをはじめとするタナゴ類や、モツゴ、タモロコなどの小型魚類の漁獲量の減少は著しいものでした。これらの魚類は、オオクチバスに捕食されたことが分かっています。
こうした魚類相の大きな変化は、それを食べる魚食性の鳥類にも大きな影響をおよぼしているはずです。そこで、潜水性の主な魚食性鳥類である、カンムリカイツブリ、カイツブリ、ホオジロガモ、ミコアイサ、カワアイサへのオオクチバスの影響を調べるため、オオクチバス侵入の前と後とで、その個体数を比較しました。
その結果、最も大きく減少したのはカイツブリで減少率93%、次いでミコアイサが69%、その他の種で23~38%でした。カイツブリとミコアイサで減少率が特に大きかった理由は、他の3種に比べて体が小さく、くちばしが短いためです。短いくちばしをもつ両種は、小型魚類を主に採食しますが、その小型魚類をオオクチバスによって食べられてしまい、彼らの食物が減ってしまったのです。食う食われるの関係によって、オオクチバスは魚だけでなく、鳥にまで影響をおよぼしていたのです。
オオクチバスの捕食によるゼニタナゴの危機的な状況を受けて、2003年に市民や研究者が集まり、「ゼニタナゴ復元プロジェクト」が始動しました。2004年には「バス・バスターズ」と呼ばれるボランティア団体が結成され、さまざまな方法によって卵、稚魚、成魚とオオクチバスの生活史全体にわたる総合的な駆除を行っています(写真3)。この活動で、伊豆沼・内沼のオオクチバスは大きく減少し、現在では数を少なく抑えた状態が続いています。2009年からは、モツゴなどの魚類の回復が始まり、近年ではゼニタナゴの繁殖も確認されるようになってきました。そして、個体数が減少していたミコアイサが、魚介類の回復とともに再び増えはじめたのです。

このように、カモ類を通して伊豆沼・内沼を見ると、日本最大級のガンカモ類の越冬地と言われながらも、沼で水生植物や魚類などを食べるカモ類が少なくなってきており、その生態系の劣化が見てとれます。しかし、オオクチバスの駆除を含め、伊豆沼・内沼では長年にわたって生物多様性の回復を目指した自然再生事業に取り組んでおり、徐々にその成果が上がってきています。
鳥インフルエンザ対策
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスによる鳥の感染症です。ウイルスの表面にある糖タンパク質のヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の種類によって、亜型が分類されています。ガンカモ類の多くは、この鳥インフルエンザウイルスをもっていますが、通常はガンカモ類にも家禽にも病気を起こしません。
こうしたウイルスが家禽に感染し、家禽の間で感染を繰り返すうちに、家禽に対して高い病原性を示すウイルスに変異したのが、高病原性鳥インフルエンザウイルスです。これまで、H5亜型とH7亜型から高病原性のウイルスが出現しています。テレビのニュースなどで毎冬話題にあがり、大量のニワトリが殺処分されてしまう鳥インフルエンザとは、この高病原性のタイプを指します。
2008年4~5月にかけて、秋田県、青森県および北海道において、オオハクチョウの死体からH5N1型高病原性鳥インフルエンザが検出されました。H5N1型に感染した個体から排出される糞に含まれるウイルスは、水を介して他の個体へも感染します。そのため、ガンカモ類が集まる給餌場所は、一気にクローズアップされました。これに伴い、東北地方の多くの越冬地で、ガンカモ類への給餌の禁止や縮小の動きが広がりました。
伊豆沼・内沼での対応
伊豆沼・内沼も調査が開始されました。オオハクチョウの死体から高病原性鳥インフルエンザが検出される前年の冬にあたる2007年から2008年にかけて、宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター前の給餌場所で、ガンカモ類の個体数と給餌量を毎日記録しました。ガンカモ類が、1日当たり必要とする代謝エネルギー量と、給餌によって与えられたエネルギー量から、給餌への依存率を推定したのです。
給餌場所に集まったガンカモ類は、オオハクチョウやオナガガモ、キンクロハジロ、ホシハジロの4種でした。オナガガモが最も多く、最大1,500羽、次いでオオハクチョウが110羽でした。月別の給餌量を見ると、12月が1,279キログラムと最も多く、そのほとんどは籾や玄米でした。このときは宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団の職員による給餌が行われていました。また、来館者による給餌は、専用の餌によって行われていました。古米に圧力をかけて膨らませたもので、100グラム程度が1袋に詰められており、観光客などはこれを募金として購入して給餌します。
月別に見ると、11月と3月は給餌への依存率が100%に近く、与えられた給餌だけでガンカモ類は1日の代謝量を賄えていました。しかし、12月には72%、厳寒期の1~2月には35~40%にまで低下し、給餌だけでは1日の代謝量を賄えていませんでした。オナガガモは、この不足分を補うべく夜間農地で採食していたと考えられ、厳寒期の早朝、給餌場所にオナガガモの姿はありませんでした。
給餌の縮小
この調査結果から、鳥インフルエンザ対策として何ができるのかを考えました。
当時、給餌場所に集まるガンカモ類は、全てのエネルギーを給餌から得ているわけではありませんでした。言い換えると、彼らは都合のよいときだけ給餌を利用し、人をうまく使っていました。また、与えられた給餌の大部分は、財団職員による大規模給餌が占め、来館者によるものはわずかなものでした。
さらに、来館者による餌づけは、人がある程度鳥を身近に観察できる機会を生んでいました。鳥は人から遠い場所をすばやく移動するため、ふだんは間近でゆっくり姿を見ることができませんが、給餌はそれを可能にします。こうした機会は、特に子どもたちが鳥への親近感を深めることにつながるでしょう。
これらのことを踏まえて、来館者による給餌だけを継続することにしました。
結果として、給餌の総量は減ることになりました。もちろん、この給餌縮小についての影響がどのようなものかについても、きちんと評価しました。
通常の給餌を行った2007年末から2008年初頭と、給餌を縮小した2008年末から2009年初頭で、月ごとの給餌量を比較すると、給餌量はおよそ80%減少しました(図2-1)。ガンカモ類は、この給餌量の大幅な減少に対して直接的な反応を見せ、オナガガモで79%、オオハクチョウでは74%が減少し、ホシハジロとキンクロハジロはほとんど見られなくなりました(図2-2)。


この給餌の縮小によって、給餌場所でカモ類を身近に観察できる場所を維持しつつ、鳥には給餌場所以外での採食を促すことができました。結果的に、給餌場所に鳥が集中する程度を減少させて群れの分散を図り、鳥同士での鳥インフルエンザウイルスの拡散リスクを軽減できました。この給餌方法は現在も継続中で、それに加えて、給餌場所やセンターの入り口には靴の裏を消毒するマットを置いています。
農業被害対策
伊豆沼・内沼の周辺の農地では、ハス田をつくってレンコンを生産している農家があります。いわゆる人が食べる食用レンコンで、白い花を咲かせます。ちなみに沼にはハスが自生しており、ピンク色の花を咲かせます。こちらは人ではなく、オオハクチョウが食べます。
そのレンコン農家から、カモ類によるレンコン食害について相談されたことがありました。食害にあったレンコンを見ると、かじられた跡があり、出荷できなくなっていました。相談の結果、音を鳴らして鳥を追い払う爆音機を使うことにしました(写真4)。通常は、音の出る部分を空や田畑に向けて使用する機械ですが、これをハス田に向けました。爆音機で音を出すと水面が波立ちます。音と水面の波立ちのダブルパンチで、カモを追い払おうという方法です。

この方法は効果的だったようで、農家からは被害がかなり減ったと言ってもらえました。被害が完全になくなったわけではありませんが、この農家は「伊豆沼・内沼という鳥がたくさん来るところでつくっているのだから」と、ある程度の被害を許容してくれています。研究の中で、カモ類を捕獲する必要があったときに、網を設置するハス田を貸してくれたのもこの農家でした。生計に影響を及ぼしているにもかかわらず、そのカモ類への理解と広いお気持ちは本当にありがたい限りです。
フライウェイの保全
これまで述べてきたことは越冬地でのことでした。しかし、国境を越えて長距離移動するガンカモ類を保全するためには、越冬地、中継地、繁殖地など、渡り経路内における生息地全体を保全していく必要があります。繁殖地、中継地、越冬地を含めた渡り経路全体を「フライウェイ」と呼びます。
フライウェイは世界で9つに分けられます。アジア・太平洋地域には、「中央アジアフライウェイ」、「西太平洋フライウェイ」、そして日本が含まれる「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」の3つがあります。東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ(EAAFP)は、当地域の渡り鳥やその生息地を保全するために、さまざまな関連機関と国際的に連携したり、連携するための枠組みの提供をしたりしています。EAAFPには、ガンカモ類、シギ・チドリ類、ツル類の3つの作業部会があります。
EAAFPの日本国内でのとりまとめ役としては、ガンカモ類国内生息地ネットワークや、生息地の管理者支援などを目的につくられた、東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワーク(ガンカモ類)支援・鳥類学研究者グループ(JOGA)があります。近年、ガンカモ類の研究を強化するために、ガンカモ類作業部会国内科学技術委員会と呼ばれる枠組みもできました。これらの機関が連携し、ガンカモ類の研究と保全の両面からの取り組みが進んでいます。
さて、全3回でカモについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。カモ類は、身近にいてもわかっていないことが多い、とても興味深い鳥です。次に見かけたときには、ぜひじっくり観察してみてください!

[出典]
図1、2-1、2-2:嶋田哲郎『知って楽しいカモ学講座』(緑書房)
【執筆者】
嶋田哲郎(しまだ・てつお)
(公財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 研究室長。1969年東京都生まれ。1992年東京農工大学農学部環境保護学科卒業、1994年東邦大学大学院理学研究科修士課程修了。1994年宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団研究員に着任。2006年マガンの越冬戦略と保全をテーマに、論文博士として岩手大学より博士(農学)号を取得。2020年より現職。専門は鳥類生態学、保全生態学。ガンカモ類を中心とした水鳥類の生態研究のほか、オオクチバス駆除や水生植物の復元など沼の保全、講話や研修会、自然観察会など自然保護思想の普及啓発に取り組む。2013年愛鳥週間野生生物保護功労者日本鳥類保護連盟会長褒状受賞。著書に『ハクチョウ 水べに生きる』(小峰書店)、『鳥の渡り生態学』(分担執筆、東京大学出版会)、『知って楽しいカモ学講座』(緑書房)など。