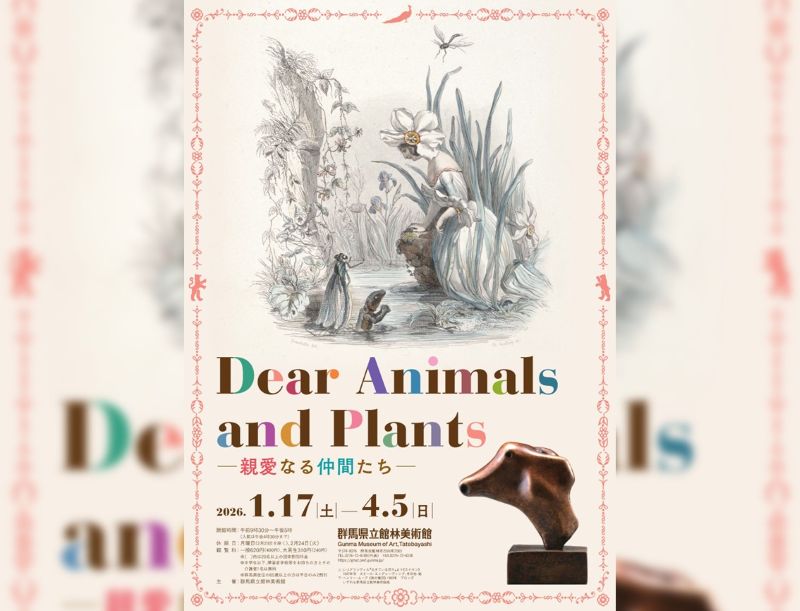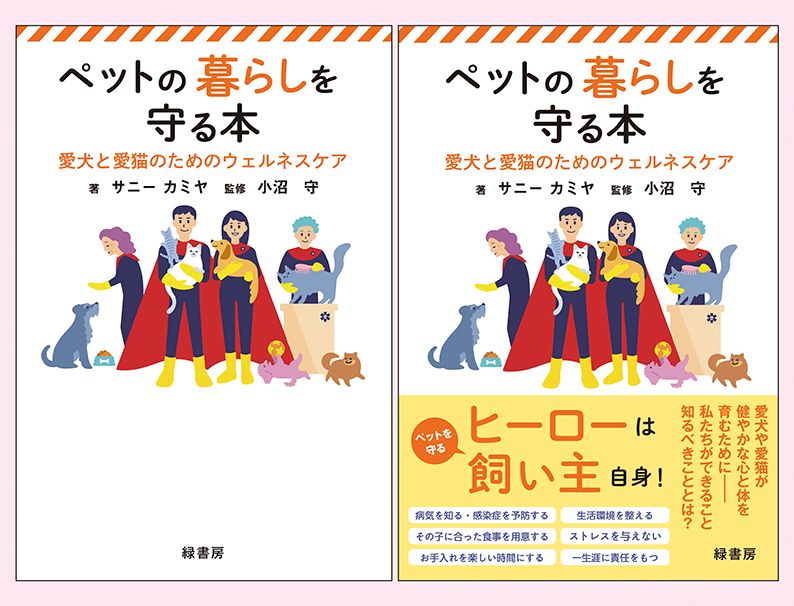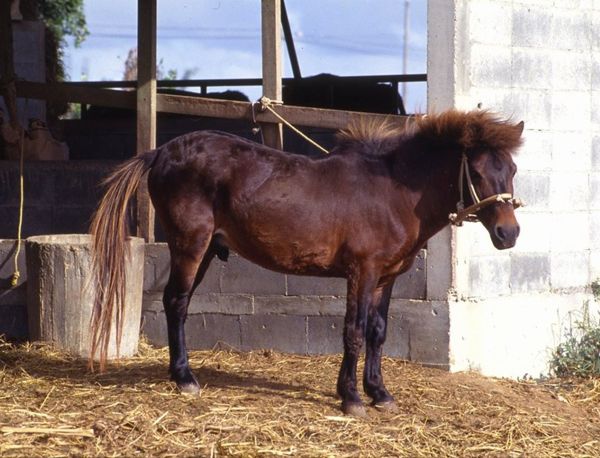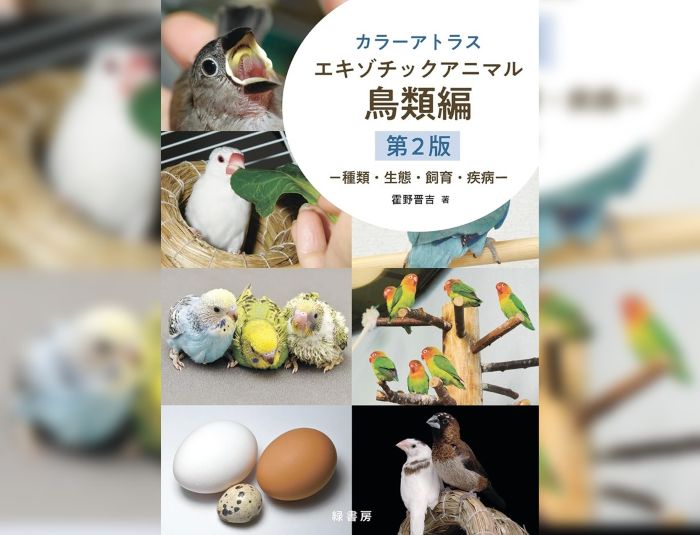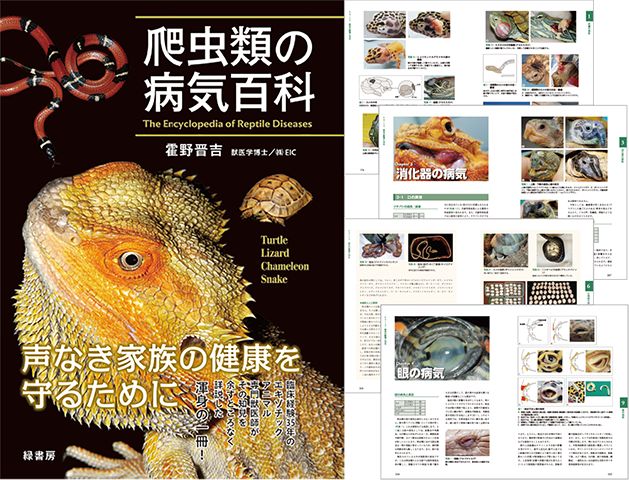子どものころの夏休み、カブトムシやクワガタムシを探すために家族と出かけた雑木林で、驚くほど大きなチョウが飛び回っているところを見ました。それまで、大型のチョウといえばアゲハチョウくらいしか見たことがなかった私には、梢の方で力強く羽ばたくダイナミックな飛び方や、時折見せる青紫色の輝きがとても新鮮で印象に残りました。それがオオムラサキでした。
国蝶オオムラサキ
オオムラサキの活動が見られるのは夏の雑木林です。地域にもよりますが、7〜8月に見られることが多いようです。

オスは、翅を広げた大きさが9センチメートルほどあり、その翅は名前の通り、青紫色に輝いています。翅を開閉させたときには、黄色や白の斑紋と相まって素晴らしいものになります。一方のメスは、茶褐色でやや地味ではありますが、翅を広げた大きさが10センチメートルほどもあり、とても迫力があります。オオムラサキは、その大きさや美しさから1957年に日本昆虫学会によって、日本の「国蝶」に定められています。
オオムラサキは、主にクヌギやコナラなどのブナ科の木に集まり、その樹液を吸います。

夏の日中、幹から滲み出た樹液にカナブンやカブトムシ、スズメバチなどが集まる中、オオムラサキもその一角に加わっているところをよく見かけます。他の虫たちに接近すると、バタバタと翅を開閉して威嚇します。それでも周囲の虫たちが動かない場合には、隙間に頭をぐいっとねじ込んで、長い口吻(こうふん)を器用に差し入れて樹液を吸う、なかなかにたくましいチョウです。
動物の糞尿に集まることもあり、そこから摂取したアンモニアからアミノ酸(タンパク質)を生成して、繁殖能力の向上に役立てていると考えられています。

縄張りと求愛
オオムラサキのオスは、強い縄張り意識を持っています。見通しの良い高い木の葉に止まり、他のオスが近づくと一気に飛び立って空中戦を繰り広げます。

このとき、バサバサと力強い羽音を響かせながら追いかけるのですが、これは相手が同種のオスである場合だけでなく、侵入者に対して即座に飛び立って迎え撃つという、少し過激なものです。ときにはトンボや他のチョウ、さらにはツバメなどの鳥にさえ突進していくことがあり、その気性の荒さはチョウのイメージを覆すものかもしれません。
そんな激しい縄張り行動のためか、シーズン後半になると翅のあちこちが破れたり、擦れて色褪せたりした個体が目立つようになってきます。オオムラサキ本来の美しさは影を潜めますが、そんな姿にも貫禄と迫力を感じられます。
また、メスが縄張り内に現れると、オスは求愛行動を始めます。メスの近くに止まって正面からじわじわと接近し、互いの触角が触れるように動かします。メスが逃げなければ腹部を曲げて近づき、メスの腹部の先と接触させて交尾をします。交尾は数時間にも及ぶようです。

ただし、メスは羽化直後から交尾が可能なので、メスはすでに交尾を済ませていることが多いようです。そのため、プロポーズはうまくいかないことがよくあります。
産卵と幼虫、そして越冬
交尾を終えたメスは、エノキの木を探して枝や幹、葉の裏側に数十から100個ほどの卵を並べるように産みつけます。

卵は直径1ミリメートルほどあり、チョウの卵としては大きな方だといえるでしょう。同じようにエノキを食草とするゴマダラチョウは、卵を一粒ずつ産みつけることが多いので、産みつけられた卵の様子からもオオムラサキだと判別できます。
産卵後、6〜10日ほど経つと、卵が孵化して小さな幼虫が現れます。孵化した幼虫は、まず卵の殻を食べて自らの栄養とし、その後からエノキの葉を食べ始めます。
この孵化したばかりの幼虫を1齢幼虫といい、脱皮をするごとに2齢、3齢と進んでいきます。2齢幼虫になると、頭部に特徴的な2本の角と背中に4対の小さな突起が目立ち始めます。
そして、4齢幼虫で秋の終わりを迎えると、エノキの根元に降りて落葉の裏に糸を吐いて体を固定し、何も食べず、ほとんど動くこともなく冬を越します。このときの幼虫は、体が褐色で皮膚が硬くなっており、冬の寒さに耐えられるようなります。

春、活動の再開
長い冬を越した幼虫は、エノキの葉が芽吹き始める4月中旬ごろ、活動を再開します。落ち葉の下から這い出た幼虫は、エノキの幹を登って若葉の出た枝先に向かい、ふたたびその葉を食べて成長を始めます。やがて脱皮をして緑色の5齢幼虫、さらには6齢幼虫(終齢幼虫)まで成長します。

たっぷりと葉を食べて成長した6齢幼虫は、葉の裏に糸を吐いて台座を作り、頭を下にしてぶらさがります。この状態を前蛹といい、さらに2日経つと脱皮して蛹になります。オオムラサキの蛹は、緑色の体にうっすらと白い粉を帯び、木の下から見上げると、葉の裏側に同化したようでほとんど目立ちません。これは外敵に見つからないための見事な擬態といえるでしょう。

そして空へ
蛹になって約2週間経つと、成虫の体が透けて見えるようになっていきます。そしてある日、背中の部分が縦に割れて、成虫が脱出してきます。殻から出た成虫はまだ翅が伸びていませんが、蛹の殻や付近の枝にぶらさがって翅を伸ばし、見慣れたオオムラサキの姿になります。

羽化は6月下旬ごろからで、まずはオスの羽化がはじまり、10日ほど遅れてメスの羽化がはじまります。羽化した成虫はやがて大空へと飛び立ち、そしてまた冒頭のように、オスたちの激しい縄張り争いやメスとの求愛の儀式が繰り広げられます。
おわりに
オオムラサキの暮らしは、食草であるエノキはもちろんのこと、樹液を出すクヌギやコナラなどが生えている、いわゆる雑木林の環境に支えられています。そうした林は、かつては人里にも広く見られたもので、オオムラサキは今よりも身近なチョウでした。
しかし、雑木林が宅地開発や杉の植林によって失われ、農業の衰退とともに放置されて荒廃していきました。そのため、オオムラサキは生活の場を失い、すっかり数を減らしてしまいました。
幸いなことに、近年では地域によって保護活動が進み、エノキの植樹や雑木林の整備によって個体数を回復させている場所もあるようです。課題はいろいろとありますが、あの美しい紫色の翅と力強い羽音が私たちの前から消えることがないように、彼らの暮らす環境を未来につなげていきたいものです。
【写真・文】
尾園 暁(おぞの・あきら)
昆虫写真家。
1976年大阪府生まれ。近畿大学農学部、琉球大学大学院で昆虫学を学んだのち、昆虫写真家に。日本自然科学写真協会(SSP)、日本トンボ学会に所属。著書に『くらべてわかる トンボ』(山と渓谷社)『ぜんぶわかる! トンボ』(ポプラ社)『ハムシハンドブック』(文一総合出版)『ネイチャーガイド 日本のトンボ』(同上・共著)など。
X:@PhotomboOzono
Instagram:@akiraozono_photography
ブログ:湘南むし日記
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!




















.jpg)