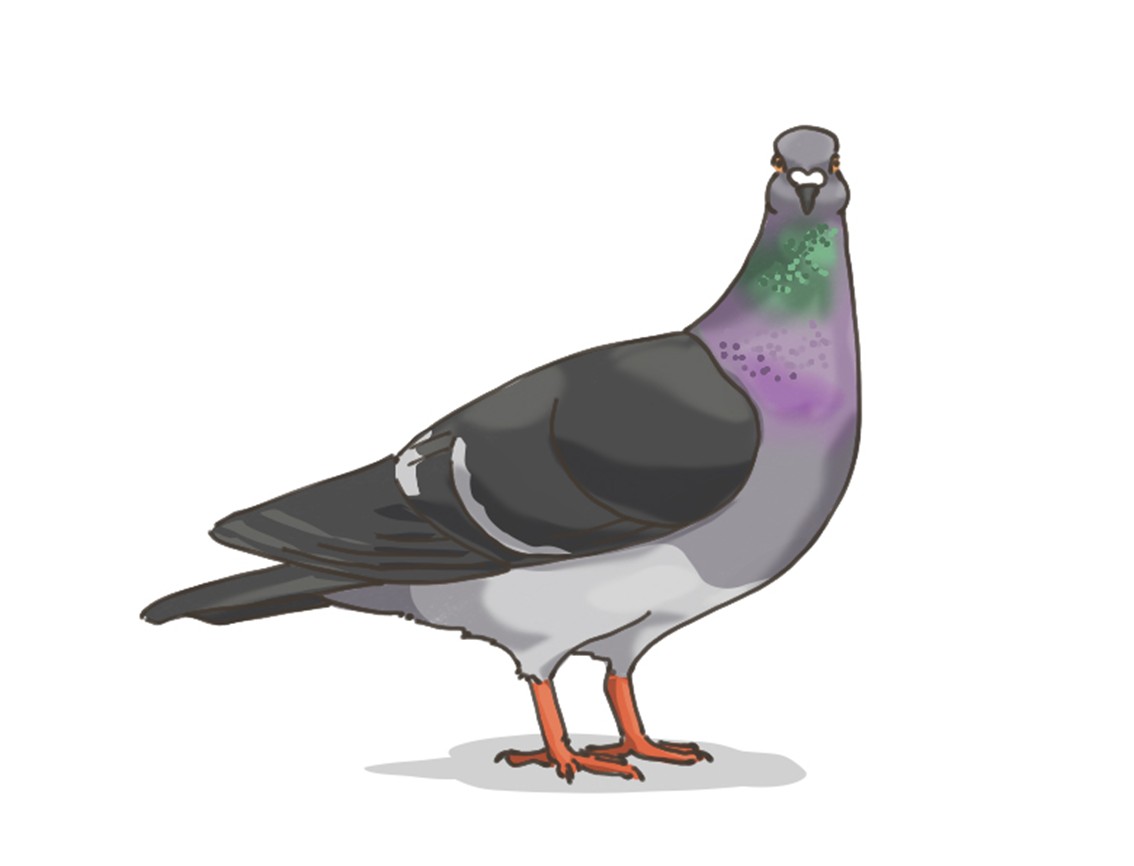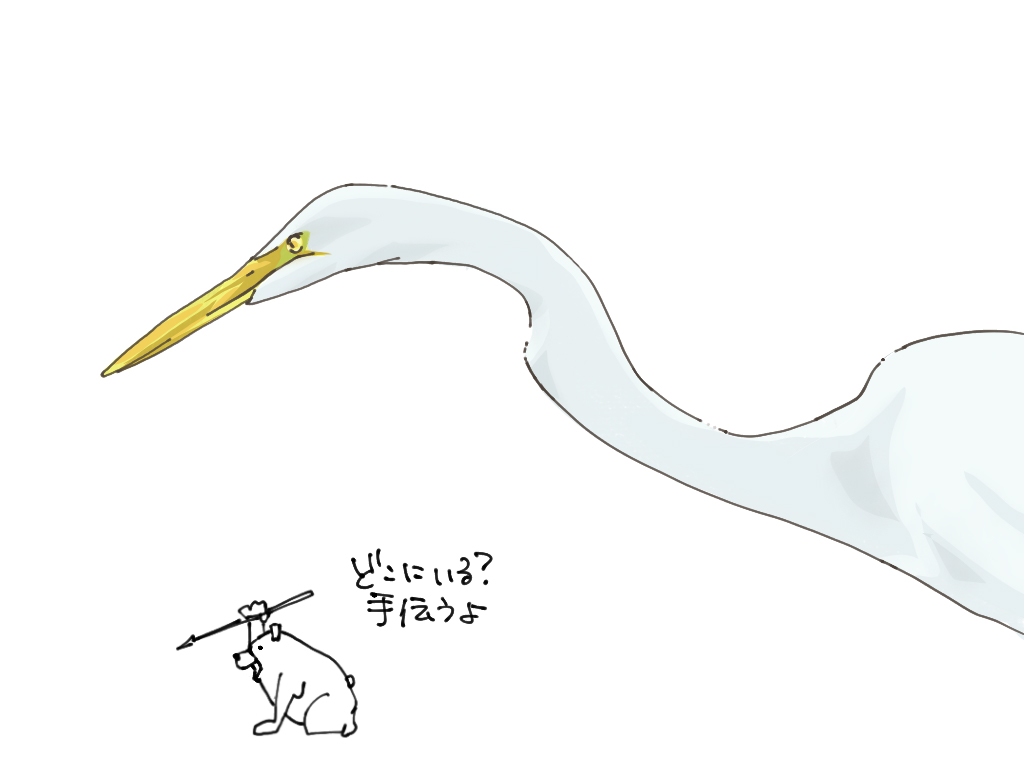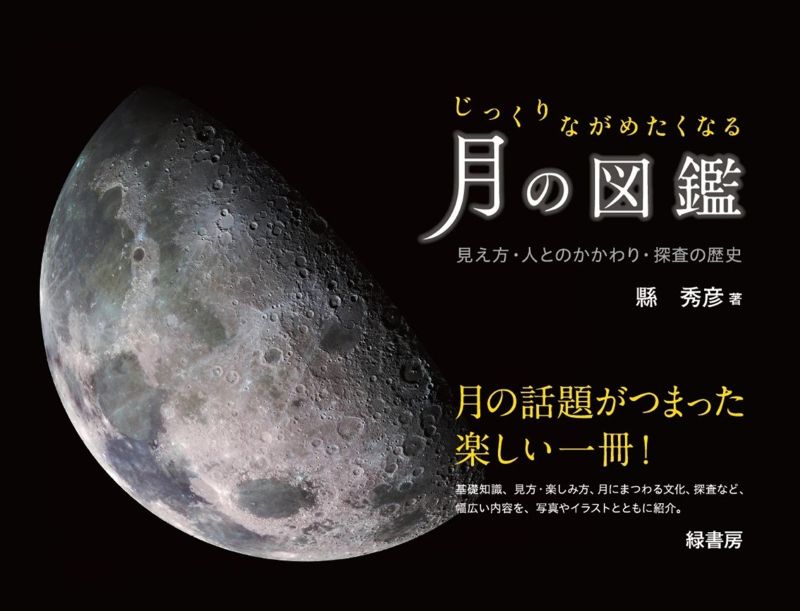もっとも身近な猛禽、トビ
予想もしていなかった相手に大事なものを奪われた(横取りされた)ことを示す例として、「鳶に油揚げをさらわれたよう」ということわざがありますが、これは実話がベースになっています。
江戸時代の百科事典である、寺島良安の『和漢三才図会』(正徳3年/1713年序)のトビの解説にも、「人が手に持っている魚物や豆腐などを掴む」とあります。
現在、江ノ島を中心とする湘南地域では、手に持つものをトビに盗られないように注意を促す看板も立てられていますが、江戸時代、もしくはそれ以前から、町中において、買ったばかりの食べ物などをトビにさらわれる事件が少なからずあった、ということなのでしょう。
「馬の耳に念仏」や「犬も歩けば棒に当たる」など、ことわざにおいて、「たとえ」として動物が登場するケースも多く見られますが、「トンビにアブラゲ」は希有な例で、事実がもとになって成立したものでした。
(とはいえ、もしかしたら「猿も木から落ちる」も、実例があったかもしれません。)
そんな接点からもわかるように、江戸時代も今も、トビはもっとも身近な猛禽です。
トビの生活スタイルは古代から変わらず、人間との距離も基本的に変化していません。
天を舞う姿を見たり、鳴き声を聞いたりすれば、子どもでもそれがトビとわかります。親がトビだと教えるからです。
時代の流れの中、日本人の暮らしはダイナミックに変化しましたが、トビは昔のままです。その変わらぬ姿に、ほっとする人も少なくないかもしれません。

神話では神の遣いだったものの、しだいに地位が低下
そんなトビは、歴史の始まりから日本人と接点をもっていました。
『日本書紀』の神話の部分には、カムヤマトイワレビコのミコト(のちの神武天皇)のもとに飛来し、その弓の上端に止まった黄金に輝くトビ(金鵄:きんし)が戦局を一変させた逸話も残されています。
このトビは、天(高天原:たかまがはら)が送った神の遣いでした。
ここから、当時のトビがカラス(八咫烏)と並ぶ神聖な存在であったことがわかります。歴史の始まりのトビは、このような誉あるイメージでした。

しかし残念なことに、その後、トビの存在感は軽くなっていきます。
たとえば平安時代を代表する随筆『枕草子』(西暦1000年ごろ成立)の中で清少納言は、「トビやカラスなどはどこにでもいる鳥なので、よく見ようとしたり、声に耳を傾ける人はいない」と語っています。
ただしこれは、「存在が当たり前すぎて、だれも関心をもたない」という主張のようで、トビの所業について、とりたてて悪い印象をもっていたわけではないようです。
こうしたトビのイメージは江戸時代になっても変わらず、先にもふれた『和漢三才図会』には、「すべて鳶・鴉は害あって益なく、しかも多くいる鳥で、人に憎まれるものである」と記されています。
変わらないというより、少し悪くなった印象も受けます。
もちろんそれにも、いくつか理由がありました。
大名や将軍家を中心に鷹狩りが行われていた江戸時代には、鷹狩りに使うタカが猛禽の頂点という意識がありました。
強い意思が感じられる、鋭い眼光をもったタカは、好まれて当時の日本画のモチーフにもなりました。
一方のトビですが、生きた獲物にあまり関心をもたず、積極的に捕えようとしません。それが、武士の時代であった江戸時代にはとくに、猛禽らしからぬ情けない姿に見えたことから、猛禽の中でも下位の存在と見なすようになったのも自然な流れだったのでしょう。
だからこそ、世間から低く見られていた家の子が、優れた他者を超える非凡な才能を示すと、とても驚かれました。その際に投げかけられたのが、「鳶が鷹を生んだ」という言葉です。

トビの食事スタイル
トビが世間から低く見られた理由のひとつに、その食生活がありました。
トビが食べているのは、ほとんどが動物の屍骸で、狩りをしたとしても、捕えるのはせいぜい畑にいるネズミや昆虫くらい。大きな動物は狩りません。
ほかの鳥が食べているものを奪うほか、人間が捨てた生ゴミまで食べていました。
大形のタカに匹敵する体をもっているにも関わらず、トビは食べ物をめぐってカラスと争ったり、集団になったカラスに追いかけられることもありました。
そうした日常が、タカの仲間らしくないと思われ、辛辣な評価につながったようです。
孤高が似合う猛禽類であるにもかかわらず“群れる”習性も、トビの評価を下げました。ただし、この点については近年、社会性の高い鳥として再評価されつつあります。

天気予報とトビ
トビの名の由来は「飛び」で、高く飛ぶ(翔ぶ)ところから来ていると考えられています。
本草書の『本朝食鑑』(元禄10年/1697年)には、「天に戻るのかと思うほど高く翔(あまがけ)る」とあります。
著者の人見必大は、「天気晴朗であると、廻舞長鳴し、空にとどき雲に入る」とも語っています。
同書には、「早朝に鳴けば、雨が降り、風が吹く。夕日に鳴くときは、雨が降っても必ず晴れる。俚俗(せけん)ではこれで天気を卜う」と綴られてもいました。
人々がトビが飛ぶ姿を見て翌日の天気を占うのも、ごく自然なことだったようです。「鳶が空に輪を描けば晴天の兆し」ということわざからも、それがわかると思います。
上昇気流を見つけたトビは羽ばたくことなく、すいすいと気流に乗り、上空で輪を描きます。大気の安定度を直感的につかむことも、トビからすればたやすいことでした。
世界で最多の猛禽
そんなトビ。今も昔も、すべての猛禽類の中でもっとも数の多い鳥です。
ヨーロッパ、アジアからアフリカ、オセアニアにかけて分布していて、その総数は500万羽を超えるほど。
トビもまた、ほかのワシ・タカに匹敵する視力をもっていることは、「鳶目兎耳(えんもくとじ)」(トビのようによく見える目をもち、ウサギのようによく聞こえる耳をもつ)という四字熟語からもあきらかです。
ほかの猛禽と同等の大きな眼球をもつことも解剖学的に確認されています。

トビの名は奈良時代に定着し、以後、地方もふくめてトビと呼ばれました。
「トンビ」の呼び名が生まれたのは江戸時代で、のちに上空を舞う姿とからめて童謡にもなりました。
トンビという音の響きやその鳴き声には、ほのぼのとした印象もあり、食べ物を取られるなどの被害を受けたことがなければ、知らず知らずのうちに親近感を感じてしまう人も少なくないようです。
【執筆者】
細川博昭(ほそかわ・ひろあき)
作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュする。おもな著作に、『インコ・オウムの心を知る本』(緑書房)、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥を識る』『人と鳥、交わりの文化誌』『鳥を読む』『人も鳥も好きと嫌いでできている』(春秋社)、『江戸の鳥類図譜』『江戸の植物図譜』(秀和システム)、『知っているようで知らない鳥の話』『江戸時代に描かれた鳥たち』(SBクリエイティブ)、『身近な鳥のすごい辞典』(イースト新書Q)、などがある。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!