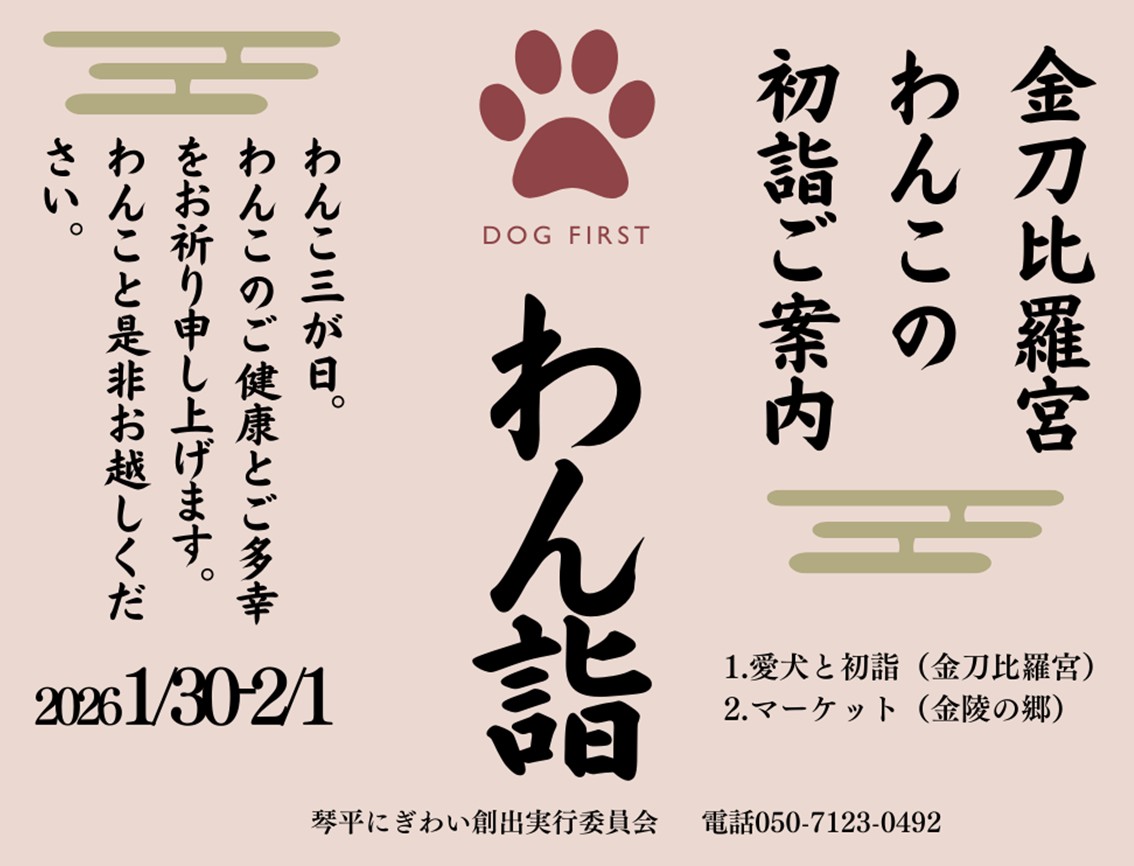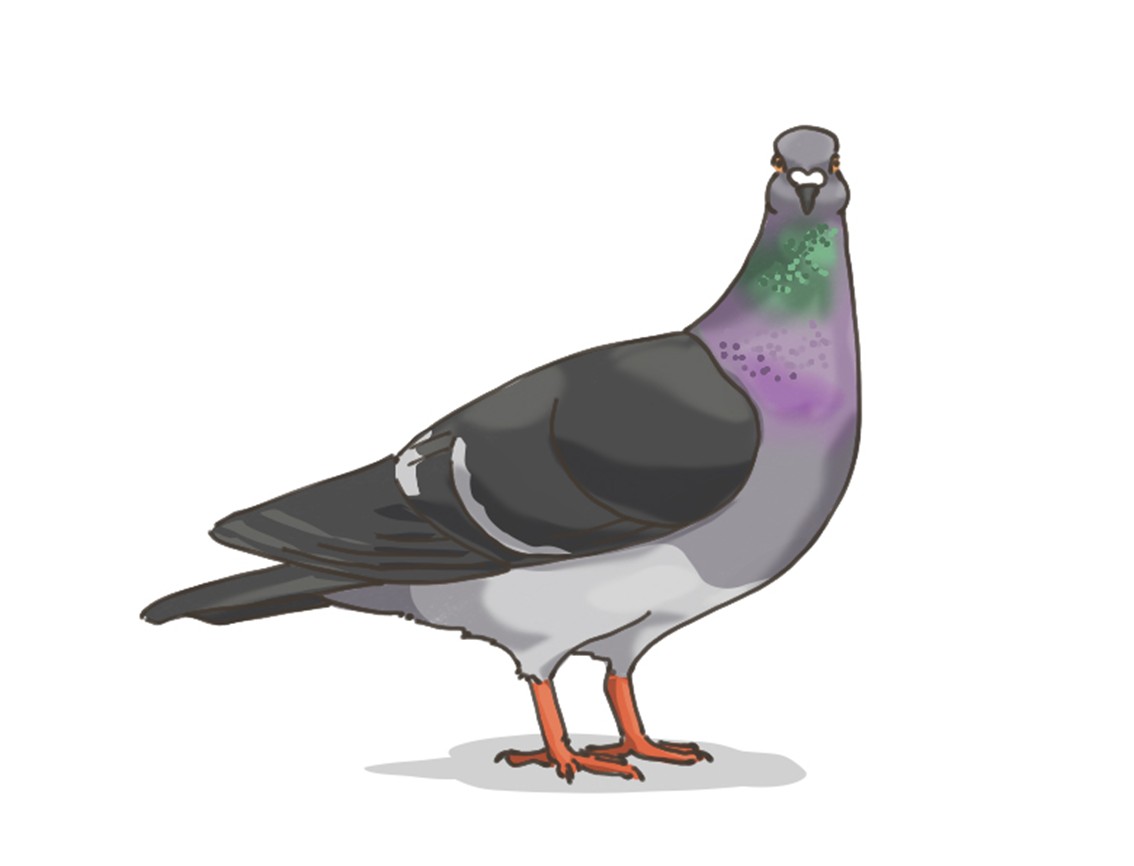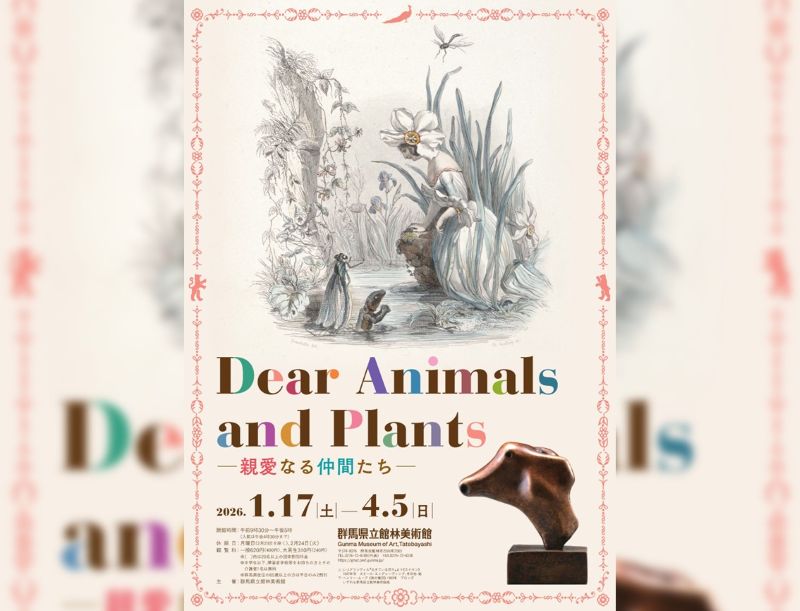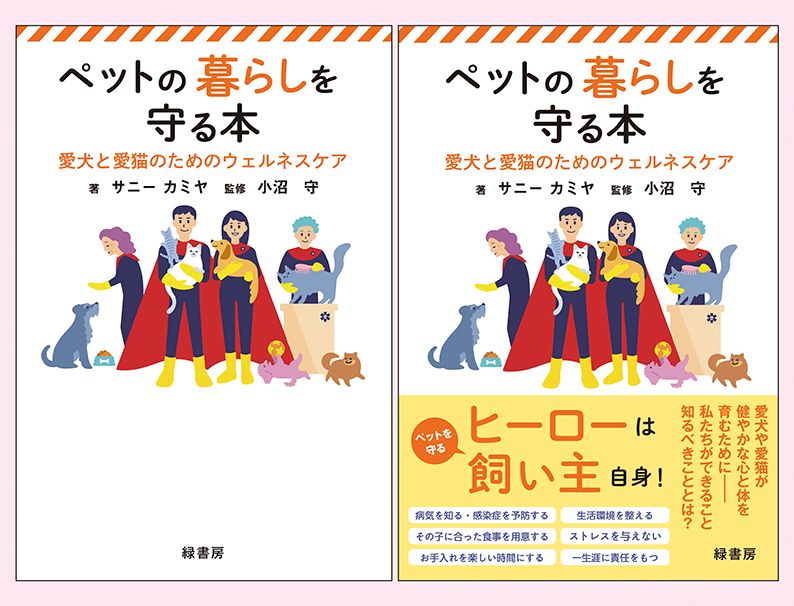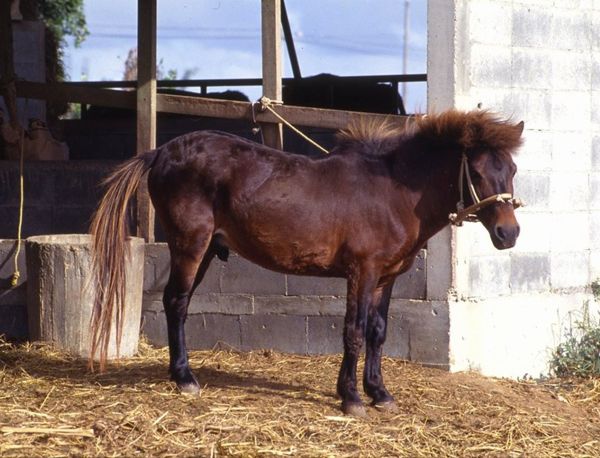秋の草むらを歩いていると、ふと緑の葉の陰に気配を感じることがあります。よく目を凝らすと、そこに身を潜めているのは1匹のカマキリです。まるでこちらを観察するかのように首をかしげたり、時に前脚や翅を広げて威嚇してくる様子すらどこかユーモラスで、単に昆虫というよりは愛玩動物に近い魅力を感じます。

カマキリの特徴
カマキリの最大の特徴は、言うまでもなく前脚が「鎌」のような形をしているところです。この鎌状の脚はただの飾りではなく、捕食のための鋭い武器です。獲物に近づいて射程距離に入った瞬間、電光石火の速さで振り下ろし、逃れる間もなく捕えてしまうのです。カマキリは待ち伏せ型の捕食者であり、草木や花の上でじっと獲物を待ち続ける忍耐力も持っています。
また、特徴的な三角形の頭部は柔軟に向きを変えることができ、獲物となる昆虫の動きや人間の接近などに応じてくるりと首を動かすこともあります。小さな昆虫でありながらこちらを見つめ返してくるような仕草は、観察する者に独特の親近感を抱かせますが、怖がるひともいるかもしれません。
カマキリはその仕草の面白さとは裏腹に、昆虫界屈指の肉食者です。小さなアブラムシから大きなバッタやチョウまで、さまざまな昆虫を捕食していますが、時にはトカゲやカエル、小鳥さえも捕えることがあります。まさに「草むらのハンター」といえるでしょう。

カマキリの種類とすみ分け
現在、世界中で2,000種以上のカマキリが知られています。熱帯のジャングルには葉っぱにそっくりな体をもつカマキリや、ランの花に擬態するカマキリもいて、それらはまるで芸術品のようです。
一方、日本で身近に出会えるのは8種ほどです。その中でも代表的なものを紹介します。
まずは日本最大のオオカマキリ。

大きな個体では体長が10センチメートル近くにもなり、たいへん迫力があります。秋の草むらでは王者のような存在感を放ちます。緑色の個体と褐色の個体がおり、左右の前脚の間の胸は黄色で、後翅は大部分が紫褐色になっています。
似た種類にチョウセンカマキリ(単にカマキリともいう)がおり、外見での判別はやや難しいので、捕まえて確認するとよいでしょう(前脚の鎌で挟まれないよう気をつけてください)。左右の前脚の間の胸はオレンジ色をしていて、後翅はほぼ透明で褐色の斑点がわずかにあるのみです。

また、雑木林など木の多い環境でよく見かけるのがハラビロカマキリです。

体長が4~7センチメートルほどの、樹上性のカマキリです。その名の通り腹部の幅が広く、全体的にずんぐりとした印象を受けます。背面から見ると、翅の中央付近に左右一対の白い斑紋が目立ちます。体は緑色と褐色のタイプがあり、まれに黄色い個体も見つかります。
そしてこちらは、体長4.5~6.5センチメートルほどの、やや小型で細身のコカマキリです。

やや丈の低い草地や林縁など、少し開けた環境で見られます。他の種に比べると、地面に近い位置にいることが多いように感じます。体は褐色のタイプがほとんどですが、まれに緑色の個体もいます。前脚の内側に白と黒のはっきりとした模様があります。
最後はヒナカマキリです。

体長は2センチメートルほどとたいへん小さく、成虫でも翅がほとんど発達していないため、飛ぶことができません。照葉樹林の林床など、落ち葉の多い薄暗い環境で見かけることがほとんどです。晩秋の産卵期には、木の幹や岩に登っている姿を見ることもあります。
このように、カマキリと一口に言っても、種類によって姿やすみかは少しずつ違います。カマキリを探すときはその場所の環境に注目すると、出会える種類が変わります。
オオカマキリのくらし
カマキリの代表として、オオカマキリの1年を追ってみます。
春
暖かな陽射しのもとで、前年に産みつけられた卵のうから小さな幼虫が一斉に孵化します。

体長わずか1センチメートルほどの幼虫は、すでに成虫と同じ形をしており、まるでミニチュアのカマキリです。彼らはアブラムシなどの小さな昆虫を捕食しながら成長し、数回の脱皮を繰り返します。
夏
体の大きな中齢幼虫となり、狩りの対象はバッタやチョウなどに広がり、ますます食欲が旺盛になります。草むらに立ち止まってじっと動かずに獲物を待ち伏せる幼虫の姿は、すでに一人前のハンターの風格を漂わせています。
そして8月のおわりごろ、最後の脱皮(羽化)をして成虫が登場します。
秋
成虫になったオオカマキリは、さらに多くの獲物を捕食し、たっぷりと栄養をとると繁殖の季節を迎えます。オスはメスを探して歩き回り、時には軽い体を生かして飛ぶこともあります。やがてメスを見つけると、後方から恐る恐る近づいていきます。これはうっかり見つかってしまうと、獲物として認識され、交尾する前に食べられてしまうおそれがあるからです。うまく交尾に至った場合でも、メスは交尾の最中にオスを捕食してしまうことがよくありますが、この場合オスの体は動いており、交尾は成立するようです。

冬
やがて、交尾を終えたメスは産卵し、成虫たちはすべて死に絶えて姿を消します。残されるのは、枝や草に産みつけられた卵のうだけです。カマキリは「一年一世代」の昆虫で、次の春に卵から孵る子どもたちが新しい命のバトンを受け取って、またカマキリの1年がはじまります。
卵のうの秘密
カマキリの卵は、ただバラバラに産み落とされるわけではありません。メスは泡のような物質で数十個から数百個もの卵を包み込み、それが固まって「卵のう」となります。この構造は実に巧妙で、外敵や寒さ、乾燥から卵を守ってくれます。種類によって卵のうの形や産み付けられる場所は異なります。

ハリガネムシ
ハリガネムシを知っていますか?
カマキリを観察していると、池や小川に飛び込む姿を見ることがあります。このとき、カマキリのお腹の先から、まるで針金のようないきものが体をくねらせて脱出してきます。これがハリガネムシというカマキリの寄生虫です。
ハリガネムシは水生生物であり、水中で卵を産みます。孵化した幼生は、水生昆虫(カゲロウの幼虫など)に食べられてその体内に潜みます。それらの昆虫が羽化してカマキリに捕食されることで、ハリガネムシはカマキリの体内に移動し、栄養をとって成長します。そしてカマキリが成虫になるころ、こちらも成虫となったハリガネムシは特殊な物質を分泌してカマキリの脳に働きかけ、水辺に向かわせます。そして、カマキリの体が水に触れた途端に、繁殖場所である水中に入ろうとして飛び出してくるのです。

外来種ムネアカハラビロカマキリ
近年、日本のカマキリに新たな種類が加わりました。外来種のムネアカハラビロカマキリです。

名前の通り胸部に赤みがあり、在来のハラビロカマキリよりも一回り大きく、オオカマキリに迫る大きさの個体もいます。東南アジア原産と考えられ、貨物や植物とともに日本へ持ち込まれたと考えられています。2000年代以降、関東や関西を中心に分布を広げ、都市部でも確認されるようになりました。特に、ホームセンターなどで販売されている中国産の「竹ぼうき」に卵嚢がついている例が多く見つかっており、国内への侵入、分布拡大に関わっているのではないかと推察されています。
問題は、その強い繁殖力と捕食能力です。大型で成長が早いため、在来のカマキリと餌を奪い合い、すみかを侵食してしまう恐れがあります。加えて、外見がハラビロカマキリによく似ており、慣れないと見分けるのが難しいことも問題を複雑にしています。
人間の活動によって運ばれた外来カマキリが、生態系にどんな影響を及ぼすのか―。今後もその動向をしっかり注視しなければなりません。
おわりに
首をかしげてこちらを見つめるカマキリの姿に、私は不思議と心を奪われます。
この秋、カマキリに出会ったときにはぜひ少し立ち止まり、そっと見つめてみてください。それぞれが暮らす自然環境の中で懸命に生きている姿や愛らしい仕草を見ていると、彼らのことをもっともっと深く知りたくなってくることでしょう。
【写真・文】
尾園 暁(おぞの・あきら)
昆虫写真家。1976年大阪府生まれ。近畿大学農学部、琉球大学大学院で昆虫学を学んだのち、昆虫写真家に。日本自然科学写真協会(SSP)、日本トンボ学会に所属。著書に『くらべてわかる トンボ』(山と渓谷社)『ぜんぶわかる! トンボ』(ポプラ社)『ハムシハンドブック』(文一総合出版)『ネイチャーガイド 日本のトンボ』(同上・共著)など。
X:@PhotomboOzono
Instagram:@akiraozono_photography
ブログ:湘南むし日記
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!




















.jpg)