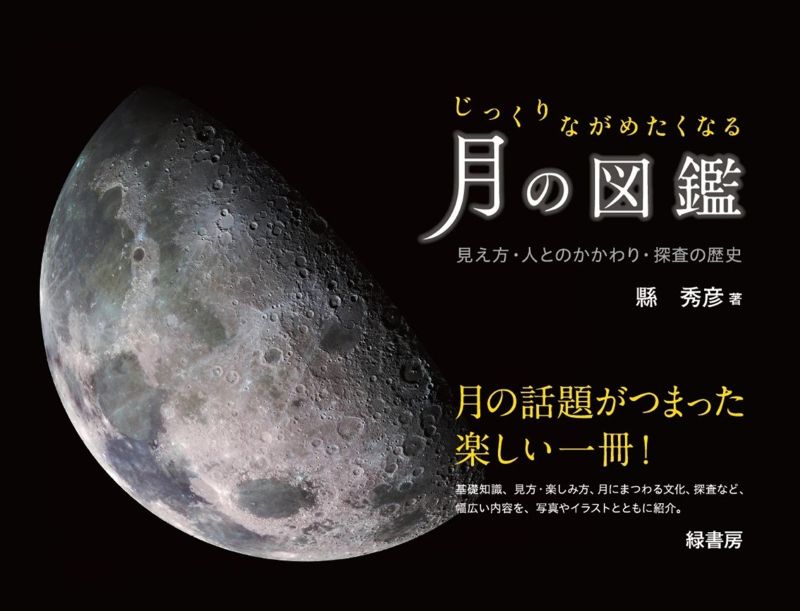はじめに
近年、日本でもペットとして人気を集めている小動物の一種に「ヨツユビハリネズミ」がいます。まんまるな姿やつぶらな瞳、愛らしくて可愛いのにトゲだらけといった存在に魅了される人が増えていますが、正しい知識と環境を整えることが健康で幸せな暮らしにつながります。
今回は、そんなヨツユビハリネズミの基本情報から飼育の注意点、楽しい暮らし方までをご紹介します。
ヨツユビハリネズミはどんな動物?
ヨツユビハリネズミ(Atelerix albiventris)はアフリカ原産の小型哺乳類です。体長は15~25センチメートル、体重は300~500グラムほどで、手のひらに乗せることができるサイズです。

背中~頭部の背側面全域は数千本の針で覆われていますが、お腹や顔、四肢、尻尾には針がなく、やわらかい毛がまばらに生えています。危険を感じると丸くなって、全身の針を立てて身を守ります。なお、この針と体毛に保温性はないため、寒さに非常に弱いです。
ヨツユビハリネズミの頭頂部の真ん中には針のない部分があり、うっすらと逆モヒカンのようになっていることは意外と知られていません。

日中は穴の中や物陰で寝て過ごし、夜間に餌を求めて広範囲を歩き回る夜行性です。
ヨツユビハリネズミは、残念ながら長命の動物ではなく、飼育下での寿命は平均4~5年です。人に馴れると手のひらに乗っても丸まらず、飼い主のにおいを覚えて安心するようになるなど、個性豊かな仕草を見せてくれます。

日本で飼育できるハリネズミはヨツユビハリネズミのみです。他のハリネズミ(ナミハリネズミやマンシュウハリネズミなど)は「特定外来生物」に指定され、飼育・譲渡・輸入が禁止されています。違反すると罰則を受ける可能性があることはもちろんですが、日本の生態系を守るためにも必ず法令を守りましょう。
かかりやすい代表的な病気と予防
ヨツユビハリネズミは体が小さく、夜行性であるため日中はほとんど動きません。人馴れしていないと触れることも難しいため、病気を見逃して一気に体調を崩すことがあります。代表的な病気として次の4つが知られています。
ダニ感染
お迎えしたばかりの子や、一度も動物病院に行ったことがない大人のハリネズミで見かけます。
皮膚にダニがいると、強い痒みや針とフケの脱落が起こります。いつもどこか痒そうに後ろ足で体を掻いている様子が見られたら要注意です。清潔な環境を保つことはもちろんですが、それよりもいち早く動物病院で診てもらってください。
歯周病
歯垢や歯石の付着によって発症し、口臭や食欲低下の原因になります。ふやかした柔らかい餌は歯に汚れがつきやすいため、食べてくれるのであればドライフードも与えるか、食後に歯磨きもしくはミルワームやコオロギなどの昆虫を与えてください。昆虫の外骨格をよく噛むことで予防になります。

子宮疾患
メスでは子宮の病気が多く、血尿や腫瘍がみられることがあります。症状がわかりにくいため、白を基調にした床材を選ぶといち早くおしっこの色の異常に気付くことができます。日頃から体重の変化に気を配り、異常な体重の増加で気付ける場合もあります。
ふらつき症候群
有名な病気ですが、ヨツユビハリネズミの歩き方がおかしければ全てふらつき症候群とは限りません。あらゆる病気で調子が悪くなれば当然ふらつきます。少しでも様子がおかしければ、早めに動物病院を受診しましょう。

事故や怪我について
家庭内で起こる思わぬ事故にも注意が必要です。
第一に温度管理が重要です。ヨツユビハリネズミは20~28度程度の範囲でしか元気に過ごせません。18度以下になると代謝が下がって活動性も低下し、便秘なども生じます。冬眠の能力は持っていないため、更に室温が下がると低体温症に陥り命に関わります。
ケージの外に出すときは、落下事故や脱走に注意してください。ヨツユビハリネズミは地面を歩き回る動物なので、立体的な動きはできません。視力も弱く、高低差の判断もできないため、高いところから落ちると怪我をしてしまいます。
また、目を離している隙に脱走すると、室内でも容易に行方不明になります。冷蔵庫や洗濯機の裏側など、狭い隙間に好んで入り込んで出られなくなることもあるため、必ず目を離さずに安全を確認しましょう。
自分の抜けた針を踏み抜いて足から出血することもあります。掃除はこまめにしてください。
おわりに
ヨツユビハリネズミは正しい知識と環境、そして愛情があれば家庭でも飼育できる魅力的な存在です。ただし、デリケートな面が多く、温度管理や日々の健康観察は欠かせません。日本で飼育できるのはヨツユビハリネズミだけという点を踏まえて、責任をもって迎えることが大切です。彼らの小さな体に秘めた個性や行動・習性を正しく理解し、暮らしのなかで少しずつ信頼を育んでいく過程こそが、私たちの日々に彩りと癒しを与えてくれる大きな喜びとなるでしょう。
「うちにはハリネズミが住んでいる。」なんともわくわくする、素敵な響きに聞こえませんか?

【執筆者】
井本 暁(いもと・あきら)
1983年生まれ。獣医師。井本稲毛動物クリニック(千葉県千葉市)院長。日本大学生物資源科学部獣医学科卒業後、7年間の動物病院勤務を経て、2015年に千葉市に井本稲毛動物クリニックを開院。犬猫以外にも、ハリネズミをはじめとするエキゾチックアニマルの診療を得意としている。著書に『ハリネズミの“日常”と“ホンネ”がわかる本』(監修、日本文芸社出版)。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!