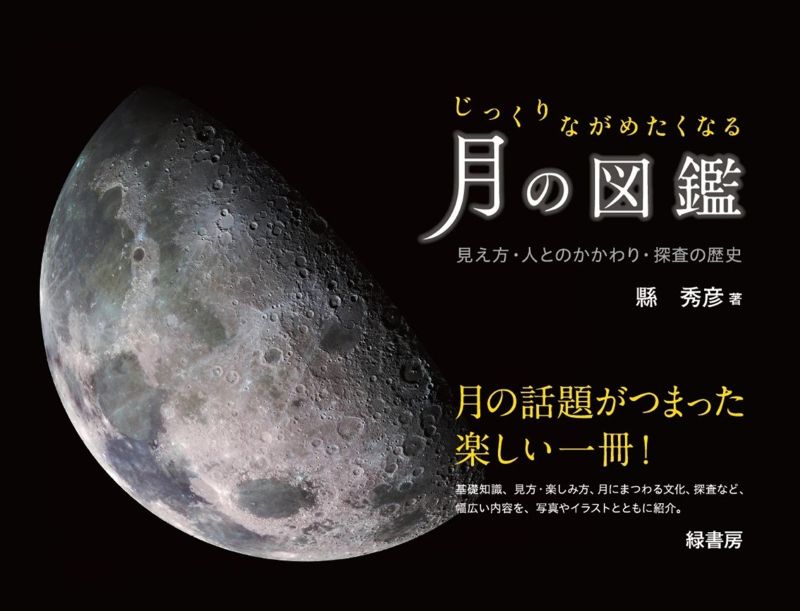チンチラはその愛らしい姿やしぐさから人気が徐々に広がり、飼育する方が増加しています。

また、いろいろな被毛のカラーバリエーションがあり、2匹以上を飼育する方も多くいます。ただ、チンチラと暮らすにあたり、特性や病気を知っておくことが必要です。体調の異常に気付くためには日々の観察が重要ですが、特にどのような状態のときに病院を受診すべきかを述べます。
チンチラを飼育する上での注意点・特性
長寿
ウサギやモルモット、フェレット、ハムスターなどの他の小型哺乳類と比べて長寿であり、20歳近くまで生きる個体もいます。長期間責任をもって飼う覚悟が必要です。
暑さに弱い
チンチラの原産地は、南アメリカ大陸アンデスの涼しい山岳高地地帯です。そのため、寒さには強いですが暑さには弱いです。夏季は1日中冷房が必要になります。暑いと熱中症になります。
しかし、面白いことにほとんどの飼い主が、チンチラは冬季にはこたつの中やヒーターの近くが好きで暖まっていると言います。ヒーターを使用することは構いませんが、ヒーターによる低温やけどや皮膚の乾燥に注意する必要があります。
何でもかじる
チンチラは、犬や猫のように大きな塊状のものを丸飲みすることはありませんが、基本的に何でもかじります。かじったものを食べることもあります。
飼育環境内にある木やプラスチック、電気コードなどをかじることが多く、その破壊力は凄まじいです。飼育ケージはオール金属の物でないと脱走用の穴を開けます。


ケージ内に入れるものはかじってもいいものか、かじれないもの(金属性や厚い陶器性)にする必要があります。
特に、電源コードは注意が必要です。感電して口唇や歯、舌をやけどして食事ができなくなってしまうことがあります。

したがって、室内散歩させるときは注意して見守る必要があります。電源コードはコンセントを抜くか、ケーブルプロテクターなどでブロックしましょう。もちろん、そのケーブルプロテクターもかじりますが……。
狂暴な個体はあまりいませんが、まれに咬みつく個体もいます。
砂浴びが必要
チンチラの美しい被毛を維持するために、専用の砂と砂浴び用の大きめの容器を準備する必要があります。
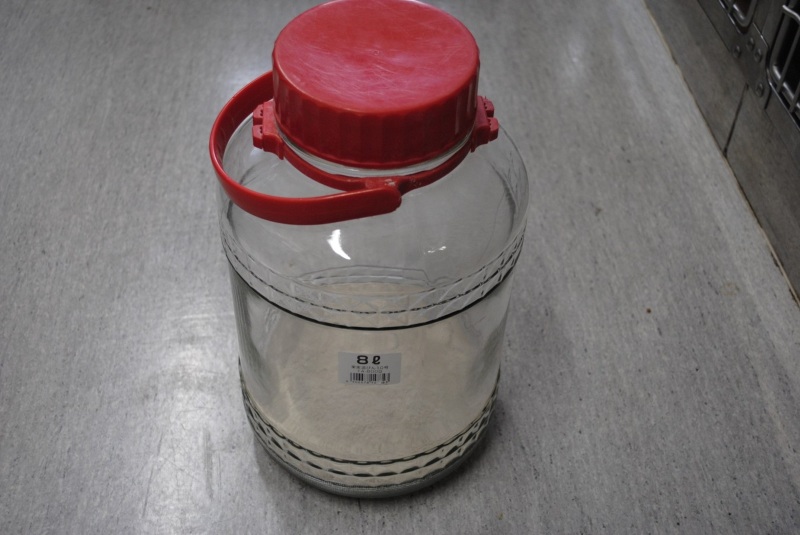
ただし、常時砂浴びさせる必要はありませんし、短時間で構いません。細かい砂が眼に入ったり、吸引してしまったりすることもあるので、ほどほどの時間でいいと思います。砂浴び後に点眼して眼を洗うと、砂による眼のトラブルを予防できます。
強力な跳躍力
飛んだり跳ねたりする能力に長けているので、ケージ内や室内で走ったときに四肢をひっかけないように予防する必要があります。足をひっかけると骨折することがあります。事故が起きないように、ケージ内や室内のレイアウトを考えて事前にブロックします。ケージ内に回し車を設置したほうが望ましいですが、体に合った大きさの製品であることと、金属製であることが望ましいです。夜行性で夜にガンガン回すので、音が響きます。

また、同じケージ内に複数頭いる場合、高速で回される回し車に巻き込まれて事故が起きるので注意が必要です。
室内では狭いところに入って捕獲するのが難しくなることがあります。
捕獲時に抵抗して毛が抜けたり、怪我をしたりすることがあるので、虫取り網があると事故を防げます。

ただし、十分な運動はストレスの発散になりますので、自由に運動できる環境や時間を確保してください。
完全草食性
チンチラは、ウサギと同じく草食性で草類を臼歯ですりつぶし、大きな盲腸内での腸内細菌発酵と食糞によりエネルギーを得ています。基本的に、牧草と良質な専用ドライフードが必要です。生野菜は与える必要がなく、糖分があるドライフルーツやナッツ類などのおやつ類は、歯の病気の原因になるので極力与えないことが望ましいです。
ただ、コミュニケーションをとるためにおやつを与える場合は、内容をよく理解したうえで飼い主の責任のもと与えるようにしてください。
動物病院へ診察に行くとき
チンチラに限りませんが、日々状態を観察して早めに異常に気づくことが重要です。状態に気が付かないと治療の開始が遅れてしまいます。
日々の状態とは、外見上の異常、活動量、食事・飲水量、排便状態、排尿状況、体重の推移です。
普段からこれらを把握しておく必要があります。

眼の異常(流涙症)
涙量(流涙)が多くなると眼の周りの毛が濡れたり、毛が抜けたりします。

涙が多くなる理由に、チンチラが眼を気にしてこすっていることがあげられます。その原因が解決しないと治りません。
チンチラが眼をこする原因として、乾燥やほこり、煙、などの環境中の眼への刺激や角膜などに傷がついていることがあります。
脱毛(真菌感染)
若いチンチラ(お迎えして日が浅い)は真菌に感染することがあり、脱毛やフケなどがしばしばみられます。

真菌感染が認められた場合は、治るまで抗真菌薬を投薬する必要があります。
ただ、ケージなどをしつこくかじっていたりすると鼻先がこすれて脱毛することもあります。
かかとの異常(飛節びらん・足底皮膚炎)
かかとの皮膚が赤くなったり、ただれたり、化膿したりすることがあります。
飼育環境や床材の状況、活動の状況、体重などが発症の原因になっている可能性があるので、それらが改善されないとなかなか治りません。

陰茎の毛からみ(ファーリング・嵌頓包茎)
チンチラの陰茎の表面には多数の細かい突起(トゲトゲ)があり、柔らかくて長いチンチラの毛がからみやすいです。
チンチラが自ら陰茎を包皮から出し入れすることにより、毛が丸まってリング状になり、固く締まると陰茎が腫れて包皮内に戻らなくなったり、最悪尿が出せなくなったりする可能性があります。
予防はチンチラが頻繁に陰茎を気にするようであれば、陰茎を包皮から出して毛がからみついてないか確認し、からみついていたらオイルをつけて取るか、リングをハサミで切って取ります。暴れて難しい場合は病院で取る、あるいは麻酔をかけて取る必要があります。

雌の陰部からの分泌(子宮蓄膿症)
メスの排尿孔と膣孔は体表部まで分かれており、肉眼で確認できます。膣孔は発情期以外は閉じており、発情期は開き少量の分泌液などがみられることもあります。
膣孔から膿が排出される場合は子宮に膿がたまっている状態、すなわち子宮蓄膿症になっている可能性があります。

子宮蓄膿症になっているかは、分泌液の検査(細菌感染の有無)およびX線・エコー検査など(子宮拡大の有無)で子宮の状態を確認して判断します。
治療は手術にて卵巣子宮を摘出することです。
歯のトラブル(不正咬合・過長症)
チンチラの歯はウサギやモルモット、デグー、カピバラなどと同じく、牧草などを細かくすりつぶすために切歯・臼歯ともに一生伸び続ける歯(常生歯)を持っています。

ただ、歯根が不安定になり歯の伸びる方向が異常になり、尖ると頬や舌が傷つき痛がって食べなくなります。

症状は口を盛んに気にする、こする、歯ぎしりする、ずっと口をもぐもぐしている、食べづらそうにする、途中で食べるのをやめる、よだれがでて口の周りや顎、体の被毛が汚れる、毛づくろいをしなくなる、排便量が減る、便が小さくなる、などです。
治療は麻酔をかけて伸びている歯を削って整えます。
一度異常になると定期的な治療が必要になることが多いです。また、治療してもすぐに食べない時には強制的にペーストフードを与える必要があります。

おわりに
美しい被毛を持ち、愛嬌のある見た目で元気に回し車を回しますが、とても繊細な動物です。
チンチラを診察している動物病院は多くありません。事前に診察可能な動物病院を探し、一度診察を受けて話を聞いておくと、安心してチンチラと暮らすことができると思います。
【執筆者】
戸崎和成(とざき・かずしげ)
三重県志摩市出身。1989年北里大学獣医畜産学部獣医学科卒業後、都内の動物病院に勤務し、1995年栃木県宇都宮市にてアンドレ動物病院を開院。現在、日本獣医エキゾチック動物学会副会長を務めている。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!