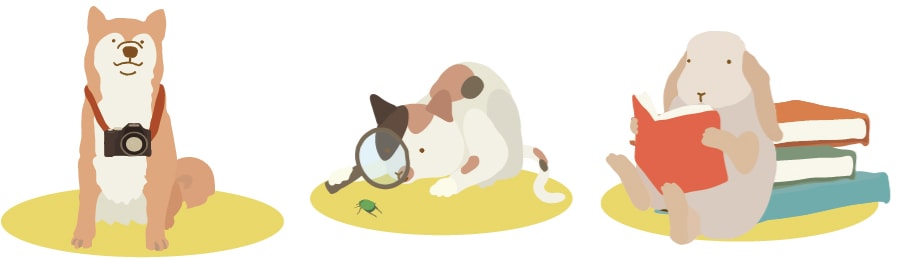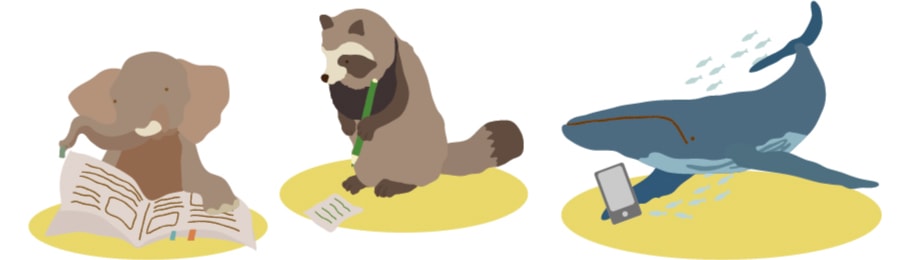横浜といえば「異国情緒」や「港町」のイメージで語られることが多いが、私の住む横浜には「異国情緒」のかけらもなく、「港町」というよりは周辺には田んぼが広がり、里山のような自然がひらけている。市民の森と呼ばれる緑化保全区域があり、オオタカの営巣地がある。近くの川にはコサギもカモもカワセミも来る。
そして春ともなると、うちの小さな庭にもたらされるメジロやヒヨドリ、可愛い目をした野ネズミに、トカゲ、シマヘビ、アブラコウモリやヒミズの面々。サッカーボールほどの蜂の巣が転がしてあったときには、レインコートをぴっちり着込み手袋と長靴で武装して恐る恐る近づいた。すでに空き家だった。
猫のユキが若かった頃、うちのまわりの小動物たちにとって、春は戦々恐々、受難の季節だったにちがいない。

ハンター・ユキと動物たちの受難
.jpg)
桜が咲き日足が伸びるとともに、8キロ超の大白猫(♂)が俄然、ハンターとして覚醒する。冬じゅう、コタツで惰眠を貪っていたくせに、人の足元をすり抜け飛び出して、呼べど叫べど、帰って来やしない。ハンター・ユキがとりわけ得意としていたのが手のひらで包めるほどのアブラコウモリで、これはもう日が暮れるまで帰らない。やがて暗い庭で、ぐるるる、と奇妙にくぐもった声がすれば、獲物を携えての帰還の合図。――いや、合図すれば直ちに獲物を取り上げられ叱られて、ユキにしてみれば良いことなど一つもなかったわけだから、それはただ、どうしたって「とったど!」と叫ばずにいられなかっただけなのかもしれない。

。.jpg)
このとき息のあるコウモリは、古布の切れ端でくるみ紙箱に入れて、お湯入りペットボトルで保温する。うちの猫がスミマセン、と謝りながら、爪楊枝の先を丸く削って水や牛乳を飲ませる。悪いのは猫を養ってる私です、スミマセン、と謝りながら、バナナを練り、解凍した合い挽き肉を小さな口に少しずつ押し込む。スミマセンスミマセンと謝りつつ、コウモリがバナナ色のフンをしたり、繻子の手袋みたいな翼をたたみ紙箱のふちに逆さにぶらさがったりするようになると、しみじみ嬉しい。
こうして夜を過ごしたコウモリを、朝一番でよこはま動物園ズーラシアに連れていく。そこにはケガをした野生動物を診てくれる獣医さんがいる。コウモリを丁寧に調べてから「このひとにはこちらで休んでもらって」と言うその人に、私はまた、ペコペコ頭を下げる。
帰りは一人で動物園を歩く。平日の朝の動物園には私のほか人っ子一人おらず、しんとしている。ときどき誰かが吠えたり鳴いたりするのだけど、不思議に静寂を妨げない。「種の保存」を担う動物園では、IUCN(国際自然保護連合)に準じた絶滅危惧度がわかりやすく掲げてあり、ネコ科のインドライオンもツシマヤマネコも、チンパンジーも、キュートなフンボルトペンギンも、絶滅危惧種なのだと知る。うららかな陽光の下、緑滴る動物園は美しい。それぞれの毛皮は健やかに輝いて、動物たちはなお毛繕いに余念がない。穏やかな時間の流れるそのなかを、私はいつしか気がつくと、スミマセンスミマセンと謝りながら、歩いているのだった。
コロナ禍以前、コウモリが感染症を媒介するのではないかと広く知られる前の話だ。
カナヘビの奇跡
またある年の春、ユキがトカゲをくわえてきたときのこと――。
いつものように意気揚々と帰ってきたユキが、この日はどうした風の吹き回しか、縁側からまっすぐ部屋のなかに入ってきた。そして「さあ、見て見て!」と言わんばかりに、獲物をぽとりと床の上に落とした。
細っこくてしっぽの長いカナヘビだ。
「あっ!」と、思わず、声をあげる私。
「あっ!」と、声をあげるかわりに、カナヘビは天分のすばやさで横に飛んだ。
それを咄嗟に掴んだら、なんとしっぽがチョン切れて、カナヘビ本人というか本体はソファの下へ。あっというまのことだった。
これには困った。うちには9匹(当時)も猫がいるのだ。カナヘビを棲み処へ帰してやりたいと思うものの、キャツらに見つかったら終わりだ。猫より先にカナヘビを見つけるのが私たち人間の家族の至上命題となったがしかし、当のカナヘビの行方は知れず。
そのうち、あれはもう、うちにはいないんじゃないの? てな気分が濃くなってくる。どこか隙間から外に出たんじゃない? そう、するっと、猫の寝てる間に。みんな寝てる間に。と、いうふうに。どこかで干からびて死んでいるとは考えたくなかった。
そうして8日目の午後だった。
ひょっこりとカナヘビが現れたのだ。
うちのなかで。娘の前に。ちょっとこう、半身に構えて。のばしたしっぽの先は見覚えのあるかたちにチョン切れていた。
このとき娘は、ソファを背に膝を抱えてメソメソしていた。病を得て休職中のところ、母親――私だ――と口喧嘩をしたからだ。喧嘩の原因はたぶん些細なことだったが、冷えた床に体育座りをするほどにはしょげていた。
そこへカナヘビだ。
傷心は一気にふっ飛ぶ。
涙目の娘が首尾よくカナヘビを捕まえられたのは、奇跡といっていい。
実際、「奇跡だ」「奇跡だね」と、私たちは手を取り合って喜び、その棲み処と思しき畑でカナヘビを放した。すでに夕方近く、ひらりと細身を翻した背中をその一瞬、夕日が金色に照らす。はっとしたときにはもう、カナヘビは草叢に消えていた。

命拾いしたカナヘビが「奇跡だ」と思ったかどうかはわからないが、そもそも、殺戮者(猫)の魔手(爪)をすんでのところで逃れたからといって、猫を養う私たちが奇跡などと言うのはおこがましい。私たちは多くの種を大規模な絶滅に追いやっている当事者でもあるのだ。
それでも、コウモリのたたまれた翼や金色に光っていたカナヘビの背中をふと思い出すとき、期せずして、人知の及ばぬ領域、に触れたと思う。
人知の及ばぬ領域。
私たちもまた、日々、薄氷を踏んで生きている。
【執筆】
岡田貴久子(おかだ・きくこ)
1954年生まれ。同志社大学英文学科卒業。『ブンさんの海』で毎日童話新人賞優秀賞を受賞。『うみうります』と改題し、白泉社より刊行。作品に『ベビーシッターはアヒル!?』(ポプラ社)『怪盗クロネコ団』シリーズ、『宇宙スパイウサギ大作戦』シリーズ(以上理論社)『バーバー・ルーナのお客さま』シリーズ(偕成社)など多数。『飛ぶ教室』(光村図書出版)でヤングアダルト書評を隔号で担当。神奈川県在住。
-

猫と暮らし、文を書く【第12回】猫の流儀
-

猫と暮らし、文を書く【第11回】天上天下唯我独尊、猫
-

猫と暮らし、文を書く【第10回】初めてのこと
-

猫と暮らし、文を書く【第9回】安心な寝床とごはん、愛がある場所
-

猫と暮らし、文を書く【第8回】あれが好き、これは嫌い
-

猫と暮らし、文を書く【第7回】はじめて一緒に暮らした猫
-

猫と暮らし、文を書く【第6回】生きているヨロコビ
-

猫と暮らし、文を書く【第5回】ハナちゃんからの贈り物
-

猫と暮らし、文を書く【第4回】帰る場所である幸福
-

猫と暮らし、文を書く【第3回】「良い手」であるために
-

猫と暮らし、文を書く【第2回】人知の及ばぬ領域
-

猫と暮らし、文を書く【第1回】名に込められた願い