腸活は「腸内細菌叢を元気にすること」です。腸内細菌叢を元気にすると、下痢や便秘などの消化器疾患、その他の疾患、肥満や精神の改善作用が期待できることから、近年多くの商品がつくられています。
腸内細菌叢とは?
腸内細菌叢は、マイクロバイオームや腸内フローラなどとも呼ばれます。細菌、真菌、古細菌、原生生物、ウイルスなどの複雑な微生物群から構成されています。
ヒトの腸内には、約1,000種類、総計100兆個以上の細菌が生息しています。ヒトの身体を構成するすべての細胞(30兆個)の約3倍の数の細菌が生息しているのです。犬や猫は、ヒトと同数以上の細菌を保有していると考えられています。
腸内細菌叢は、腸内病原体に対する防御、栄養素の供給や消化・吸収の促進、腸内のバリア機能の改善、腸の発育促進、免疫系の調節などの多面的なメカニズムを介して、腸内および宿主のホメオスタシス(恒常性)の維持に寄与しています。ホメオスタシスのバランスが崩れると、下痢や便秘になったり、免疫抑制で感染症、がん、アレルギーなどになります。身体の免疫細胞の過半数が腸にあるので、腸活しない理由はありません。
腸内細菌叢を元気にする仲介役
腸内細菌叢を元気にする仲介役には、短鎖脂肪酸、二次胆汁酸、トリプトファン代謝産物などの細菌代謝産物があります。これらは宿主~微生物叢相互作用で重要な役割をもちます。
特に、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸が重要です。腸活は、菌を増やすことではなく、「その菌から産生される短鎖脂肪酸をいかに産生させるか」が重要なのです。
短鎖脂肪酸(有機酸;SCFA)
短鎖脂肪酸とは、酢酸(塩)、プロピオン酸(塩)、酪酸(塩)を含む食物繊維の細菌発酵産物です。大腸の細胞のエネルギー基質、消化管粘膜上皮バリアの維持、エネルギー代謝の調節、抗炎症作用などで腸および宿主の健康に寄与しています。
腸内では、短鎖脂肪酸がリレー方式で酪酸を産生しています。乳酸*は、このリレーをスタートさせるという重要な役割があり、腸内環境(pH調整)の改善にも関与します。短鎖脂肪酸のプロピオン酸は、肝臓と筋肉のエネルギー産生を担っています。酢酸は、最も重要な酪酸産生に関係しています。
*乳酸は広義の意味では短鎖脂肪酸に含まれることもありますが、狭義の意味では含まれません。
では「乳酸菌には意味がないのか」と考えてしまいがちですが、そうではありません。ラクトバチルス属やビフィドバクテリウム属の乳酸菌は、それ自体では酪酸を産生しませんが、他の常在菌を交差摂食することで酪酸産生を促すこともあります。
短鎖脂肪酸の産生を促進する作用
短鎖脂肪酸の産生を促す作用には、次のようなものがあります。
・腸内環境の安定化(腸管内を弱酸性の環境に改善)
・腸内のバリア機能の改善(腸内粘液の増加)
・免疫バランスの調整(制御性T細胞などの免疫系細胞の免疫応答の調整)
・便秘改善(大腸の螺動運動の改善に役立ち排便環境を整える)
このように、腸活において短鎖脂肪酸は重要な栄養素です。中でも酪酸は、犬や猫でも繊維質またはタンパク質から生成できる、食事中の腸内細菌叢の主要影響因子ともいわれています。
プロバイオティクスとは?
腸活について学んだところで、腸活に効果があるとされる「プロバイオティクス」について解説します。
国際プロバイオティクス・プレバイオティクス科学協会(International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics:ISAPP)によるプロバイオティクスの定義は、「適切な量を投与することで、腸内細菌叢のバランスを改善し、宿主の健康に有益な効果をもたらす、生きた微生物」です。ほかにも、次のことが条件とされています。
・安全性が保証されている
・宿主(対象生物)の腸内細菌叢の一種が望ましい
・胃液や胆汁などに耐えて、生きたまま腸(大腸)に到達できる
・下部消化管(大腸)で増殖できる
・宿主に対して明らかな有用効果を発揮する(有効性が証明されている)
・食品として、有効な菌数が維持できる
抗生物質の代わりとして有望視?
牛や豚、鶏などの家畜では、感染症対策の抗生物質が課題となっています。抗生物質を使うと、出荷が遅れたり出荷できなくなったりするだけでなく、ヒトが食べることでヒトの耐性菌をつくってしまうなど、多くの課題があるのです。
近年では、プロバイオティクスが感染症対策に使える可能性を示す報告が多くあります。消化・吸収する栄養の増加、腸の形態学的な改善、腸内細菌叢の最適化、炎症の抑制など、多くの有効性が確認されています。このためプロバイオティクスは、畜産において抗生物質の代わりとして有望視されています。
実は、犬の消化器疾患の診断をする際の、国際的なガイドラインでも、以前は入っていた抗生物質がプロバイオティクスに変えられています。犬や猫においてもプロバイオティクスが重要になっていくと思われます。
TOPICS:犬や猫で有効性を示しているプロバイオティクスの一部紹介
代表的なプロバイオティクスは、 乳酸を産生する乳酸菌や酢酸を産生するビフィズス菌などです。一般に乳酸菌やビフィズス菌は腸管以外では発酵食品(ヨーグルト、 チーズ、醤油、味噌、漬物、キムチなど)に生息しています。
ヒトにおけるプロバイオティクスは、IBD、抗生物質関連下痢、大腸がん、アレルギー、2型糖尿病、アトピー性皮膚炎などさまざまな疾患において予防や治療で良い結果が報告されています。犬や猫でも、慢性腸症、炎症性腸疾患、急性(出血性)下痢症などでプロバイオティクスの有効性が確認されています。作用のしくみは、腸内細菌叢のバランスが改善し、炎症が緩和され、免疫機能が向上し、腸内病原体またはバランスの改善から保護されていくと考えられています。
ヒト由来のプロバイオティクスでは、ラクトバチルス属、ビフィドバクテリウム属、サッカロミセス属の菌株が安全かつ効果的に使用されてきた長い歴史があります。今後期待されるものには、ローズブリア属、アッカーマンシア属、プロピオニバクテリウム属、フェカリバクテリウム属があります。特に乳酸菌のストレプトコッカス属やラクトバチルスラス属の一部株は、それぞれ乳糖消化と胆汁酸代謝を促進し、抗菌分子の産生を介して、病原体のコロニー形成を阻害することが知られています。
犬や猫では、ビフィズス菌(Bifidobacterium infantis、B. breve、B. longum、およびB. bifidum)、酵母菌(Saccharomyces boulardiiおよびS. cerevisiae)が、プロバイオティクスとして長く使用されており、安全性と有効性が検証されています。ヒトと同様、酪酸菌(Faecalibacterium prausnitziiなど)も期待されています。
プレバイオティクス・シンバイオティクス・ポストバイオティクス
プロバイオティクスと似た名称の、「プレバイオティクス」「シンバイオティクス」「ポストバイオティクス」について、それぞれ解説します。
プレバイオティクス
プレバイオティクスは、元来存在している有用菌を埋殖させるための栄養素です。食物繊維、グルカン、フルクタン(イヌリン)、マンノース、グルコース、キシロース、ペクチン、デンプン、ヒトミルク、ポリフェノールのオリゴマーなどで、犬や猫での有効例が報告されています。
プレバイオティクスの代表例である食物繊維は、不溶性と可(水)溶性に分類され、特に可(水)溶性食物繊維が注目されています。
■不溶性食物繊維
具体的な食品は、キチン(エビやカニの殻)、 セルロース(野菜、穀物、フスマ)、 ヘミセルロース(豆類、フスマ)、 不溶性ペクチン(未熟果物、野菜)、リグニン(ココア、フスマ、豆類)などです。
■可(水)溶性食物繊維
具体的な食品は、アルギニン(昆布、ワカメ)、イヌリン*(ゴボウ)、 大麦β⁻グルカン(大麦)、グアーガム(グアー豆、豆類)、グルコマンナン(コンニャク、山芋、犬や猫でも便秘改善作用もあり)、水様性ペクチン(未熟果物、野菜)、 難消化性デキストリン(トウモロコシ原料の加工品)、 フコダイン(毘布、ワカメ、モズク)、ポリデキストロース(トウモロコシ原料の加工品)などです。
*ニンニクや玉ねぎにも入っていますが、犬や猫には禁忌です。
犬や猫でのプレバイオティクスには、βグルカン、イヌリン、乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、イヌリンなどが良く使われています。特に食物繊維のサイリウムや、フラクトオリゴ糖のフルクトースなどで、多くの有効例の報告があります。
シンバイオティクスとは?
プロバイオティクスとプレバイオティクスは、異なった作用機序により腸内細菌叢を改善します。近年では、両者を組み合わせることでシナジーを期待する「シンバイオティクス」(Synergyのシン)が誕生しました。具体的には、乳酸菌(プロバイオティクス)とフルクトオリゴ糖(フルクトースやイヌリンなどのプレバイオティクス)の組み合わせが多いです。
ヒトの食材で例えると、ヨーグルト(乳酸菌またはビフィズス菌)とバナナ(オリコ糖)、ワカメやナメコ(食物繊維)入りの味噌汁(麹菌というプロバイオティクス)、キムチ(乳酸菌と白菜などの食物繊維)や納豆(大豆と納豆菌、醤油)をそれぞれあわせて食べることと似ているかもしれません。
ポストバイオティクス
死菌や、菌体物質などの菌の成分がプロバイオティクスと同様の効果のある、「ポストバイオティクス*」というものもあります。
*国際プロバイオティクス・プレバイオティクス科学協会は、ポストバイオティクスには、無生物の微生物とその構成要素(細胞壁成分、繊毛、その他の構造体など)、さらに生理活性物質も含むとしています。しかし近年は、無傷または壊れて不活性化された微生物細胞を「パラバイオティクス」と呼ぶなど、定義も統一されていません。
プロバイオティクスの課題
プロバイオティクスの種類によっては「効果がない」という研究報告もあります。「ある乳酸菌を投与しても犬や猫の腸内細菌叢や免疫学的パラメータに影響を及ぼさなかった」というものです。なので、最低限の有効性が示された菌を使うべきでしょう。
その他、いくつかの課題を紹介します。
プロバイオティクスに使う菌は1つだけでいいの?
腸内細菌叢の解析技術の進歩により、犬や猫でおおむね類似していることや、多様性は猫が高いことがわかりました。種類は、ファーミキューテス属、プロテオバクテリア属、バクテロイデーテス属、フソバクテリア属、およびアクチノバクテリア属(放線菌)が主ですが、ヒトと同じように効果のある菌が個体によって違います。
また、複数の乳酸菌とビフィズス菌では抗菌ペプチドなどの産生を刺激するなど免疫調整作用が高いことが多く報告されています。その数は4種から、多いもので7種のものもあります。1つの菌でも有効なプロバイオティクスはありますが、やはり腸内細菌叢には多様性があるため、多くの菌を使用する方がいいのかもしれません。
ヒトの微生物叢と犬や猫の微生物叢には違う?
ヒトの微生物叢は、犬や猫とは違うといわれています。
安全性と有効性は未確認ですが、犬や猫から同定された菌として、乳酸菌ではLactobacillus reuteri、L. fermentum、Enterococcus faecium、Pediococcus pentosaceus、Ligilactobacillus animalis(旧: Lactobacillus animalis)、Limosilactobacillus fermentum、L. rhamnosus、L. plantarumが知られています。ネコではEnterococcus hirae 、Bacteroides sp. CACC 737などが分離されています。また、Lactobacillus fermentum 、Lactobacillus acidophilus、Enterococcus faecalisなどは、犬で安全性が報告されています。
ヒトでは、プロバイオティクスの特性は宿主特異性があると報告されています。よって前述したプロバイオティクスの条件「宿主(対象生物)の腸内細菌叢の一種が望ましい」に鑑み、犬や猫に与える用途であれば、安全性の面でもプロバイオティクスの菌は犬や猫由来または犬や猫の腸内細菌叢にある菌を使う方がベストなのかもしれません。
しかし、有効性が示されていれば、犬や猫由来であることにこだわる必要はないかもしれません。近年では、腸内細菌ではない土壌菌や、食品由来の乳酸菌の有効性も多く報告されています。例えば、キムチから分離した乳酸菌(Weissella cibaria)では、脂質代謝の改善、糞便中の乳酸菌数の増加、アンモニア排出量の減少が証明されています(ただし、キムチは刺激性が強いため、犬に与えてはいけません)。ほかに、枯草菌(Bacillus subtilis)や苔癬菌(Bacillus licheniformis)、納豆菌など多くの報告があります。ネコでも、食品中の土壌菌Bacillus licheniformisなどで有効な報告があります。
また、サプリメントでよく使われるビール酵母などと同じ酵母類のサッカロマイセス・セレビシエ酵は、アンモニアなどの便臭化合物の濃度が低くなることで便臭改善効果があったり、酪酸濃度やいわゆる善玉菌(Bifidobacteriumなど)が多くなり、悪玉菌(E. coliなど)が少なくなるなどの腸内細菌調整作用の報告もあります。
胃酸でだめにならない?
前述したプロバイオティクスの条件に「胃液や胆汁などに耐えて生きたまま腸(大腸)に到達できること」「下部消化管(大腸)で増殖が可能である」とありました。しかし、ヒトでも「胃酸で菌が死んでしまうので、意味がないのでは?」と疑問視されているうえ、犬や猫はヒトより強い胃酸をもちますので、多くが死んでしまったり、生着せず排出されるようです*。
*腸内で死んでも有用菌増殖作用があったり、生きたまま便に排出されていることを証明した報告もあります。
しかし、犬の胃酸および腸内でプロバイオティクス菌が生存していることが確認されたという研究報告や、マイクロカプセル化により猫の消化管通過中の生存率を維持させた報告があります。これらのことから、生きて腸まで届けられると証明されている菌を使うべきでしょう。
しかしながら最近では、安全性と有効例が証明されていれば、生きた菌にこだわらなくなってきています。増殖しないオリゴ糖、菌体物質、死菌などでも「宿主に対して明らかな有用効果を発揮すること」が証明されていたり、細胞壁などの菌体物質が腸内細菌叢に良い影響を与えることも確認されていたりするからです。この死菌や菌体物質のことを「ポストバイオティクス」といいます。
それでは最後に、がん・腎臓・皮膚と腸活について解説します。
がん・腎臓・皮膚と腸活
がんと腸活
腫瘍には、良性腫瘍と悪性腫瘍があります。悪性腫瘍のなかの「●●癌」「●●肉腫」を、ひらがなまたはカタカナで「がん」「ガン」といいます。良性腫瘍も悪性腫瘍もサプリメントで予防するなら同じ方向なので、この記事では腫瘍全体を指して解説します。また、がんには多くの種類がありますが、わかりやすく塊のがんについて説明します。
がんの腫瘍細胞は、その腫瘍細胞を支える血管をつくる細胞などと構成されています。つまり、腫瘍細胞だけでなく、これらの細胞も増えないようにしなくてはなりません。
がんのサプリメントには、免疫の賦活作用、調整作用、抗酸化作用により、腫瘍細胞や血管をつくる細胞の抑制や、抗がん剤などの副作用の軽減を期待したものが多くあります。
犬や猫で用いられている主なサプリメントについて、腸活以外のものも含めて紹介します。
■n-3脂肪酸
そもそも、がんの発生には炎症が関与していることが知られています。例えば「胃の炎症(胃炎、胃潰瘍)を繰り返しているうちに胃がんになった」「皮膚に炎症を伴うダメージ(紫外線暴露)を長期にうけたから皮膚がんになった」などです。つまり、がんを予防するためには、日常的に炎症を緩和させる必要があります。DHAやEPAなどのオメガ-3脂肪酸が抗炎症作用をもつことは過去の記事でも紹介してきました。これらの投与は、がんの犬を放射線治療するときの副反応(主に炎症)を軽減させるという報告もあります。
■β-グルカン
β-グルカンは、細菌や真菌酵母、藻類、大麦のような植物の細胞壁に含まれる糖です。キノコや酵母などが由来であることが多いです。犬のワクチンに有効な免疫応答などの免疫賦活作用や、舞茸から抽出したβグルカンによる免疫細胞の調整効果や賦活効果、抗がん薬の副作用を軽減する効果などが認められています。また、α-グルカンでも同様の効果が認められています。
サプリメントには、キノコ由来のAHCC®、アガリクス、メシマコブ、ハナビラダケなどがあります。
■サメ軟骨
サメ軟骨は、がん免疫を促進するホルモンであるインターフェロンγを増やす作用や、腫瘍へ栄養を送る血管を作る細胞の抑制により腫瘍細胞の増殖を抑制する効果が知られています。多くのサプリメントがあり、他の軟骨や大豆由来で類似作用のある製品もあります。
■抗酸化サプリメント
ビタミンC、ビタミンEが有名です。それ以外に、カロテノイドであるカロテン類(β-カロテンやリコピンなど)があります。キサントフィル類(ルテイン、アスタキサンチン)、コエンザイムQ10、ポリフェノール(ライチなど)などの抗酸化作用による抗がん作用も期待されています。
腎臓病と腸活
プロバイオティクス・プレバイオティクス・シンバイオティクス・ポストバイオティクスの作用は、腎臓病にかかわりがあります。尿毒素の産生には腸内細菌叢がかかわっており、乳酸菌などの善玉菌は窒素物を利用して消化管内の窒素物が低減するからです。
プロバイオティクスには、ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・プランタラム、ペティオコッカス・アシディラクティシ、エンテロコッカス・フェシウム、ペディオコッカス 5051株乳酸菌などの乳酸菌、ビフィズス菌があります。
プレバイオティクスには、乳酸菌などの善玉菌の栄養となるマンナンオリゴ糖、ビートオリゴ糖、環状オリゴ糖、フレクトオリゴ糖などのオリゴ糖や、マルトース、大豆(発酵)成分などがあります。
ポストバイオティクスには、死菌や乳酸菌発酵原液エキスなどがあります。
犬アトピー性皮膚炎と腸活
犬アトピー性皮膚炎とは、痒みを伴う湿疹が慢性的に発症する、搔痒性の皮膚病です。痒み・炎症・脱毛・外耳炎など症状は多岐にわたります。遺伝的素因により皮膚のバリア機能が低下することでアレルゲンが侵入し、それに対してIgEが異常産生されて自身の細胞を攻撃することで、炎症が生じます。
犬アトピー性皮膚炎の発症部位では、Th2細胞の活性と、Th2細胞が分泌するIL-4の過剰産生が確認されています。さらにTh2 細胞が分泌するIL-31が犬アトピー性皮膚炎CADの症状である痒みを発現させているとされています。
犬においては、Bifidobacterium属やLactobacillus属の細菌を投与することで腸内細菌叢が調整され、症状が改善したという報告があります。
アレルギーのヒトでは、Bifidobacterium属やLactobacillus属が低下しており、ケストースという三糖のオリゴ糖がLactobacillus属およびBifidobacterium属において最も多様な種を増殖させるという報告や、乳幼児においてケストースを摂取することで酪酸が増加してアトピー性皮膚炎の症状が改善した報告があります。また、ケストースを主成分としたフラクトオリゴ糖混合物をアトピー性皮膚炎モデルマウスに与えたところ、Th2細胞由来の免疫応答が抑制されたという報告や、健康なビーグルにケストースを経口摂取させたところ、Bifidobacterium属が増加し、Fusobacterium属 およびClostridium perfringensは減少していたという報告があります。よって犬においても、Bifidobacterium属やLactobacillus属のプロバイオティクスやケストースが、犬アトピー性皮膚炎に効果のある可能性があります。
【執筆者】
小沼 守(おぬま・まもる)
獣医師、博士(獣医学)。千葉科学大学特担教授、大相模動物クリニック名誉院長。日本サプリメント協会ペット栄養部会長、日本ペット栄養学会動物用サプリメント研究推進委員会委員、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会編集委員、日本機能性香料医学会理事・編集委員他。20年以上にわたりペットサプリメントを含む機能性食品の研究と開発に携わっている。
[参考文献]
・小沼守. 免疫とサプリメント. ペット栄養学会誌. 2023. 26(2):104-109.
・Hosseini SH, Farhangfar A, Moradi M, et al. Beyond probiotics: Exploring the potential of postbiotics and parabiotics in veterinary medicine. Res Vet Sci. 2024 Feb;167:105133.
・Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74.
・Paris S, Chapat L, Pasin M, et al. β-Glucan-Induced Trained Immunity in Dogs. Front Immunol. 2020 Oct 9;11:566893.
・Ferreira LG, Endrighi M, Lisenko KG, et al. Oat beta-glucan as a dietary supplement for dogs. PLoS One. 2018 Jul 31;13(7):e0201133.
・Konno S. Synergistic potentiation of D-fraction with vitamin C as possible alternative approach for cancer therapy. Int J Gen Med. 2009 Jul 30;2:91-108.
・Hansen RA, Anderson C, Fettman MJ, et al. Menhaden oil administration to dogs treated with radiation for nasal tumors demonstrates lower levels of tissue eicosanoids. Nutr Res. 2011 Dec;31(12):929-36.
・左向敏紀. 第4章4-5 腫瘍(がん). ペットサプリメント活用ガイド. 松本浩毅監. 一般社団法人日本ペット栄養学会編. 2023, p.88-89.
-

ペット用サプリメントのトリセツ【第9回】腸活のすすめ
-

ペット用サプリメントのトリセツ【第8回】皮膚病と闘う備え~皮膚バリアの強化と免疫調整~
-

ペット用サプリメントのトリセツ【第7回】慢性腎臓病との付き合い方
-

ペット用サプリメントのトリセツ【第6回】サプリメントを与える際の工夫
-
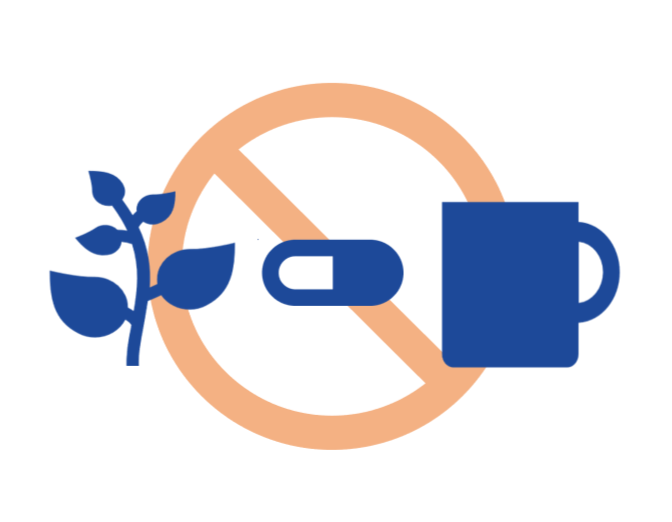
ペット用サプリメントのトリセツ【第5回】犬や猫に危険な動物用薬剤・サプリメント・食品など
-

ペット用サプリメントのトリセツ【第4回】サプリメントの規定量と注意点
-
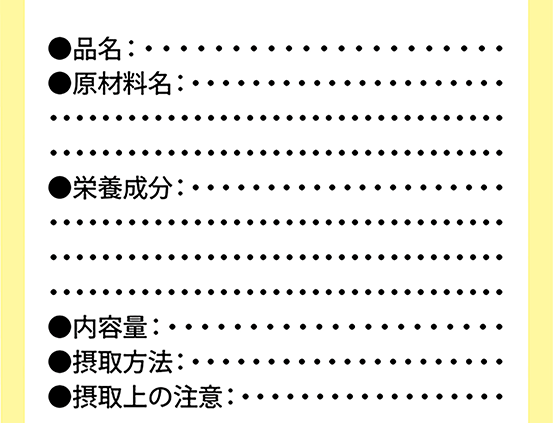
ペット用サプリメントのトリセツ【第3回】製品の良し悪しの見分け方(原材料表示、エビデンスなど)
-
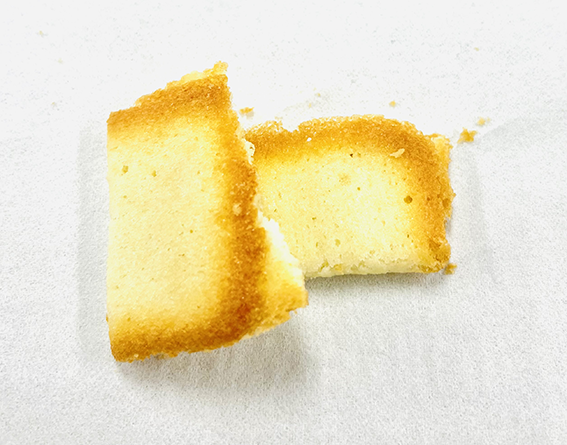
ペット用サプリメントのトリセツ【第2回】
サプリメントを投与しているのになぜ効かないのか -

ペット用サプリメントのトリセツ【第1回】
犬や猫にサプリをあげる前におさえておきたいこと












