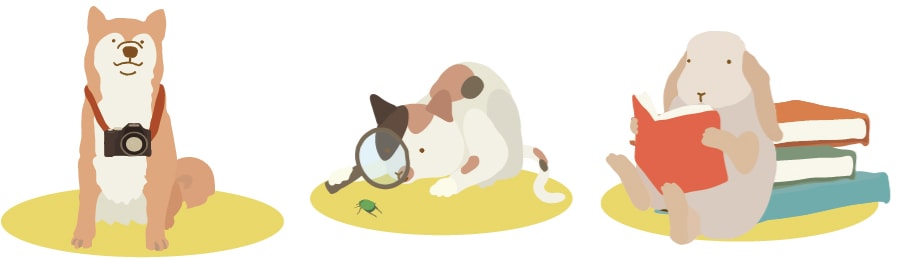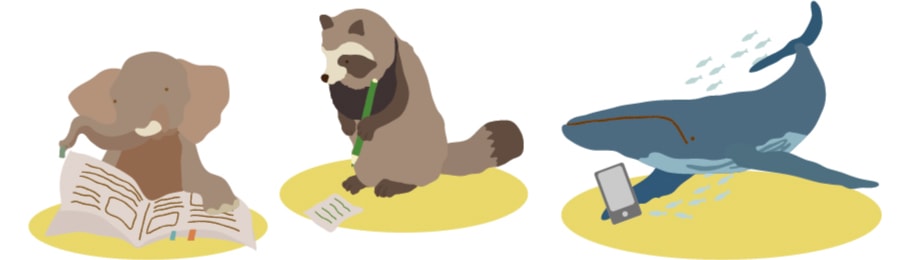「病院、断固、拒否!」コタロの大脱走
2006年生まれのコタロ(キジ猫のオス)6才の6月。
キリのいい数字なのでよく覚えている。
梅雨のさなか、その日は珍しく晴れた。午後遅くなってもあかるく、そこここに犬を連れて散歩する人たちがいた。すでに夏の夕方のようだった。
コタロは怒っていた。意に反して、ペットキャリーに押し込まれ、テリトリーから外れた道を進んでいたからだ。さらに腹立たしいことには、キャリーを運搬する人間の家族はどうやら、病院へ向かっているようなのだ。キャリーごしに、
「コタロは膀胱炎じゃないかな」
「うん、よくトイレに行ってるね。しばらく座り込んでるし……」
「それでちょっぴりしか出てないし」
などという会話が聞こえてくる。
「尿路結石だと怖い」とか、「いや、元気があるから大丈夫」とか。
元気なのになぜ病院へ行くのか?
大嫌いな病院。
ずっと前に「去勢手術」というのに連れていかれて、そこで大暴れしたのに恐れをなしたか、以来、人間の家族は「病院へ行こう」とは言わない。ちょっと風邪気味の時も「お薬飲もうね」ですませたじゃないか。
なのにいや増す不穏な気配。
気に入らないったら気に入らない。
病院、断固、拒否!
全力闘争突入だ!!
ナメんなよ、とハチマキを締めたいところ。で、コタロはパワー全開大暴れ。
夫と私と2人で必死におさえていたキャリーケースはバラバラになってふっ飛んだ。
コタロもふっ飛んだ。――とみるまに、ずんずん駆けていく。
「コタロ!!」と2人して叫ぶと、一度だけ立ち止まって振り向いたがそれきり、家並みのかどを曲がり、私たちが駆けつけた時には誰もいなくて、生け垣に縁取られた道だけがぽつんと夕日をあびていた。
夫と私は見知らぬ家々を片端からピンポンしては生け垣の中から縁の下、庭の隅々まで見せてもらった。でもコタロはいなかった。
打ちひしがれて夜道を戻る。これを絶望と言わなくてどう言おう。
探し回るも見つからず……

コタロはてのひらに乗りそうなほど小さい子猫の頃、兄弟のマシロ(白に黒ブチ柄のオス)と一緒に母さん猫に連れられ一家でうちの庭にやってきた。愛らしい子猫はてのひらに乗るどころか人の手を怖がった。すでに野良猫教育が施されて人間になれていなかった。それでも年経て徐々に、うちの猫になっていったが、勝気なコタロにはどこかワイルドな一線を画すようなところがあるのだった。
「猫は家につく」というけれど、コタロは帰ってきてくれるだろうか。――自信がなかった。そもそも、うちを「家」と認識してくれているのかどうか。わからない。
体調不良なのに。病気で亡くなった母さん猫に「子猫の面倒はみる」と約束したのに。
それから毎日、コタロを探して歩いた。コタロが消えた周辺のお庭に入らせてもらい、文字通り草の根分けて探す。許可いただけるところには保護猫団体から借りた捕獲器を置いた。「ルートに使用済みトイレ砂を撒く」というペット探偵の話から、ヘンゼルの道標のように道の端々に猫砂を少しずつ撒いた。遠くまで声の通る夜更けには名前を呼んだ。雨が降ると寒がっていないか、帰路の匂いが消えやしないか、心配だった。雨はまたよく降った。雨に降り込められ色を失くした空模様はそのまま、私の心模様だった。
コタロの帰る場所
そうして1週間が過ぎた午後9時頃。
庭へ続く石段のあたりで、小さく猫の鳴く声がした――気がした。母さん猫が最初に子猫たちを引き連れてきた石段だ。
そっとガラス戸を開けてみる。
するとそこにコタロがいた。
痩せて目がつり上がり、面差しが変わって見えたけれど、間違いない。心臓が口から飛び出しそうになるのをのみこんで、
「おかえり、コタロ」
と言った。不覚にも声が震えた。
コタロはニャンとも言わず入ってきて、お気に入りの毛布にそそくさと潜り込んだ。
途端に、世界が色つきになった。
そっとガラス戸を閉める。
ガラスに鮮やかに映る、コタロのいる部屋。これを幸福と言わなくてどう言おう。

翌日、コタロは新品の頑丈なキャリーで病院へ行き膀胱炎と軽い風邪の薬をもらった。
それにしてもどうやって、コタロは見知らぬ場所から帰れたのだろう? 1週間、試行錯誤しながら歩いたか、あるいは方角を定め確信をもって一気に駆けてきたのか。車道を渡ったか歩道橋を来たか、それは人通りも車通りも絶えた深夜だったろうか――。謎は今もって謎のまま。
猫は感覚や感触を言葉にしないことで、むしろ言葉に疎外されない、生きるに必要な能力を持っているのだと思う。その全知全能をふり絞り、きっと様々な危機をくぐり抜けて、「おうちへ帰ろう」と無事、帰りついた。コタロの「おうち」が私たちの家であったことが、しみじみ嬉しかった。

晩年、認知症を患った母は、夕方になるとよく「うちに帰る」と言い出した。「ここが家だよ」と応じても頑なに「違う」と言い張る。ある時、説得に疲れ、「じゃあ、おうちに帰ろうか」と、母と手を繋いでうちを出た。他愛ないおしゃべりをしながら、草花を摘んだり歌を歌ったりして、そのへんをぐるっとひと回りした。そうして戻ると、母は晴れやかに「ただいま!」を言った。玄関がぽっと明るむような極上の笑顔だった。
帰る場所のあることの幸福を思う。そして帰る場所であることの幸福を思う。

【執筆】
岡田貴久子(おかだ・きくこ)
1954年生まれ。同志社大学英文学科卒業。『ブンさんの海』で毎日童話新人賞優秀賞を受賞。『うみうります』と改題し、白泉社より刊行。作品に『ベビーシッターはアヒル!?』(ポプラ社)『怪盗クロネコ団』シリーズ、『宇宙スパイウサギ大作戦』シリーズ(以上理論社)『バーバー・ルーナのお客さま』シリーズ(偕成社)など多数。『飛ぶ教室』(光村図書出版)でヤングアダルト書評を隔号で担当。神奈川県在住。
-

猫と暮らし、文を書く【第12回】猫の流儀
-

猫と暮らし、文を書く【第11回】天上天下唯我独尊、猫
-

猫と暮らし、文を書く【第10回】初めてのこと
-

猫と暮らし、文を書く【第9回】安心な寝床とごはん、愛がある場所
-

猫と暮らし、文を書く【第8回】あれが好き、これは嫌い
-

猫と暮らし、文を書く【第7回】はじめて一緒に暮らした猫
-

猫と暮らし、文を書く【第6回】生きているヨロコビ
-

猫と暮らし、文を書く【第5回】ハナちゃんからの贈り物
-

猫と暮らし、文を書く【第4回】帰る場所である幸福
-

猫と暮らし、文を書く【第3回】「良い手」であるために
-

猫と暮らし、文を書く【第2回】人知の及ばぬ領域
-

猫と暮らし、文を書く【第1回】名に込められた願い