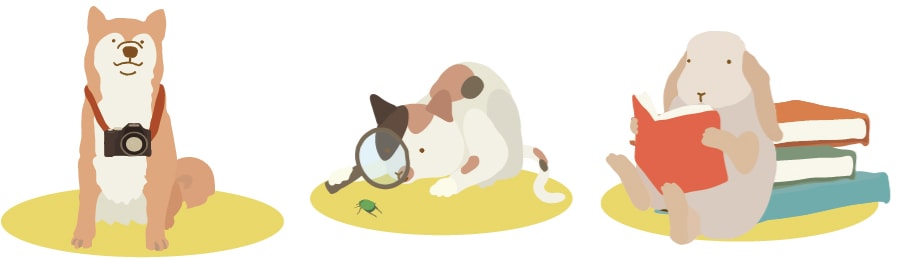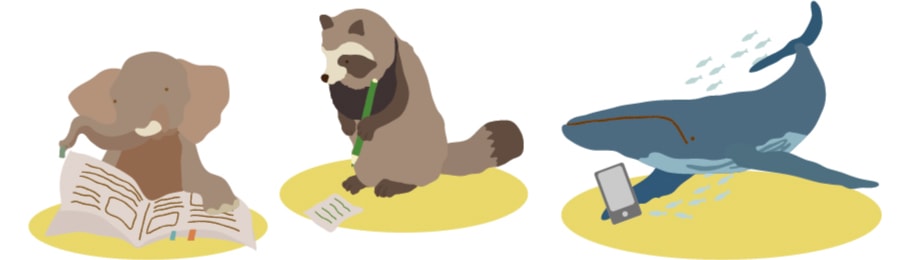思いがけない再会
その日は建国記念の祝日だったので、学校がお休みだった。
子どもがうちにいる時には文を書かない。次女が小学生だった当時はそう決めていた。
自慢ではないが、私は何によらず仕事が遅い。「文を書く」となると、そこへ、心平らかでいられない、というのが加わる。適切な言葉や展開が浮かばないまま、時間ばかりがジリジリと過ぎていく。気持ちもジリジリする。イライラすると言ったほうが当たりだ。これは掲げる理想と現実にギャップがあるからに他ならないのだが、はた迷惑この上ない。子どもが楽しめるお話を書こうというのに、イライラしてどうする。亡き母も、機嫌のいい人が一番偉いと言っていた。
というわけで、昼少し前、日頃は後回しにしている用事(図書館に本を返却するとか手紙の投函とか夕飯の買い物だとか)をすませるべく、私は足早にバス停へと向かっていた。雪のちらつく寒い日だった。
公園を突っ切ろうとして、その時、ベンチの裏に子どもたちが数人、ひとかたまりでいるのに気がついた。静かに頭を寄せてしゃがみこんでいる、その様子が気になり、肩ごしに覗いてみて目をみはった。
子どもたちの輪のなかに子猫がいた。
薄茶トラの、まだ4か月才ほどのが1匹。ほわほわのちっちゃな頭のてっぺんに、線で一筆書きしたみたいな花の模様が一つある。
私がそんなにも驚いたのは、子猫がいたからじゃない、子猫が私の知っている「チャッチビちゃん」だったからだ。
当時はまだ「保護猫」という言葉はなかったけれど、地域の野良猫にごはんをやりながら避妊・去勢手術をしてリリースする、貰い手を探すという活動を、隣り近所で私たちはやっていた。母さん猫に連れられ食事に来ていたのがその「チャッチビちゃん」で、2、3日前には、枯葉を獲物に見立てて遊んでいたのではなかったか。それがどうしたことだろう、
「おばちゃん、この猫歩けないんだよ」
「ここで動けなくなってたの」
「だからほら、車に乗っけてあげたんだ」
子どもたちが口々に言う。
子猫は積み木の台車に乗せられ、両後足を妙なかたちに投げ出している。抱き上げてみると後足はブラブラで、それでも知った顔を見て安心したのか、ミャアと小さく鳴いた。
私は用事をほっぽりだして子猫を動物病院へ連れていった。
診断は骨盤骨折による脊髄損傷、下半身の麻痺。何か事故に遭ったのかもしれない。わからない。わかったことは2つ。おそらく一生、自力で排尿できない。歩けない。先生が圧迫排尿すると、トマトジュースのような真っ赤なオシッコが膿盆に溢れた。
その日から「チャッチビちゃん」改め「ハナ」になった子猫は、うちの猫になった。

冬休み中だった学生の長女と私は、病院に通って圧迫排尿のやり方をおぼえた。ハナちゃんには1日3回の圧迫排尿が必要で、膀胱を圧す係と猫を支える係の2人がいなければならなかった。シッポ穴の空いたオムツも必要だった。ハナちゃんは、両前足で上半身を支えながら、オムツのお尻を弾ませて上手に移動するやり方をおぼえたからだ。
猫はもともとずば抜けたアスリートだ。時速50キロメートルで走り体高の5倍を跳び、視覚、聴覚など五感の鋭敏さは人間の比ではない。その身体能力の高さをもってすれば、機能しない器官があっても、家のなかであればハナちゃんは自由自在なのだった。
ポンとオムツを弾ませ、どこへでも行ける。ポポンと、階段だって上れてしまう。お気に入りの椅子や窓辺やひざに乗りたい時には、人間の家族を呼べばいい。


困難を乗り越え天寿を全う
愛情深くさっぱりとした気性は先住猫2匹にも愛された。圧迫排尿に(双方)慣れて、生活のリズムができると、小柄で食の細かったハナちゃんはよく食べるようになった。「食べられる」ということは「生きられる」ということ、「食べたい」と「生きたい」は同義なのだった。
こうして、当初、病院で「1週間生きられない」と告げられたハナちゃんは、18年と6か月を生きた。長女は就職後、家を離れ、結婚して母親になった。小学生だった次女はハナちゃんとすこぶる気が合い、喜びも悲しみも分かち合って大人になった。大学を卒業してから就職、結婚をし、母親になった。


コールとレスポンス
猫には愛しかないけれど、人間の家族のあいだには愛も憎もある。反抗期だの病気だの休職失職転職だの、天から降ってはまた、湧いてきたりもする試練やら揉め事やらきりなくあり、でもそのさなかにも、圧迫排尿だけは1日も欠かせなかった。それはつまり、1日たりとも家を空けられないということ。日に3回、定刻には万障繰り合わせ、2人揃わなければならないということ。顔を背け口をきかないような時でも、その時だけは、丁寧にハナちゃんを支えて「頑張ったね」「さっぱりしたね」と声をかける。否も応もなく家族一丸とならざるを得なかったあの時間は、ハナちゃんのくれた夢のような時間だったのだと、しみじみ思う。
今日も私は、掲げる理想と現実とのギャップを嘆きつつ、文を書いている。
進歩のない私と、進歩なんかてんでする気のない、ゆえに心平らかな猫たちと、ふと目が合う時、脳内に漫画の吹き出しみたいに浮かぶ言葉がある。―「善きものからの呼びかけ(コール)があれば、それに応答(レスポンス)する責務を人間は負わなければならない」。責務を負うために人間は存続せよ、と続く、これは哲学者ハンス・ヨナスの言葉で、彼の言う「善きもの」とは「子ども」を指すのだけれども、個人的にはそこへ、猫とか犬とか付け加えてもいいんじゃないか、と考えている。
呼ばれたからには応えねばなるまい。
それが空耳でも。年がら年中、彼らに振り回されることになるのだとしても。
【執筆】
岡田貴久子(おかだ・きくこ)
1954年生まれ。同志社大学英文学科卒業。『ブンさんの海』で毎日童話新人賞優秀賞を受賞。『うみうります』と改題し、白泉社より刊行。作品に『ベビーシッターはアヒル!?』(ポプラ社)『怪盗クロネコ団』シリーズ、『宇宙スパイウサギ大作戦』シリーズ(以上理論社)『バーバー・ルーナのお客さま』シリーズ(偕成社)など多数。『飛ぶ教室』(光村図書出版)でヤングアダルト書評を隔号で担当。神奈川県在住。
-

猫と暮らし、文を書く【第12回】猫の流儀
-

猫と暮らし、文を書く【第11回】天上天下唯我独尊、猫
-

猫と暮らし、文を書く【第10回】初めてのこと
-

猫と暮らし、文を書く【第9回】安心な寝床とごはん、愛がある場所
-

猫と暮らし、文を書く【第8回】あれが好き、これは嫌い
-

猫と暮らし、文を書く【第7回】はじめて一緒に暮らした猫
-

猫と暮らし、文を書く【第6回】生きているヨロコビ
-

猫と暮らし、文を書く【第5回】ハナちゃんからの贈り物
-

猫と暮らし、文を書く【第4回】帰る場所である幸福
-

猫と暮らし、文を書く【第3回】「良い手」であるために
-

猫と暮らし、文を書く【第2回】人知の及ばぬ領域
-

猫と暮らし、文を書く【第1回】名に込められた願い