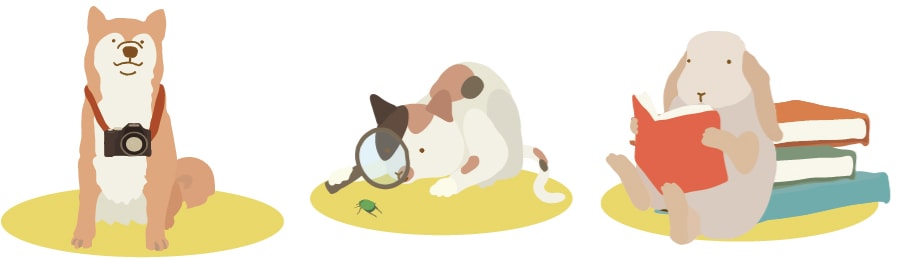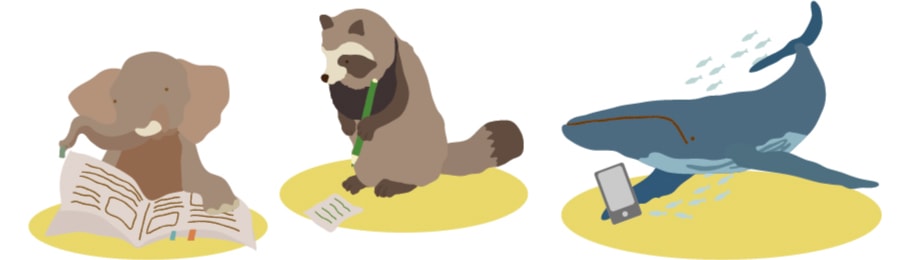いとこと猫とハイビスカス
はじめて一緒に暮らした猫は、私が22才だった秋に来た。
ある日の午後、当時、夫と二人で住んでいた小さいアパートの1階の、さらに小さいベランダに「ニャン」という顔をしてすわっていた。鼻づらの白いキジ猫(♂)は痩せて小さく見えたが、今思えば、1才にはなっていたかと思う。どこから来たの、と聞くまでもなく、猫はベランダむこうの原っぱを越えて来たに違いなかった。背中がイノコズチだらけだった。声をかけられた猫は熱心にのどを鳴らし、ゆうべの鍋の残りのチクワを出してやると、それをきれいに平らげてうちの猫になった。ミィ、と呼ぶ声が可愛くて「ミィ」と名前をつけた。

1977年(昭和52年)、夫と私は3月にそれぞれ京都の大学を卒業して、5月に結婚したばかり。就職した夫の最初の赴任地が横浜だったので、一つ違いのいとこが先立って港北区日吉に新居を見つけてくれていた。私は父の仕事の関係で、関西で育ったのだが、両親ともに東京出身で、親戚はみな、東京とその近辺の横浜や鎌倉在住なのだった。
「そりゃもう小さいアパートだけど、二人で住むんだからさ。駅近だし、ほぼ新築だし、近所にスーパーマーケットもあるし。家賃もお手頃」。いとこの言葉どおり、2階建の小さいアパートは日当たりもよく、二人で住むのにぴったりではあったけれど、さらに小さい間口からは、結婚に際し父母の持たせてくれた家具・調度品がことごとく入らなかった。外した掃き出し窓から搬入してどうにかおさまり、結果、小さい部屋は余計に狭くなって、私たちは新婚らしくいつもぴったりくっついていなければならなかった。
そこへ、ナイターのある日には当たり前のように、いとこが立ち寄る。その頃、いとこは慶応大学日吉キャンパスに通う学生で、スマホなどなかった時代のこと、講義が長引いても、うちに来れば試合を見逃さずにすむというわけだ。夕飯のテーブル―二人用―を三人でぎゅうぎゅう囲み、日本社会の先行きなど憂えつつ―当時の若者はみな政治を語った―、ナイターを観戦する。ミィが散歩から戻れば、一つきりの部屋はもう満員になり、台所から戸口へ繋がるガラス戸が塞がってトイレへも行けやしない。
夜更けてご機嫌で帰るいとこに、「謀られたか!」という気はしたが、実際、家賃はお手頃で、スーパーマーケットの魚も野菜も安く新鮮だった。その入口にあった花屋で、夏の終わりに、安売りしていたハイビスカスを買った。高さ20センチほどの小ぶりな鉢に赤い花が一輪、目に染みた。鉢を抱えた帰り道、鼻先で揺れる花のきっぱりと混じりけのない明るさになぜだか励まされる気持ちになり、その時気がついたのだが、自分のために花を買うのは初めてなのだった。

ミィの災難

そうして冬の初め。
とっぷり暮れた灯ともし頃。
散歩から帰ったミィを見て驚いた。
ひたいの真ん中へんが切れて盛大に血が流れている。ミィはさして気にするふうもなく、ごはんを催促するのだけど、私はおろおろ、ごはんどころじゃない。ああ、ミィが死んじゃう! リアルな恐怖に胸がドキドキした。すぐそばの電話ボックスに走り、落ちつけ、落ちつけ、と念じながら、ふるえる指で電話帳をめくる。「港北区日吉」「動物病院」「田口良作」を探しあて、ふるえる指でダイヤルを回す。落ちつけ。落ちつけ。何度も回し損ねてようやくつながった田口先生は「すぐに診ましょう」と頼もしい。折よく帰宅した夫と二人、いやがるミィをバスケットに押し込んで、すっ飛んで行った。
先生は五十がらみと思しき恰幅のいい温顔で、ベテランの風情。ミィを見るなり、「これは有刺鉄線に引っ掻けたな」と断じたのはさすがだった。が、診察には手こずる。先生によると「しばらく診療から離れていた」そうで、その上、診察室でパニックになったミィが大暴れしたからだ。傷は浅かった。先生の傷のほうが深かったかもしれない。恐縮する私たちに、先生は、いいよいいよ、と鷹揚に手をふり、「生活も大変な若い人が猫を養うなんて感心だ、横浜の未来は明るい」と破顔一笑された。私が教員免許を持っていて求職中だと知ると、「いつでも就職先を世話しましょう」。診療代金は受け取ってくださらなかった。私たちが余程貧しく見えたのか―実際に貧乏だったけれど―、それでもご厚意に甘えてはいけないと、後日、菓子折りを持参したら、病院前に黒塗りの公用車が止まっていた。先生が横浜市議で副議長を務めておられたことを、その時初めて知った。
私は若く迂闊だった。
物のわかった大人たち
消火器詐欺に遭ったのも、この頃だ。
アパートのキッチンの小さな窓越しに、いやにすばやく”身分証”を見せる”消防署員”から、うかうかと2本も消火器を買ってしまった。1か月分の家賃半分ほどに相当する値段だった。交番に被害届を出したものの、逆に不注意を注意される始末。もちろん親にも言えやしない。今日からおかず一品だ、泣く泣く覚悟したところで、なんてありがたいこと、大家さんが買い上げてくれることになった。
「アパートに消火器が必要だと思ってたんだよ、1階と2階にね」
消火器を引き取りに来た大家さんは言う。
ありがたやありがたやと拝聴する私。
「不審者を近づけた責任もあるしね」
いえ、全部、アホな私の責任です。
その時、帰ってきたミィがひらり、部屋に入ってきた。
思わず固まる私。
アパートはペット不可だった。
そんなの関係ないもんねと、ミィは大家さんの足に機嫌よくからだをすりつける。
「可愛い猫だねえ」
そう言って、大家さんは目を細めた。
私は若く迂闊だった。自分がどれほど物を知らないか気づかぬほどに。
そんな私を物のわかった大人たちは甘やかしてくれたのだ。
今や、ハイビスカスは私の背丈を超えた。
庭の日当たりのいい場所で、径45センチほどの大鉢におさまり、冬の初めにうちのなかに取り込む時は夫と二人がかりだ。
夏には毎日のように花を咲かせる。きっぱりと混じりけのない明るさが、今も変わらず私を励ましている。
年経ても未だ、私の迂闊は治らない。
横浜の未来が明るいかどうか、それも未だわからない。

【執筆】
岡田貴久子(おかだ・きくこ)
1954年生まれ。同志社大学英文学科卒業。『ブンさんの海』で毎日童話新人賞優秀賞を受賞。『うみうります』と改題し、白泉社より刊行。作品に『ベビーシッターはアヒル!?』(ポプラ社)『怪盗クロネコ団』シリーズ、『宇宙スパイウサギ大作戦』シリーズ(以上理論社)『バーバー・ルーナのお客さま』シリーズ(偕成社)など多数。『飛ぶ教室』(光村図書出版)でヤングアダルト書評を隔号で担当。神奈川県在住。
-

猫と暮らし、文を書く【第12回】猫の流儀
-

猫と暮らし、文を書く【第11回】天上天下唯我独尊、猫
-

猫と暮らし、文を書く【第10回】初めてのこと
-

猫と暮らし、文を書く【第9回】安心な寝床とごはん、愛がある場所
-

猫と暮らし、文を書く【第8回】あれが好き、これは嫌い
-

猫と暮らし、文を書く【第7回】はじめて一緒に暮らした猫
-

猫と暮らし、文を書く【第6回】生きているヨロコビ
-

猫と暮らし、文を書く【第5回】ハナちゃんからの贈り物
-

猫と暮らし、文を書く【第4回】帰る場所である幸福
-

猫と暮らし、文を書く【第3回】「良い手」であるために
-

猫と暮らし、文を書く【第2回】人知の及ばぬ領域
-

猫と暮らし、文を書く【第1回】名に込められた願い