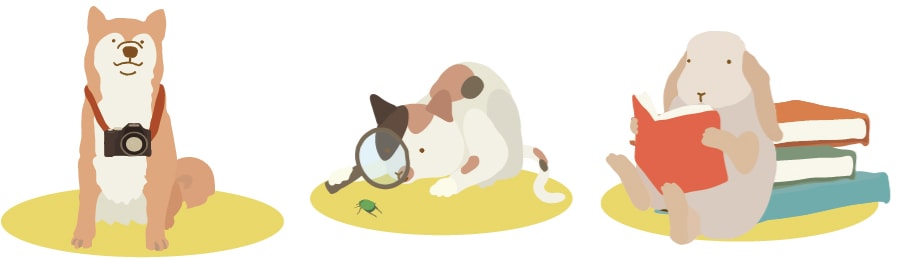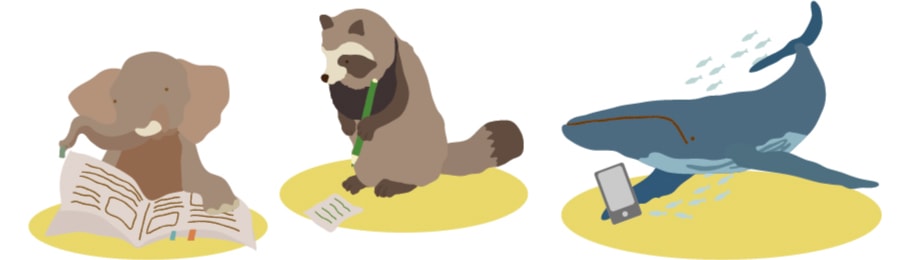猫の居場所
うちには7匹の猫がいる。人間は夫と私の2人だから一目瞭然、猫の数の方が多い。
かつては猫が14匹いたこともある。
その頃は娘家族3人も同居していたのだがやはり一目瞭然、猫の方が多かった。
どうしてこう猫が集まるのかと問われれば―とくに誰も問わないが―、答えはシンプルで、子どもたちや私が拾ってきてかつ、貰い手が見つからなかったからだ。
拾ったのが年端もいかぬいたいけな仔猫ならば、そのかわいさに射抜かれて、誰かしら貰い手が見つかるのだけど、結局、うちにとどまることになった猫たちにはそれぞれに訳がある。仔猫ではあっても、まだ目も開いておらず今すぐ死にそうだったり、その目に不具合があったり、汚れきって病気だったり―。大人の猫となると、さらに貰い手を得るハードルは上がる。噛み癖があるだの尻癖が悪いだのとくれば、なおさらだ。放浪の末に心が荒んでついた悪癖の数々、ほんとうはこういう猫たちにこそ安心なおうちを、と思うものの、さすがに、貰ってください、とお願いするのは気が引ける。
で、その結果の14匹。
今は7匹。
ユキとチッチ
拾った猫が猫を拾ってきたこともあった。
それは14年前、次女が就職し家を離れてまもなくのこと。
一晩中春の嵐が吹き荒れた翌朝、どこか壊れたところはないか、庭に出て点検していたら、見慣れない白猫が勝手口にいた。痩せて薄汚れてはいるけれど、見れば、ゴールドの目がきろきろと輝くまだ若い大柄な猫。1才か2才か、遊びたい盛りの活力に溢れている様子は、嵐の夜にさんざん遊んじゃってハラペコで、ボク、ここらでちょこっと腹ごしらえしてからおうちに帰りたいんです、と言わんばかりに見えた。実際、すでに去勢されていた雄猫はフレンドリーで私の足にまとわりつき、猫缶を出すと、3缶ぺろりと平らげて優雅に顔を洗う。どこぞのお屋敷のお坊ちゃんといった風情なのだった。
ところがそれから毎日、”お坊ちゃん”はやってきた。
庭や玄関回りをうろついてはごはんをよく食べ、どこかへ出かけてもまた来る。縁側の猫ハウスに寝泊りして”お屋敷”へは帰らず、やがて当たり前に自由に家を出入りするようになった。嵐の夜にはどこへも行かずにお気に入りの毛布にくるまって熟睡する。
動物愛護センターや近隣の動物病院に問い合わせても、「白猫を探しています」という話はなかった。情報があれば知らせます、と言われて待つも、連絡はとんと来ない。誰にも探されていないなんてあんまりだ、と思うと同時に、連絡が来なければいいのに、とも思う。うちのこになったら、何はなくとも安心な寝床とごはんがある、愛がある、気楽に暮らせる。当時、何かと癖のある先住猫たちがいたけれど、いかにも”お坊ちゃん”な気のいい白猫は誰にでもフレンドリーで上機嫌なのだった。
こうして夏の初め、白猫はうちの「ユキ」になった。

そのユキがある日の午後、子猫を連れてきた。生後半年くらいの白キジ柄(♀)で、物怖じすることなくクリクリした大きな目で私をまっすぐ見つめる。
「ユキの彼女?」と聞くと、ユキは、そうだ、と言う。なにか食わせてやってくれよ、と言うので、ごはんを出してやると、子猫はドライフードも猫缶もよく食べた。それをユキは慈父のような―、いや、雄猫ながら、慈母そのものの目で見守る。子猫が食べ終わると顔を舐めてやりクビを掻いてやり、かいがいしく世話を焼く。慈母なのだ。
それから毎日、子猫がユキの後をちょこまかついて歩くのを見るようになった。ユキが走れば走り、ハクモクレンの枝を揺らせば幹にかじりつき、くっついて眠る。姿が見えないと「チィチィ」鳴く。だからチッチ。


純粋な関係性
あれから猫も人も増えては減りまた、増えもしたが、ユキとチッチの関係は変わらない。母と幼子のように親密だ。
猫であれ人であれ、一回限りの生のなかで、そんな関係を結べるのはどんなにか幸せなことだろうと思う。
イギリスの社会学者ギデンズは、人間どうし「純粋な関係性(ただ単に好きだと思うこと)」を結ぶには、利害や性別によって割り振られてきた役割―たとえば誰がごはんを作るの、とか、お皿を洗うの、というたぐいの―に、都度調整が必要なため困難もあるとしている*。
猫は役割とは無縁ゆえ、「純粋な関係性」が成り立つのかもしれない。
人はそもそも社会的動物だから、社会的な関係性があるからこそ自己を規定できるという面もある―たとえば、母であり60代女性であり娘だったし文を書く、そんな役割を生きている、というような。イギリスの作家カズオ・イシグロはその著書(『クララとお日さま』:土屋正雄訳、2021年、早川書房)で、人の魂(心と呼ばれるもの)は周囲の人々がその人を愛し唯一無二だと感じる気持ちのなかにあるのではないか、とさえ述べている。
猫も7匹いれば緩やかに社会を形成するのだが、猫の方が悠々自適に生きている気がするのは気のせいか?
私はくっついて眠るユキとチッチを眺めながら、その春、家を離れ大阪に着任した娘に思いを馳せた。あのこが小さい頃は……、とうっかり感傷に浸りかけるのをこらえ、母親の役割をやり遂げた、子の独り立ちを寿ぐべし、そう思った。やがて、てんやわんやありすったもんだあり、娘とまた同居することになろうとは、当時、知る由もない。


*『猫社会学、はじめます』:赤川学編著,新島典子・柄本三代子・秦美香子・出口剛司・斎藤環著著,2024年,筑摩書房
【執筆】
岡田貴久子(おかだ・きくこ)
1954年生まれ。同志社大学英文学科卒業。『ブンさんの海』で毎日童話新人賞優秀賞を受賞。『うみうります』と改題し、白泉社より刊行。作品に『ベビーシッターはアヒル!?』(ポプラ社)『怪盗クロネコ団』シリーズ、『宇宙スパイウサギ大作戦』シリーズ(以上理論社)『バーバー・ルーナのお客さま』シリーズ(偕成社)など多数。『飛ぶ教室』(光村図書出版)でヤングアダルト書評を隔号で担当。神奈川県在住。
-

猫と暮らし、文を書く【第12回】猫の流儀
-

猫と暮らし、文を書く【第11回】天上天下唯我独尊、猫
-

猫と暮らし、文を書く【第10回】初めてのこと
-

猫と暮らし、文を書く【第9回】安心な寝床とごはん、愛がある場所
-

猫と暮らし、文を書く【第8回】あれが好き、これは嫌い
-

猫と暮らし、文を書く【第7回】はじめて一緒に暮らした猫
-

猫と暮らし、文を書く【第6回】生きているヨロコビ
-

猫と暮らし、文を書く【第5回】ハナちゃんからの贈り物
-

猫と暮らし、文を書く【第4回】帰る場所である幸福
-

猫と暮らし、文を書く【第3回】「良い手」であるために
-

猫と暮らし、文を書く【第2回】人知の及ばぬ領域
-

猫と暮らし、文を書く【第1回】名に込められた願い