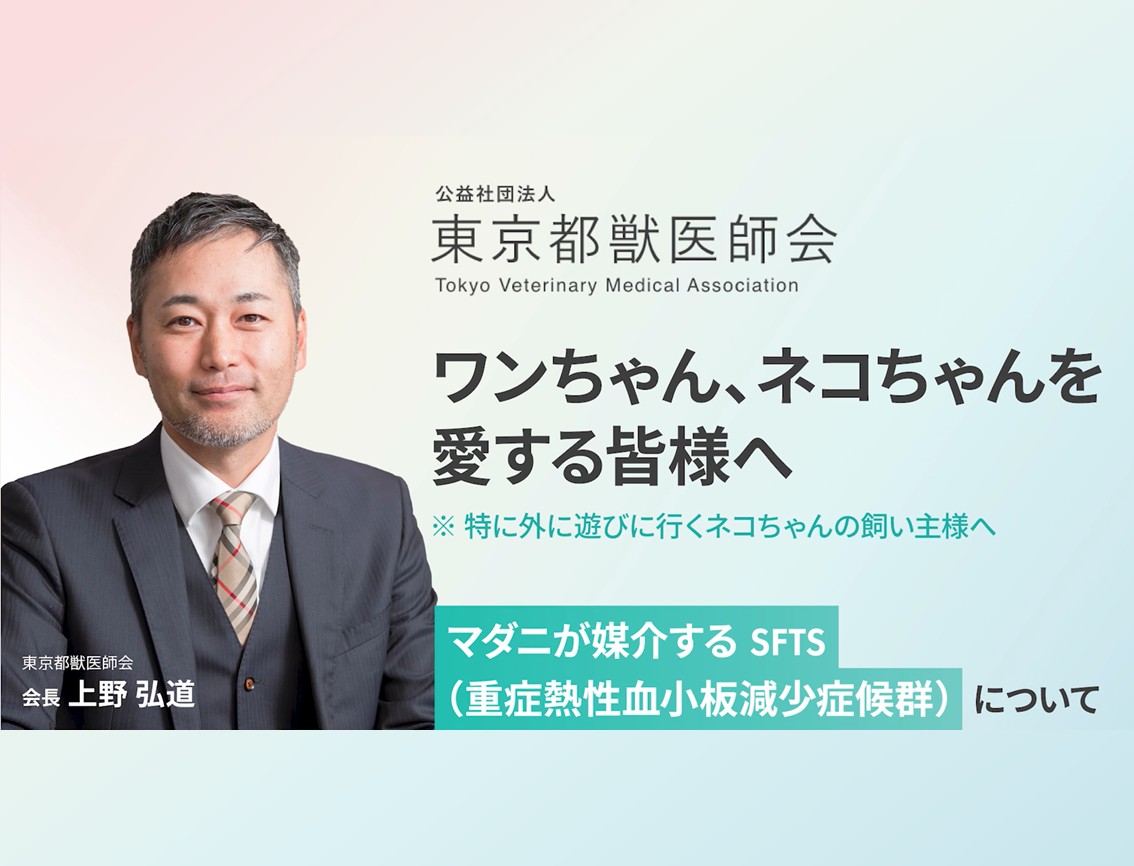前回は、畜産物の生産を支える牛の飼料について紹介しました。現在、濃厚飼料の原料となる穀類は大部分を外国からの輸入に頼っていますが、畜産物の安定的かつ持続的な生産のためには、飼料の国産化を進めることが必要です。
今回は、そんな国産飼料の生産拡大についての取り組みを紹介します。
水田を活用した飼料用イネやとうもろこしの生産
飼料用イネとは、牛のエサにする専用品種のイネです。穂の部分だけではなく、茎葉部をまるごと刈取り、乳酸発酵させて利用するもの(稲ホールクロップサイレージ、以下稲WCS)や、私たちが食べるお米と同じようにイネの子実のみを収穫し利用するもの(飼料用米)があります。

飼料用イネは、水田農業の枠組みをそのまま利用できるため、近年は水田の転作作物*¹として作付面積*²が増加してきました。また、青刈りとうもろこしも水田の転作作物として作付けが推進されています。こちらは、飼料用とうもろこし(デントコーン)を完熟前の時期に収穫して、稲WCSと同様に、茎や葉、実のすべてをサイレージに調製して飼料として利用します。

*¹ 転作作物:同じ農地で栽培するそれまでとは異なる作物のこと
*² 作付面積:農地のうち、実際に作物が植えられている面積
サイレージとは、牧草や上述の飼料作物を適度な水分を保った状態で密封し、乳酸発酵させて貯蔵性を高めた飼料です。密封して嫌気状態(酸素のない状態)になると、乳酸が生成されpHが低下します。このような酸性状態では雑菌が増殖できず、腐敗が進みません。乳酸発酵が十分に進んだサイレージは嗜好性も高く、牛が好んで食べてくれます。
耕作放棄地を利用した放牧
放牧では、牛が放牧地の草を直接食べることで飼料生産や給餌が省力化できます。また、牛が自ら放牧地に排せつするため、排せつ物の処理を省力化できるメリットもあります。肉用繁殖牛では、利用されなくなった中山間地域の水田や耕作放棄地*³を活用した放牧が行われています。これらは、耕作放棄地の解消や集落の景観形成、農地保全にも寄与しています。

*³ 耕作放棄地:過去に耕作していた土地で、過去1年以上作物を栽培せず、今後もする考えのない土地
エコフィードの利用
エコフィードとは、食品を製造する際に生じる副産物(パンくずや豆腐粕、焼酎粕など)や、売れ残った食品や調理残さ(野菜のカットくずなど)、農場で生じる規格外野菜などを利用して製造された家畜用飼料です。令和5年度の食品廃棄物1426万トンのうち1036万トンが再生利用されており、そのうち約8割が飼料として利用されています。エコフィードを活用することで、フードロスの解消だけでなく飼料コストの削減にもつながります。エコフィードの利用による畜産物の品質向上効果も見込まれ、ブランド化して販売する取り組みもされています。食品循環資源を飼料として生まれ変わらせる過程において、異物混入を防止するために分別を徹底することや、病原微生物による汚染を防止するために加熱処理規定を順守するなどの厳しい品質管理も求められます。エコフィードは牛だけでなく、養豚や養鶏の現場でも利用が進んでいます。
おわりに
私たち消費者が、これからも国際情勢に左右されず安定的に国産畜産物を口にできるようにするためには、食料自給率だけでなく家畜の飼料自給率の向上も重要な課題なのです。いま国産飼料に立脚した畜産への転換が求められています。
[参考資料]
・農林水産省、「飼料をめぐる情勢」、飼料、基本情報、https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/index.html
・農研機構webページ、「家畜のエサにする飼料用イネ」、https://www.naro.go.jp/laboratory/tarc/contents/feed/index.html
・農林水産省webページ、「青刈りとうもろこし生産の推進について」、https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/aogari_corn.html
・農畜産業振興機構 webページ、「外部寄稿 放牧をめぐる情勢について」、https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_001268.html
・農林水産省、「エコフィードをめぐる情勢」、エコフィードについて、エコフィードをめぐる情勢について、https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/attach/pdf/ecofeed-185.pdf
[写真出典]
・写真1:農研機構webページ
【執筆】
岩崎まりか(いわざき・まりか)
獣医師、博士(獣医学)。2010年に日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科を卒業後、山形県農業共済組合にて9年間、乳牛・肉牛の診療に従事。その後、同大学にて博士号を取得。同校でのポストドクターを経て、2022年より東京農業大学農学部動物科学科で、主に牛の生産性や疾病、飼養管理についての研究および学生教育に従事している。
「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!