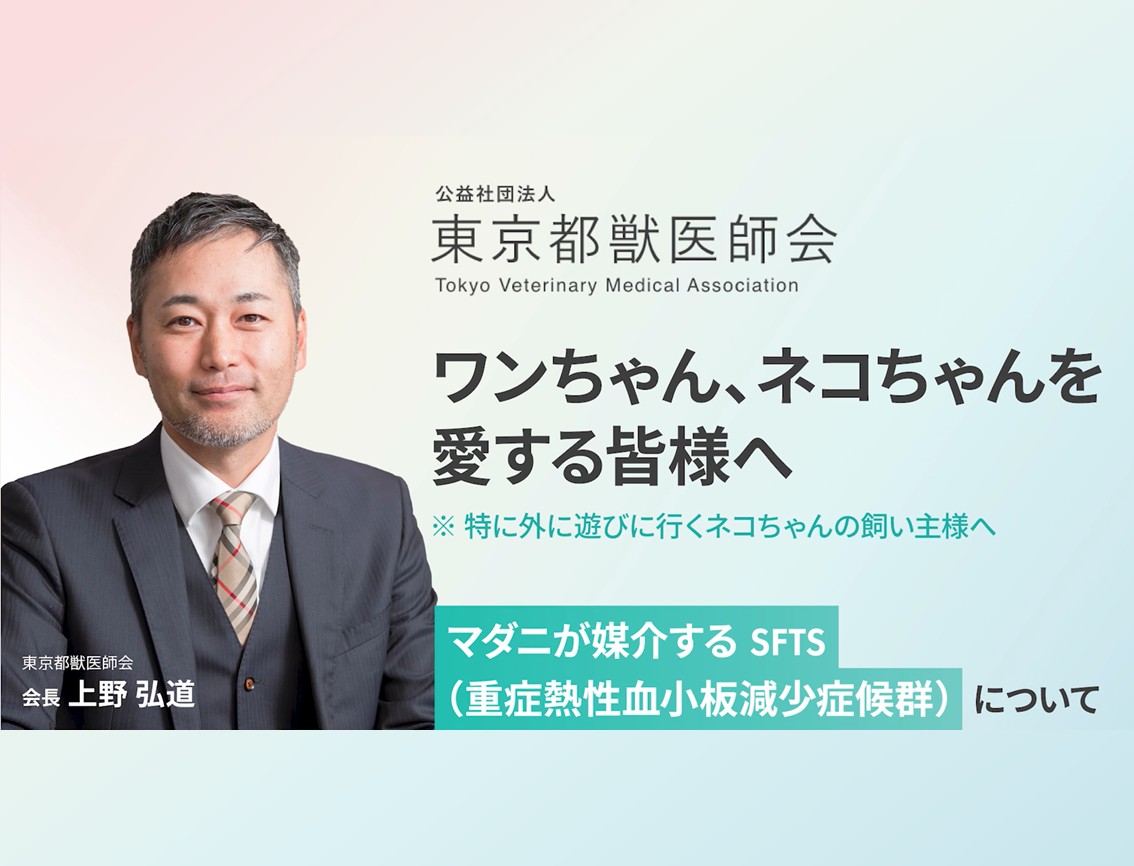沖縄美ら海水族館館では、アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、クロウミガメの計5種類のウミガメを約170頭飼育しています。
今回はその中でも最も多く飼育している、タイマイについて紹介します。
※情報は2025年6月30日時点のものです
鳥のようなくちばしをもつウミガメ(沖縄美ら海水族館)
タイマイはこんな生き物
タイマイ(ウミガメ科タイマイ属・学名Eretmochelys imbricata)は、世界中の熱帯および亜熱帯の海域に分布しており、IUCN(国際自然保護連合)をはじめ、環境省および沖縄県のレッドリストでも「絶滅危惧種」に指定されています。日本全体ではまれですが、沖縄本島以南で産卵が確認されています。
タイマイの特徴は、くちばしが尖っていることで、その姿がカラスに似ていることから、沖縄では「ガラサーガーミー」と呼ばれています(沖縄方言で「ガラサー」はカラス、「ガーミー」がカメを意味する)。
野生下ではこの尖ったくちばしで、岩の隙間などにいるホヤや海綿動物などを食べていること分かっていますが、これらの餌は年間を通して安定的に入手できません。安定的に入手でき、且つ栄養素が自然界での餌に近いものを検討した結果、成長したタイマイには体重の約1パーセント量のイカと魚を与えています。

タイマイの甲羅は、古くから中国や日本で「鼈甲(べっこう)」と呼ばれる高級な装飾品の材料として珍重されてきました。そんなタイマイはウミガメの仲間でありながら、名前に「ウミガメ」が入っていません。それは、「アオウミガメ」や「アカウミガメ」などの標準和名がつけられるよりもずっと前から、「タイマイ」という呼び名で親しまれてきたからだと考えられています。
所説ありますが、タイマイという和名の由来は、中国語の「玳瑁(ダイマオ)」(美しいカメの意味)が日本語に訛ったものと考えられています。
沖縄美ら海水族館のタイマイの日常
朝、飼育員が餌の準備を行います。
生まれて間もない仔ガメは病気にかかりやすいため、水分補給も兼ねて水でふやかした栄養価の高い配合飼料を与えています。
給餌の際は、餌の食べ方や排便の様子から、個体の健康状態をチェックし、食欲のない個体には、餌料種を工夫をします。たとえば、配合飼料を食べない仔ガメには、イカや魚で作ったミンチを与えることがあります。
また、行動や血液検査結果に異常が見られた場合は、獣医師と相談しながら治療を行うこともあります。
当館のウミガメ飼育プール(ウミガメ館)は屋外に設置されているため、日光などの影響で甲羅に藻が生えやすい環境です。そのため、水槽の掃除とあわせて甲羅をデッキブラシで磨く「掃除の日」を設けています。1週間に2回、プールの水を完全に抜いて掃除をします。
特にタイマイは、甲羅の隣接する鱗板(りんばん:体表を覆っている角質化した鱗)の一部が瓦のように重なっているため、その隙間に入り込んだ藻は落ちにくく、アカウミガメやアオウミガメと比べて磨くのが大変です。

飼育員さんの小話
当館では、繁殖に成功した仔ガメを対象に、配合飼料を用いた飼育を行っています。この方法によって、アカウミガメやアオウミガメのふ化後1ヶ月以内の死亡率をほぼ0パーセントに抑えることができており、安定した飼育成果が得られています。
一方タイマイは、同じ飼育条件にもかかわらず、死亡率がやや高い(2024年度は4パーセント)傾向にあります。野生下のタイマイは主に海綿動物を食べています。海綿動物に含まれる栄養素は複雑であるため、現在使用している配合飼料がタイマイに適しておらず、これが生存率の低下に影響しているのではないかと考えています。そこで不足していると思われる栄養素を餌に添加したり、腸内細菌叢を調べたりすることで、栄養面の改善を図り、死亡率のさらなる低減を目指しています。
これらの取り組みは、飼育技術向上のためだけではなく、タイマイという希少種の成長に必要な栄養素を明らかにする貴重な機会にもなっています。とりわけ、飼育下での繁殖成功例が世界的にも少ない本種において、当館の飼育データは生態解明や保全活動にとって重要な情報となります。
これからも、希少な海洋生物の保全と飼育技術の発展を目的に、ウミガメ類の飼育に取り組んでいきたいと思います。
飼育員さんが教えるウミガメの見どころ
当館のウミガメプール(ウミガメ館)には、人工の産卵場が併設されています。毎年5~9月ごろの産卵期には、ウミガメが産卵のために上陸した足跡が、朝まで産卵場に残っていることがあります。この足跡は、野外では波や風、ほかの動物の歩行によってすぐに消えてしまうため、ここでじっくり観察できることはとても貴重です。ぜひ砂浜の足跡に目を向けてみてください。

通常ウミガメは夜間に産卵しますが、まれに日中に産卵することもあるため、運が良ければ、実際にウミガメが上陸している場面を見ることができるかもしれません。
もし、砂をかき分けているウミガメを見かけたら、驚かさないよう静かに見守ってください。そのまま産卵が始まる可能性もあります。

ウミガメ館の隣にある「仔ガメ育成プール」では、当館で誕生した仔ガメを飼育・展示しています。仔ガメ育成プールでは、ふ化直後の小さなウミガメたちが、少しずつ成長していく姿を間近で観察することができます。甲羅の模様や色、行動の変化など、日々変わっていく様子には多くの発見があります。
たとえば、タイマイは成長すると甲羅に黄色と褐色のモザイク模様が現れますが、実はふ化直後ははっきりした模様ではありません。毎日見ている飼育員でさえ、「いつの間にか模様が出てきている!」と後から気づくこともあるほど、変化は少しずつ進んでいきます。

また、アオウミガメのふ化幼体は黒色の甲羅をしていますが、成長するにつれて放射状の「朝日模様」が出てくることがあります。この模様は、さらに成長する過程で徐々に消えていきます。


アカウミガメでは、椎甲板や肋甲板と呼ばれる甲羅の鱗板が盛り上がり、ゴツゴツした質感になりますが、これも成長とともに滑らかな甲羅へと変化していきます。


このように、種によって異なる成長のプロセスを見比べられるのは、育成プールならではの魅力です。展示されている仔ガメの成長段階は時期によって異なるため、訪れるたびに新しい発見があるかもしれません。
【文・写真】
国営沖縄記念公園(海洋博公園)
〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町石川424番地
TEL 0980-48-3748
公式サイト:https://churaumi.okinawa/
Instagram:@kaiyohaku_churaumi
Facebook:海洋博公園・沖縄美ら海水族館
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!