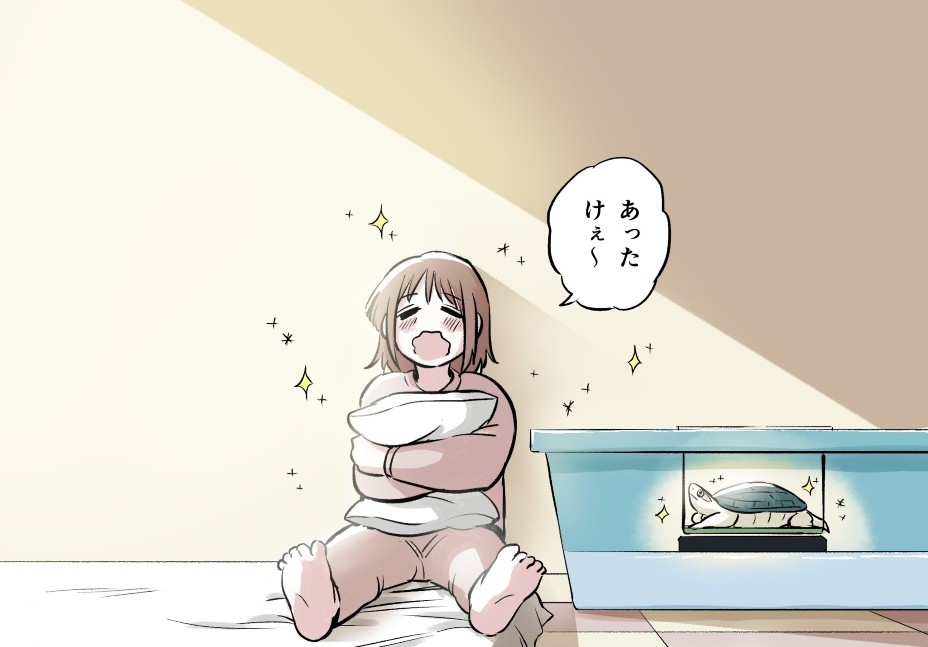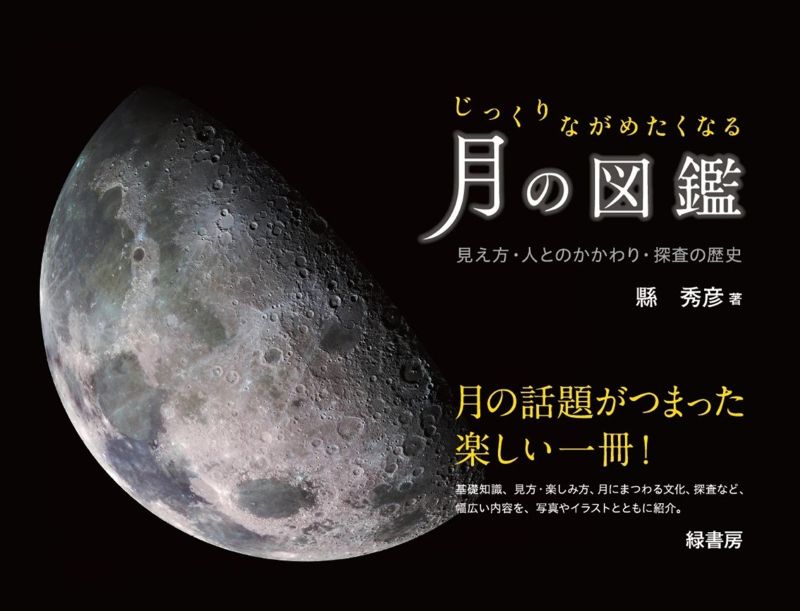ビバリウムとは、箱庭のような飼育スタイルのことで、自然環境を切り取ってきたかのようなレイアウトを飼育ケース内に再現するものです。熱帯雨林のジャングルや水辺を模したものなど、さまざまなビバリウムがあります。水景を再現したアクアリウムや、陸地が半分ほどのアクアテラリウム、水場がないテラリウムなどもビバリウムの一種と言え、最近では苔やシダを豊富に用いたパルダリウムや苔リウムなんていうスタイルもあります。
今回は、そのなかでも爬虫類・両生類の飼育について解説します。
野生環境を再現してみる
爬虫類・両生類の生息環境は多岐に渡り、熱帯雨林のジャングルや砂漠・草原・荒れ地・水辺・湿地・田んぼなど、じつに多様です。ビバリウムに収容する爬虫類・両生類の産地に合わせて植物や砂などを選択すると、雰囲気もぐっとアップします。逆に、アフリカのいきものがいるビバリウムに南米の植物を配すると、どこかしっくりこなかったり、違和感を抱いたりすることもあります。


爬虫類に力を入れている動物園の飼育場は、生息環境を意識して環境設定がされていることが多いので、良い参考になると思います。家庭サイズではありませんが、それもビバリウムと言えるでしょう。

「自然環境を再現する」と言っても、細かな定義はないですし、完全に再現することは不可能です。どこまでこだわるのかは飼育者次第です。日照時間を季節ごとに変えてみたり、小さな沢を設けてみたり……。
一方、爬虫類・両生類を飼育するにあたっては、ヒョウモントカゲモドキやコーンスネーク、フトアゴヒゲトカゲ飼育のように、床材やシェルター、水入れといった必要なものだけをセッティングするほうが飼育者も管理しやすく、一般的です。では、なぜビバリウムでヒョウモントカゲモドキなどを飼育しないのでしょうか? 先述したように、世話の効率化や飼育スペースの関係などが理由の一つで、もちろん、生息環境をイメージして広い飼育ケースを用いたビバリウムで飼育することもできます。

ビバリウムに向いた爬虫類・両生類
ビバリウム向けの爬虫類・両生類の例は、以下の通りです。
※お迎えする前に、よく検討しましょう
・ヤドクガエルをはじめとした中型までのカエル(アカメアマガエルなど)
・小型のヤモリ(チビヤモリやマルメヤモリ・ヘラオヤモリなど)
・小型のカメレオン(コノハカメレオンやカーペットカメレオンなど)
・イモリやサンショウウオの仲間(ファイアサラマンダーなど)
・樹上棲ヘビ(エダセダカヘビやラフアオヘビなど)
・小型のカメ(ミシシッピニオイガメなど)



ビバリウム飼育の魅力やメリット
ビバリウム飼育は、準備や管理が難しいという面がありますが、それ以上に魅力やメリットがあります。
・鑑賞価値が高い
・植物育成も楽しめる
・本来の生息環境に近い
・生体の動きがいきいきしてくる
・生き物たちが落ち着きやすい
・植物が生長するなど飼育環境に変化が見られる
・収容する生体によっては世話が軽減できる
植物の茂みに潜み、葉っぱに擬態しているカメレオンの飼育レイアウトに植物を入れると、生体も落ち着きやすいうえに、葉上の水滴を舐める仕草も観察できます。ヤドクガエルは、ブロメリアの葉の間に溜まった小さな水場に産卵することもありますし、植物の隙間は良い隠れ家となります。スナトカゲ(サンドフィッシュ)は細かな砂の中を泳ぐように移動し、同時にシェルターの役割も果たすので、厚く敷いてあげるとトカゲが落ち着きやすいです。
また、植物をビバリウム内に直接植え込むと、微生物による排泄物の分解も期待できます。ただし、これは排泄量の少ないヤドクガエルのような小型種での話で、他のいきものでは排泄物を取り除く作業が必要になることもあります。
なお、ビバリウムに向かない爬虫類・両生類もいます。せっかく作ったレイアウトを壊したり、植物を踏み荒らしたり、食べてしまったりすることもあります。大型のトカゲやヘビはビバリウム飼育が難しい面もありますが、工夫次第では可能かと思います。飼育する爬虫類・両生類の食性なども考慮しておきましょう。


ビバリウムを作ってみよう!
具体的なビバリウム制作ですが、収容する生体の生息環境を調べることから始めてみましょう。飼育方法の基本を押さえながら、植物などを植え込めるかどうかなどを検討します。実際のところ、ビバリウム内は自然下に比べて光量が不足しがちなので、半日陰で育成できるような植物が向いています。メタルハライドライトを照射しても良いでしょう。
ビバリウム内の要素と自然下のものを比較してみます。
・照明器具=太陽光
・保温器具=太陽熱
・霧吹き=雨や霧
・水入れ=川や池
・水中ポンプ=水の流れ
・ファン=風
・床材=土や砂などの土壌
・餌=食べ物
・掃除やバクテリア=排泄物の分解
飼育ケースはできるだけ容量が多いほうがレイアウトしやすくなります。また、照明器具や床材選びは特に植物と生体の好みを考慮します。流木や枝などの配置を考えたり、地面に起伏を設けたりして、変化をつけてみるとより楽しくなります。パルダリウム用のさまざまな関連製品が流通しているので、それらを活用するのも良いでしょう。
たとえば、空気の流れも考慮し、蓋部分がメッシュ状や細かなパンチング状になっていて、手前にも空気の抜け口があるようなケースも市販されています。さらに、水の流れをケース内で行うのではなく、ミスティングなどで雨を降らせ、排水口から汚れた水をケースの外に出す方法もあります。いつでも新鮮な水を提供してやると、生き物も植物もいきいきとしてきて空気感すら変わり、森林浴をした時のような心地良い空気のビバリウムも作ることができるでしょう。
日頃のメンテナンスとしては、枯れた植物や糞を見つけたら取り除く、くらいでしょうか。正直なところ、植物はそこに植えてみないと生長するかどうかわかりません。うまく根付いたりすることもあれば、なぜか枯れてしまったり……。場合に応じて、配置や種類を変えて植えてみてください。ビバリウム内で開花のシーンを経験すると感動するものです。
以下に使いやすい植物をピックアップしてみました。
・ハイゴケ
・シノブゴケ
・ホソバオキナゴケ
・マメヅタ
・シダ類
・ポトス
・フィロデンドロン
・チランジア
・ネオレゲリア


おわりに
ビバリウムだけではありませんが、各々の工夫次第で楽しみかたが無限に広がります。野生の爬虫類・両生類を観察しに行くと、さまざまなことが学べるので、空気感やいきもの周辺の植物や土壌なども体感しておくと、ビバリウム作りがより楽しくなるはずです。海外や南西諸島まで足を伸ばさなくても、身近な自然環境でも参考になりますし、十分「切り取れる」景色がたくさんあるはずです。ぜひ挑戦してみてください。
【文・写真】
川添宣広(かわぞえ・のぶひろ)
1972年生まれ。早稲田大学卒業。爬虫類・両生類関連の雑誌や書籍を多数手がける。
ホームページ:http://www.ne.jp/asahi/nov/nov/nov/HOME.html
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!