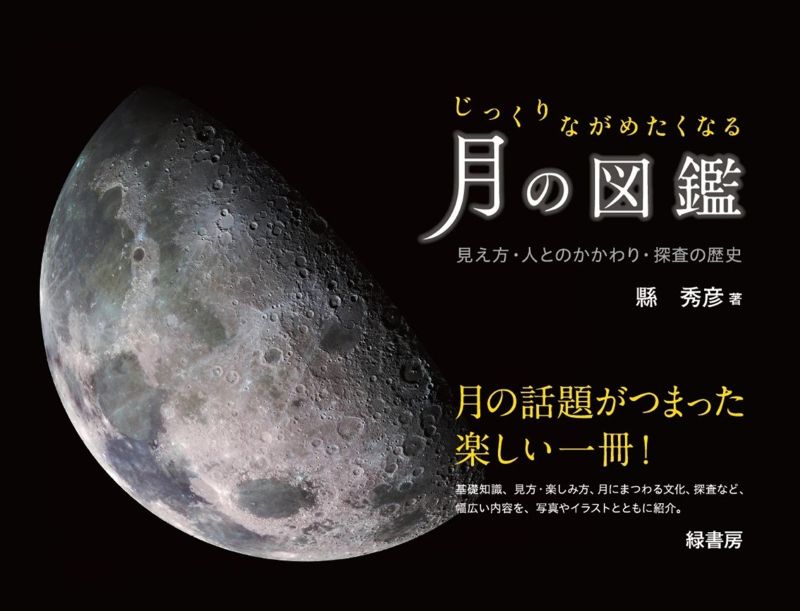さまざまな種類がいる小型哺乳類たちですが、専門の病院や飼育に関する情報が少ないことで困った経験のある方も多いのではないでしょうか?
今回は、ペットとして人気のある代表的な小型哺乳類に共通する悩み事と、対処法を中心にお話をします。
初心者が知っておきたい「犬や猫と違うところ」
それぞれで生態系が異なる
アンデス山脈原産のチンチラやデグー、モルモットなどは、寒い山の上か温暖なふもとに生息しているかで生態が大きく変わります。たとえば、チンチラは標高が高いところに生息しているため寒冷環境に強く、逆に温暖環境には弱いです。
また、ウサギは捕食者から素早く逃げるために骨が軽量化され薄い一方で、筋力が強いので骨折をしやすいなど、種によって身体的特徴の差があります。飼育している子たちが本来どのような環境に生息していて、身体の作りはどのようになっているのかを把握することは、適切な飼い方を考えるうえで重要です。
病気を「隠す」傾向にある
小型哺乳類の多くは病気を「隠す」傾向にあります。野生環境では、自分の弱った姿を見せることは相手に捕食しやすそうだと思わせてしまうためです。「小型哺乳類は体調が急変しやすい」といわれていますが、このように病気を隠すため、わかりやすい症状が認められたときにはすでに病気が進んでいるケースが多いことがその理由のひとつとしてあげられます。
隠された不調を発見するためには、日頃から体重や食事量、外見など、その子の正常な状態をチェックしておきます。そして、少しでも変化を感じたときには、様子を見ずに小さなことでもすぐに動物病院に相談することをおすすめします。
診療ができる動物病院が少ない
犬や猫にくらべて、小型哺乳類の診療ができる動物病院は少数です。いざというときのために、内科治療のみではなく外科手術や入院管理などができる動物病院を見つけておくと安心です。
動物病院に診療範囲を聞くことは問題ありませんので、わからない場合には聞いてみましょう。
実際に「体調が悪そう」で困ったとき、どうすればいい?
観察すべきポイントは、病気によってもさまざまです。すべてを観察したいところですが、中でも重症度が高く、動物種による特徴的なサインを紹介します。
ウサギ <呼吸・体温>
ウサギは鼻で呼吸します。そんなウサギが鼻を大きく広げた呼吸や口を開けて呼吸をしている場合には、呼吸器や心臓などの病気が疑われます。それ以外にも、消化管の病気から2次的に起こることもあります。
また、特に急性胃拡張症候群・小腸閉塞などの胃腸の動きがとまってしまうことでおこる「ショック状態」が認められたときに、体温が低下することがあります。最近普及している赤外線体温測定器などは、数値の正確さは不明ですが体温を測る基準のひとつとなります。測定部位で一番変化がわかりやすい箇所は、耳の根本あたりといわれています。

チンチラ <よだれ>
チンチラには歯の病気が多くみられます。歯の伸びすぎだけではなく、歯周病なども多いです。その際に、口の中の痛みや炎症がある場合には、口周りによだれが見られることがあります。口周りが汚れていなくても、足で口のよだれを拭くことで炎症が起こり、前足の脱毛などが見られることもあります。また、歯の異常に伴って食欲が低下します。

ハムスター <脱水>
ハムスターの毛がゴワゴワしていてぐったりしているなどの症状があるときには、脱水を代表とする全身状態の悪化による変化かもしれません。脱水とともに、眼の周辺の目やにや赤み、くぼみなどの変化がでることも多く、眼の症状を主訴に来院したものの実は全身状態が悪かったということも少なくありません。

フェレット <よだれ・ぐったり・後ろ足の麻痺>
フェレットがよだれを流してぐったりしている、小刻みな震えがある、後ろ足の動きが悪い、這うように移動しているなどの症状がある場合には、低血糖状態になっている可能性があります。低血糖の原因として、膵臓の腫瘍であるインスリノーマが一番多いです。
これらの症状がみられたときに、ブトウ糖液を与えてその後すぐに症状が改善する場合は、低血糖状態である可能性が強くなります。

デグー <呼吸が速い・腹部が膨らんでいる>
デグーの呼吸が速い場合には、肺炎など肺の問題のほか、歯の根本にトラブルが起こり鼻の通り道を圧迫していたり、鼻の通り道にできもの(腫瘍)ができていたり、もしくは心臓の病気などが原因となっていることがあります。その場合は、無理に抱っこをしてストレスをかけたり、過度に保温したりすると病状が悪化することがあるので注意が必要です。呼吸が荒すぎるせいで空気を飲み込み、お腹にガスがたまって膨らんでいることもあります。

ハリネズミ <食べづらさ>
硬いものを食べなくなったなど、食欲低下やよだれが見られた場合には、歯周病や口の中にできもの(腫瘍)があることがあります。すぐに体を丸めてしまうハリネズミでは口の異常に気づくことはなかなか難しいのですが、早期発見であるほど治癒率が高くなります。そのため、動物病院で鎮静処置を行いながら口の中の確認・検査をする必要があります。

動物病院に連れて行くまでにしたほうが良いこと
よく保温などが推奨されていますが、呼吸器や心臓の病気、脳神経の病気による発作がある場合は過度な保温は推奨されません。まずはすぐに動物病院に連絡をして状態を伝え、状況に合わせた適切な対処をしたうえで受診することをおすすめします。
また、症状がいつからでているのかなどを簡単にメモしておくと、動物病院で状態を伝えやすくなります。もし発作や行動の異常がある場合には、動画を撮っておくと良いでしょう。
日頃からの準備・予防
かかりつけの動物病院を見つけよう
まずは、かかりつけ医を決めましょう。特に問題がなくても、健康診断に行くことで病気の予兆を察知できるだけでなく、その子の正常な状態を記録しておくことができます。
たとえば、草食動物であれば定期的に口の中を検査することで歯の病気を早期発見することができます。
家の環境づくり
小型哺乳類は、特に不適切な飼育環境が原因の不調が多い傾向にあります。そのため、その子の本来の生態にあった環境づくりと観察が重要となります。
たとえば、ウサギの床材の金網などは清潔を保ちやすいなどのメリットがありますが、犬や猫と異なり、足の裏に肉球がないウサギにとっては刺激が強く、足の皮膚がむけてしまう「足底皮膚炎」という病気が起こるデメリットがあります。
飲料水はボトルで与えるよりも水皿を用意したほうが、摂取量が増えるという研究結果も出ています。
また、ほとんどの小型哺乳類は温度と湿度の管理が重要になるので、温度計と湿度計をその子が生活している場所に配置したほうが良いでしょう。
おわりに
それぞれの動物種に合った生活環境をつくってよく観察を行い、小さな体調の変化を見逃さないことが重要です。
しかし、小型哺乳類の飼育に関してはしっかりとした情報が少ないことから、悩まれる飼い主さんも多いと思います。我々獣医師の仕事は病気を治すだけではなく、病気にさせないための予防医療も重要な任務です。飼育についてもし困ったことがあれば、気兼ねなく相談してもらえると嬉しいです。
【執筆者】
村上彬祥(むらかみ・あきよし)
獣医師。大相模動物クリニック/東埼玉犬猫エキゾチックアニマル総合診療科(埼玉県越谷市) 院長。日本大学生物資源科学部獣医学科出身。北里大学および中央動物専門学校非常勤講師。日本獣医エキゾチック動物学会、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会(技能講習試験修了獣医師)に役員として所属する他、鳥類臨床研究会理事を務める。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!