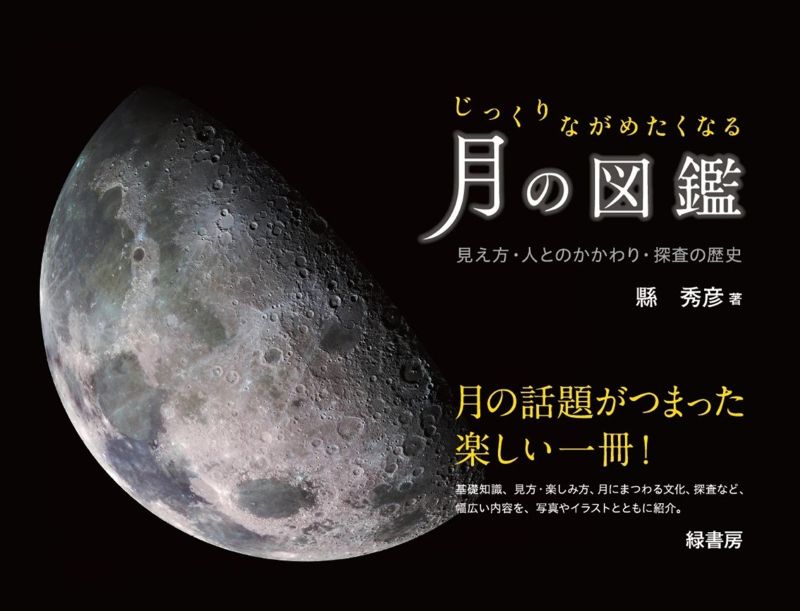ウサギやフェレットなどの小型哺乳類をケージの外に出して部屋の中を散歩させる「部屋ん歩(へやんぽ)」。
ケージから出て部屋でのびのびと遊ぶ姿は見ていてたいへん愛くるしいですし、飼い主になでられたり抱っこされたりすることで、飼い主とのコミュニケーションの機会にもなります。
ただし、すべての小型哺乳類で部屋ん歩が必要というわけではありません。
動物の種類や特徴、性格、安全な環境を提供できるかどうかを検討したうえで、部屋ん歩をさせるかどうかを決めることが大切です。
今回は、そんな小型哺乳類の部屋ん歩について解説します。
部屋ん歩のメリット・デメリット
メリット
・運動不足の解消:広いスペースを歩き回ったり、おもちゃで遊んだりすることで運動量が増加し、運動不足の解消になります。
・ストレス発散:体を動かしたり、興味のあるもののニオイを嗅いだりすることで、ストレスを発散できます。
・健康状態の把握:歩き方がいつもと異なる、普段ならすぐケージから出てくるのに出てこないなど、いつもと違うところに気づきやすくなります。また、なでたり抱っこしたりすることで、毛づやや体の変化にも気づきやすくなります。
・飼い主とのコミュニケーションの機会:おもちゃで遊んであげたり、おやつを与えたりすることで、ペットと良いコミュニケーションを取ることができます。

デメリット
・誤飲:ペットが届くところに置いてあるものや、家の柱の角や家具、植物などを食べる・かじる事故が起こりやすくなります。かじられて困るものは、ペットが届かない場所にしまいましょう。ペットがかじってしまいそうな部屋の壁の角や家具などは、カーペットを巻いたり、L字型カバーなどを取り付けたりしてガードしましょう。

・ケガ:ソファなどの高いところからの落下や、足元にじゃれてきたペットを飼い主が蹴ってしまう、ブランケットやクッションの下に潜り込んでいることに気づかずに、上から座ってしまう、といった事故が起きています。部屋ん歩中は、絶対にペットから目を離さないようにしてください。
・感電:電源ケーブルを噛んでしまうことで感電してしまうことがあります。ケーブルは家具などの裏に隠すか、保護チューブなどでカバーしましょう。
・逸走:ドアが開いた瞬間に部屋の外に出てしまったり、開けていた窓から外に出てしまう逸走も起こりやすいので注意してください。また、家具の隙間に入り込んで出られなくなるケースもあります。入りこんでしまいそうな隙間はふさいでおくことをおすすめします。
部屋ん歩をさせるときの注意点
ペットから目を離さず、常に様子を見守るようにしましょう。
ツルツルしたフローリングは滑りやすく、足腰を痛める可能性があります。ペットが歩く場所は、ジョイントマットやカーペットを敷いてあげると良いでしょう。

ペットが自由に部屋ん歩できるスペースをサークルなどで囲い、その中で自由に過ごさせてあげましょう。部屋全体を開放するときは、コンセントやコード類が多い場所や、ペットが入り込んで出てこられなくなりそうな場所に近づけないように、家具でふさいだりサークルで囲ったりして工夫します。

同居家族が部屋のドアを開けた隙にペットが部屋の外に出てしまうこともあります。ペットが部屋ん歩中であることを同居家族にも伝えて、うっかり逸走してしまうことのないように注意してください。
ゴミ箱を倒したりゴミをあさったりできないように、ゴミ箱はフタつきで倒されないような重いものにするか、ペットが届かない場所に置くようにしましょう。
ペットにとって有害な観葉植物も多いです。動物種によって毒性があるかどうかは異なり、すべてが解明されているわけではありません。自分が飼っているペットにとって安全だとわかっているもの以外は片付けるようにしましょう。農薬を使っている植物はペットが届くところに置かないようにしてください。
頻度や時間
動物種や個体によっても異なりますが、部屋ん歩の頻度と時間は、だいたい1日に1回、15分~2時間程度が目安です。
最初は短時間・狭いスペースから慣れさせて、ペットの様子を見ながら徐々に部屋ん歩の時間を延ばし、遊べるスペースを広げていくようにしましょう。

おわりに
ペットの運動不足の解消やストレス発散、飼い主とのコミュニケーションの機会として、部屋ん歩は最適です。
しかし、ペットのための環境が整っていない状態で部屋ん歩をはじめると、悲しい事故につながりかねません。
部屋ん歩を行うときは、ご自身のペットに部屋ん歩が必要かどうかを今一度検討し、安全に部屋ん歩ができる環境を整えてから行うようにしてください。
日本愛玩動物協会では、一般市民向けの無料公開シンポジウムを定期的に開催しています。2025年11月29日に、千葉県で「ペットと高齢者等の福祉」をテーマに開催予定です。
詳しくはこちらまで!
https://www.jpc.or.jp/seminor/
【執筆】
公益社団法人日本愛玩動物協会
1982年に設立した、ペットの動物愛護と適正飼養の普及啓発を行うことを目的に活動する公益法人。
愛玩動物飼養管理士の養成事業のほか、ペットオーナー検定、ペット共生住宅管理士の検定事業などの実施を通じて、ペットに関する法令や正しい飼い方などの普及啓発を行う。また、一般市民向けの無料公開シンポジウムも定期的に開催しており、「飼い主とペットのための災害対策指導者研修会」の実施や、小学校でのふれあい活動など、人とペットが幸せに暮らす社会の構築のために、新規事業を展開している。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!