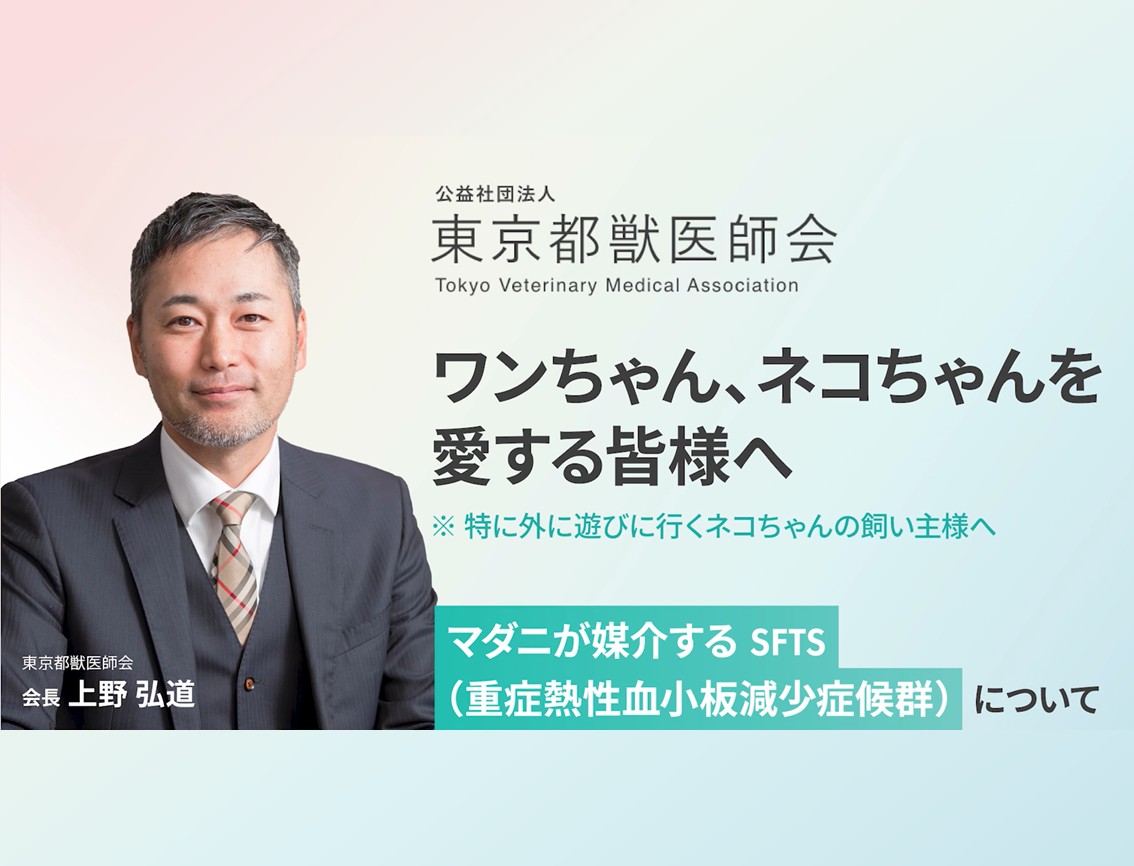はじめに
猫がゴロゴロ(purr)と鳴くことはとても有名であり、犬から発せられることはない、猫の大きな特徴の一つです。「鳴く」と書きましたが、このゴロゴロ音は喉鳴りであり、猫が発する鳴き声の「ニャー(ミャオ / meow)」とは異なります。実は、猫同士ではニャーと鳴くことはあまりなく、人に対して特化させた鳴き声のようです。
謎が多いいきものである猫ですが、このゴロゴロは科学的にも不明瞭なことが多く、研究者も首を捻っているようです。今回は、このゴロゴロについて迫っていきたいと思います。
猫のゴロゴロとは
猫は、数種類の鳴音を場面や状況に応じて発しているといわれています。ニャーも非常によく知られた鳴き声ですが、攻撃の際にはグルルル(Growl)と唸るような鳴音を発声することもあります。
猫のゴロゴロの基本周波数は、25~30ヘルツと低い音です。咽頭の筋肉を収縮しながら声帯を振動させることで発生させており(実はこの発声メカニズムも十分な解析には至っていません)、息を吸うときや他の鳴き声と同時に発することもできます。生後すぐ~2日齢にはゴロゴロと鳴き、母猫も子猫に近づく際にはゴロゴロと喉を鳴らします。ゴロゴロの振動がお互いに伝わるので、母子間のコミュニケーションに用いられていると考えられます。成長するにしたがって、ゴロゴロは別の意味をもつようになっていきます。
一般的に、ゴロゴロは心地良いときや、要求時などの様々な状況でよく聞かれるように思われますが、鳴らす理由やその役割は明確には判明していません。ゴロゴロは、人や他の猫との接触時、眠いとき、怪我をしたときなど、心地良い状況とは相反する恐怖やストレスを感じる場面でも発せられます。このことから、ゴロゴロは猫の感情を伝える複雑な表現方法といえるかもしれません。人が嬉しいときや幸せなとき、怒ったとき、なにか欲しいときにも微笑するように、猫たちのゴロゴロは人の微笑みに相当するのではないかとも称されています。

猫はなぜゴロゴロと喉を鳴らすのか
ゴロゴロは、リラックスしているときや子猫が母猫からミルクをもらっているとき、また成猫同士が体を寄せ合う場面でよく耳にします。そして、人に対しても同様に、ふれ合っているときに発されます。これは、体同士の接触による刺激とリラックス感を伴うゴロゴロといえるでしょう。
一方で、食べ物などを猫が要求する際にもゴロゴロは発せられます。この要求時のゴロゴロは、人によっては不快に感じ、急かされていると感じるようです。2009年、Karen McCombらサセックス大学の研究グループは、心地良いときのゴロゴロとは異なる「要求のゴロゴロ」があることを発見しました*¹。この要求のゴロゴロには、220~520ヘルツ(平均380ヘルツ)の高い周波数が含まれているそうです。大人が乳児の泣き声に緊急性を感じるような類似点があるようです。本来低い音程のゴロゴロの中にある高い音が、猫が餌を要求する際には強調され、人が過敏に反応してしまうゴロゴロ音になると考えられています。
さらには、地位の低い猫や病気の猫は、地位の高い個体が近づくと喉を鳴らすことがあります。ゴロゴロは、個体間の無用な衝突を避ける役割を果たしている可能性もあるようです。
このように、猫の喉を鳴らすという行為は、接近・接触といった親睦や要求、衝突回避など、多様な役割があると考えられています。
ゴロゴロがもたらす人への影響
猫は、痛みを感じる場合にもゴロゴロと発します。直接的な実証はされていないものの、カリフォルニア大学デイビス校のLeslie A. Lyonsは、ゴロゴロが骨に含まれる骨芽細胞や破骨細胞を活性化させ、骨密度の維持に役立っているのではないか、という猫の自己治癒能力について仮説を立てています*²。これは、猫のゴロゴロが発する低周波によって骨が圧力を受けて硬くなり、骨の成長と骨折の治癒を促進する可能性があるというものですが、未だ仮説の域を出ていません。
しかし、この周波数帯は、人の体にも恩恵をもたらす可能性があります。ウサギでの実験ですが、骨折に対して機械的振動を与えると治癒の促進が認められ、骨の強度は20~30パーセント程度上昇したようです。このときの、最適な周波数は25~100ヘルツであり、猫のゴロゴロの周波数はこの範囲内です。
近年、医療分野では様々な疾患に対する長期的な治療法の一つとして、振動療法(Vibrational therapy)が用いられることもあるようです。振動の刺激が、筋肉の張りを抑える効果を持つことが報告されています。患部や全身の筋肉に、疲労しない程度の振動を与えることがトレーニングとして有効だと考えられています。実際に、骨の増強(構造・骨密度)や、脳性麻痺による歩行能力低下に対する予防・治療法などにも活用されているようです。
また、音楽療法には、ボディソニックシステムという音楽の重低音やリズムなどを体で感じとることで、音と振動による効果を期待した療法的なアプローチがあります。
こうした音と振動刺激を利用したリラクゼーションを考慮してみると、猫のゴロゴロの音刺激が人に対してリラクゼーション的な効果を与えることも、あり得る話ではないでしょうか。
このように、猫のゴロゴロは人の健康に効果があるのではないかと推察されているのですが、直接的な証明はほとんどされてはいません。最近では、猫のゴロゴロ音は心拍数を減少させてリラックス効果をもたらすことや、ゴロゴロの低周波にリラックス効果があるということを示唆した報告も出てきました。社会的には「ゴロゴロセラピー」としてメディアにも取り上げられたこともあり、ゴロゴロ音が入ったCDが販売されるといった事例もあります。
確かに、猫の飼育やふれ合いによって、ストレスの低減や心血管疾患による死亡リスクが低くなることは多く報告されています。猫を抱いていれば、ゴロゴロは音と振動で私達に伝わってきますし、猫が膝の上などで安心してゴロゴロ鳴くと、私達もリラックスできることは経験的にも知られていることでしょう。

京都大学は、「アンドロゲン受容体遺伝子(AR遺伝子)」という男性ホルモンの働きを調整する遺伝子と猫の喉を鳴らす行動との関連性について、最新の報告をしています*³。この遺伝子の長さが短い場合、「よく喉を鳴らす」「人に対してよく鳴く」といった行動特性が認められました。特にオスではこれが顕著に見られ、人とのコミュニケーションに積極的である可能性が考えられました。短いタイプの遺伝子を持つメスは、見知らぬ人へよく攻撃することも明らかになり、猫の遺伝子とゴロゴロの発し方といった行動特性との関連性が示されました。
また、ストレスを感じて発しているであろう診察中のゴロゴロは、多くの獣医師にとって、聴診器を当てて診断するときに心雑音などをかき消してしまう厄介なものです。このとき、水が流れる蛇口に近づけると81パーセントの猫がゴロゴロを止めたそうです*⁴。
おわりに
猫のゴロゴロ研究では、このような面白い報告が多くあります。ゴロゴロと猫の性格・遺伝子・人や他の猫への影響と効果など……。研究者を悩ませる猫のゴロゴロは、未だ謎に満ちた不思議な行動なのです。猫のゴロゴロにはどんな役割があるのか、またこのゴロゴロを通して私達に何を伝えているのか、ますます興味深いところです。
[参考]
*¹ Karen McComb et al, “The cry embedded within the purr”, Current Biology, 19, 13, 507-508, 2009.
*² https://www.scientificamerican.com/article/why-do-cats-purr/
*³ Yume Okamoto, Madoka Hattori, Miho Inoue-Murayama, “Association between androgen receptor gene and behavioral traits in cats (Felis catus)”, PLOS One, 2025.
*⁴ Little CJ, Ferasin L, Ferasin H, Holmes MA, “Purring in cats during auscultation: how common is it, and can we stop it?”, J Small Anim Pract, Jan, 55(1), 33-8, 2014.
【執筆者】
内山秀彦(うちやま・ひでひこ)
1978年生まれ。博士(学術)、東京農業大学 農学部動物科学科 教授、ヒトと動物の関係学会 常任理事・事務局長。麻布大学卒業、同大学動物応用科学専攻修了。東京農業大学農学部バイオセラピー学科を経て今に至る。主な専門分野は、動物行動学、ヒトと動物の関係学。これら専門分野に係る学術論文および著書を執筆・監修。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!