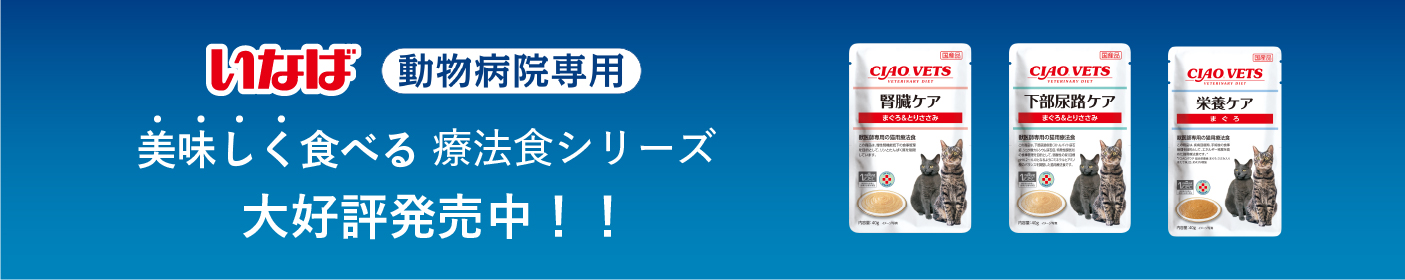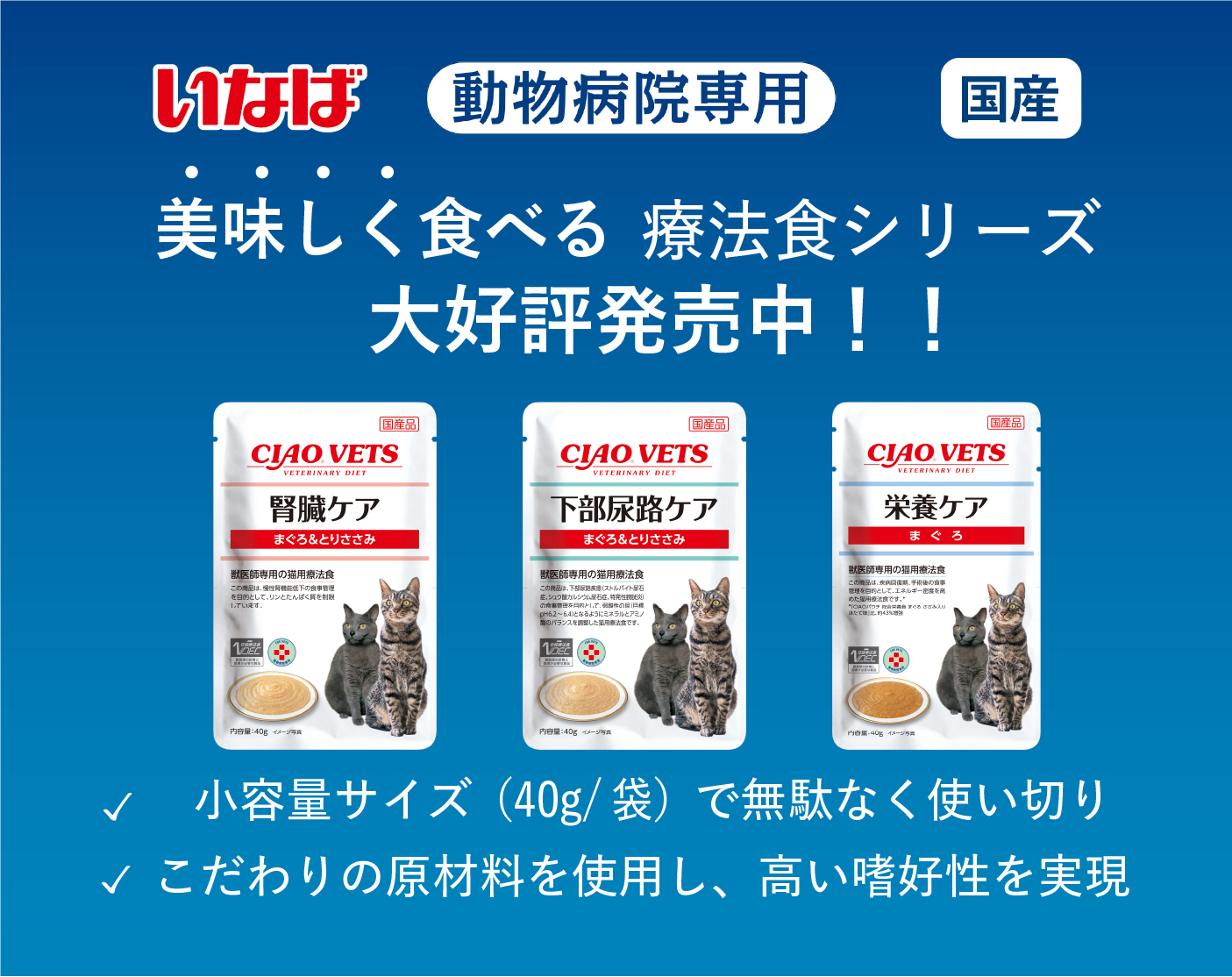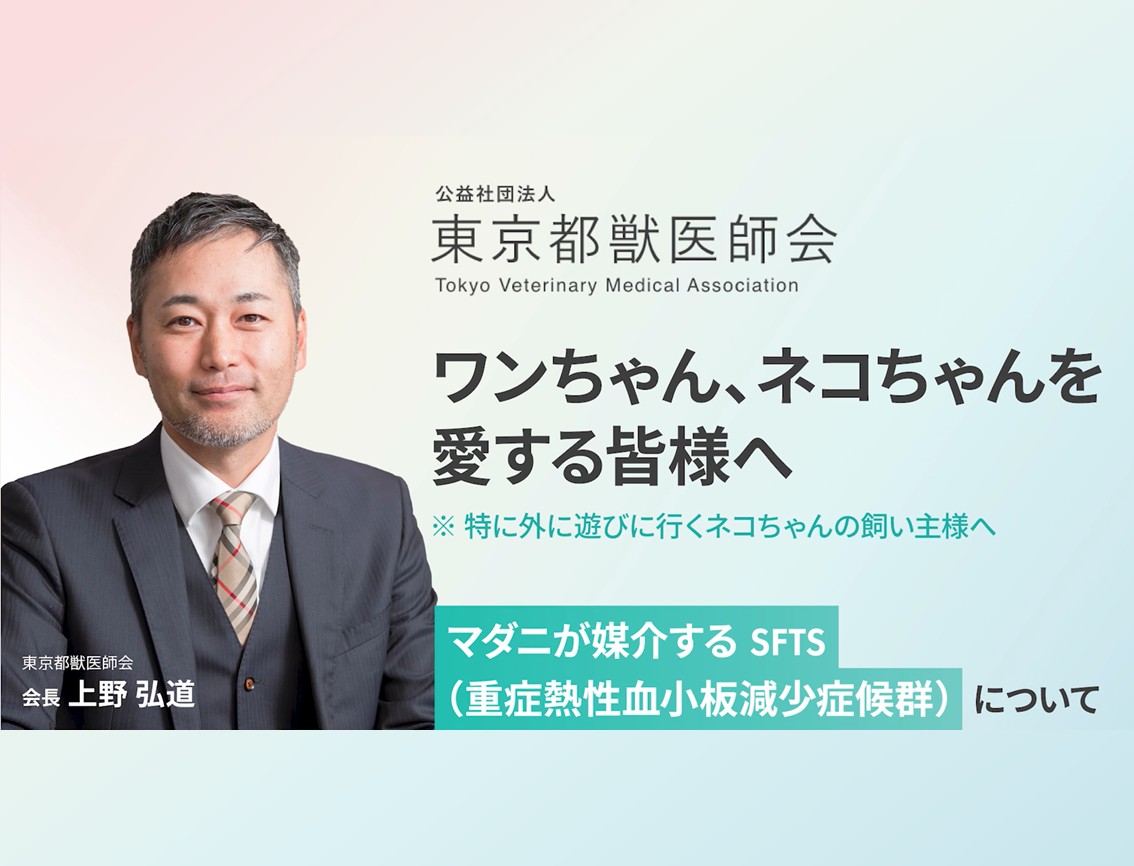暑い夏がやってくると、私たち人間だけではなく、愛猫たちも体調を崩しやすくなります。特に、「熱中症」は命にかかわる危険な状態です。猫は見た目では体調の変化が分かりにくく、異変に気づいたときにはすでに重症化していることもあります。
今回は、猫の暑さ耐性から夏に起こりやすい健康障害、予防策、万が一の対処法まで、獣医師の視点から分かりやすく紹介します。
猫は暑さに弱い?
猫は砂漠地帯をルーツに持つ動物なので、人や犬よりも暑さに強い動物です。それでも、近年の温暖化に伴う高温多湿な日本の夏は、猫にも危険な暑さです。猫の平熱はおよそ38〜39度と人間よりも高く、体温調節のメカニズムが異なります。人間のように全身に汗腺があるわけではなく、汗をかけるのは肉球のみです。その代わりに、猫はグルーミングで唾液を体に塗り、それが蒸発することで気化熱を利用して体温を下げています。
とはいえ、猫は全身が被毛に覆われているため熱がこもりやすく、効率よく排熱することが苦手です。特に長毛種や肥満気味の猫は体内の熱が逃げにくく、熱中症のリスクが高まります。

夏に起こりやすい健康障害
猫が夏にかかりやすい代表的な健康障害には以下のようなものがあります。
熱中症
高温多湿の環境や風通しの悪い室内、直射日光の当たる場所に長時間滞在することで発症します。熱中症になると、猫自身で体温を下げることができなくなることで体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体の調整機能が壊れたりしてしまいます。重症例では死にいたる怖い病気です。
症状:体温が高い(40度以上)、呼吸が荒い、ぐったりしている、よだれが出る、嘔吐、意識がもうろうとしている、場合によっては痙攣や昏睡状態になることもあります。
脱水症状
水分摂取量の不足や下痢・嘔吐などで過剰に水分が失われることで起こります。猫は脱水症状に鈍感であるため、多少脱水していても水を飲まないことが多いです。
症状:皮膚をつまんでもすぐに戻らない、食欲不振、嘔吐、尿量の減少、目が落ちくぼむなどです。
食欲不振・胃腸のトラブル
人と同じように、猫も夏バテをすることがあります。夏の暑さで元気がなくなり、食欲が低下します。ただし、冷房による温度差で体調が悪くなることもあるので、設定温度を低くしすぎることにも注意が必要です。
猫の夏バテ・熱中症を防ぐ5つのポイント
夏の健康障害を防ぐためには、飼い主の工夫が欠かせません。
室温管理
エアコンや扇風機を使用して、室温を25〜28度程度に保ちましょう。特に、留守中は温度設定に注意が必要で、体が冷えすぎたときに入れるダンボールやベッドがあると安心です。
また、夏の車の中は高温になるので、たとえ短い時間であっても絶対に猫を車内に放置しないようにしましょう。移動中は、ペット用冷却マットや携帯用の冷風機を利用するのも一つの方法です。
湿度管理
部屋の中の湿度が高いと体温をうまく下げられなくなります。エアコンのドライ機能や除湿機を使って湿度を下げると良いでしょう。
日除け対策
直射日光が当たる窓にはカーテンやブラインドを取り付けましょう。猫のベッドは、日陰への設置をおすすめします。
風通しの確保
換気や空気の流れを意識して家具の配置を工夫しましょう。扇風機やサーキュレーターを使うことも検討してください。
水分補給
新鮮な水を室内の複数箇所に置きましょう。中には水をあまり飲まない猫もいるため、鶏肉の茹で汁など風味や香りがついた水をあげてもよいでしょう。とろみがついたペット用の飲料水を与えたり、普段の食事にウェットフードを取り入れたりすることも効果的です。

食欲不振
冷蔵庫から出したてのウェットフードは、冷たすぎて猫の好みに合わないことがあります。与える前に常温に戻すか、匂いが立つように電子レンジで軽く温めるなどの工夫をしてみましょう。ただし、夏場はウェットフードが痛みやすいため、長い間置きっぱなしにしないようにしてください。
万が一熱中症になってしまったら
愛猫に上記のような熱中症の症状が見られた場合は、すぐに次のような応急処置をして動物病院へ連絡してください。
応急処置
・涼しい場所に移動させる
・濡れタオルで体を包んだり、首や脇、内ももを冷やす
・水を少しずつ与える(意識がある場合のみ)
※氷水などで急激に冷やすと逆効果になることがあるので注意が必要です
獣医師による処置
・点滴や酸素吸入などによる体温の安定化
・血液検査による臓器ダメージの確認
・重症の場合は入院治療
まとめ
猫にとって、日本の夏は決して過ごしやすい季節ではありません。熱中症や脱水など、命に関わる健康障害のリスクがあるため、日々の予防と観察が非常に大切です。愛猫の健康を守るためには、飼い主の気配りと知識が何よりの武器になります。普段から室温管理や水分補給に気を配り、少しでも異常を感じたら早めに獣医師へ相談しましょう。
【執筆者】
服部 幸(はっとり・ゆき)
1979年生まれ。北里大学獣医学部卒業後、2年半の動物病院勤務を経て2005年にSyuSyu CAT Clinic院長を務める。2012年、江東区に東京猫医療センター( https://tokyofmc.jp/ )を開院、院長として猫の専門医療にかかわりつづける。2014年にねこ医学会(JSFM)理事に就任(現副会長)。『ネコにウケる飼い方』(ワニブックス)、『イラストでわかる! ネコ学大図鑑 』(宝島社)、『猫を極める本 猫の解剖から猫にやさしい病院づくりまで』(インターズー)など著書多数。
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!