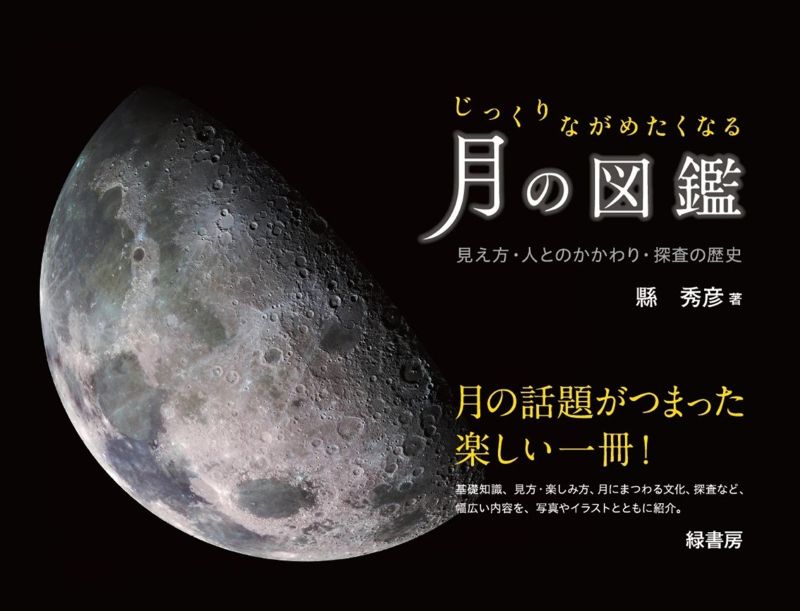アマミノクロウサギとは?
アマミノクロウサギは、奄美大島と徳之島にのみ生息しています。ウサギ科の仲間ですが、ウサギにしては短い後肢と耳を持ち、全身は暗褐色の毛で覆われています。これらの特徴は、肉食哺乳類が島にいなかったため、逃げるための長い後肢や放熱器官としての長い耳を必要としなかったのではないかといわれています。大陸のアマミノクロウサギ属は絶滅したため、現在アマミノクロウサギ属は1属1種となっています。

このように、奄美大島や徳之島には大陸の近縁種が絶滅してしまった「遺存固有種」や、大陸と別れてから生まれた「新固有種」が生息しています。
開発や外来種の影響で絶滅危惧種に分類されていますが、外来種であるフイリマングースやノネコの対策が進み、個体数や生息地が回復してきています。
観察してみよう
アマミノクロウサギは夜行性で、昼間は森の中に掘られた巣穴で休んでおり、暗くなると活動を始めます。行動範囲は1ヘクタール(100×100メートル)程度といわれていて非常に狭いですが、開けた場所で草を食べたり糞をしたりする習性があるため、道路にもよく出てきます。

昼のうちに、林道などでつやつやした新しい糞を確認しておき、夜にその場所へ観察に行くと出会える可能性が上がります。
アマミノクロウサギは音に敏感なので、できるだけ早く見つけて距離を保って観察することがコツです。見つけたらその場で立ち止まり、静かにしていると長く観察することができます。
奄美大島や徳之島には毒をもったハブが生息しているので、特に雨が降った夜は、足元を照らすライトを忘れずに持参しましょう。野生動物は、私たちが思ったように現れてくれるとは限りません。気長に根気よく探すことが重要です。

観察における注意点とマナー
強いライトを当てると、驚いて逃げてしまうことがあります。動物のストレスになることもあるので、見つけた後は強いライトを当てずに観察しましょう。
野生動物は、病気を持っていることがあります。また、私たちの病気をうつしてしまうこともあります。アマミノクロウサギも例外ではありません。直接触ったり、近づきすぎたり追いかけたりしないように注意しましょう。
動物を探しながら運転することは慣れていないと難しく、観察に夢中になって事故を起こしてしまうこともあります。また、飛び出してきた動物や見えにくいカエルなどを轢いてしまう危険もあります。初めてのナイトツアーは、エコツアーガイドと一緒に行くことをおすすめします。ガイドさんに案内してもらうことで、アマミノクロウサギはもちろん、ほかの動植物についての知識も深めることができます。

もしご自身で運転して観察に行く場合は、アマミノクロウサギだけでなく、ネズミやカエル類、ヘビなどにも注意して、通行してください。注意するポイントは以下の3つです。
① 事故の多い場所には看板や減速帯があります。そのような場所ではすぐに止まれる速度で通行しましょう。
② 対向車がいないときはハイビームにしておきましょう。ハイビームにしていると、より早く動物を見つけることができます。
③ 茂みや水たまりがある場所は動物が近くにいる可能性があります。飛び出してくることもありますし、見えていても思わぬ方向に逃げる場合があります。「かもしれない」運転を心がけましょう。

私たちがアマミノクロウサギの生息地に入る際に外来種を持ち込んでしまうと、生息地の環境を変えてしまう可能性があります。山に行くときは、服に種などがついていないか確認し、靴やタイヤの泥を落としてから行くようにしましょう。
観察におススメの時期やスポット
奄美大島も徳之島も、アマミノクロウサギを観察するナイトツアーが盛んにおこなわれています。特に安全で動物にも配慮して観察できる場所が、奄美市の三太郎線と徳之島町の林道山クビリ線です。三太郎線では、2021年から予約制での台数制限や観察ルールを決めることで、野生動物に影響の少ないツアーの実施を進めています。また、林道山クビリ線は奄美群島エコツーリズム推進協議会認定ガイドのツアーでしか入ることができないため、動物に対して影響が少ないだけでなく、質の高い体験ができます。

三太郎線の利用調整
山クビリ線の利用調整
また、どちらの路線もアマミノクロウサギだけでなく、それぞれの島の固有種のカエルや鳥なども観察できるチャンスがあります。アマミノクロウサギは年中観察できますが、カエルや鳥などは季節によって見やすい種が異なるため、それぞれの季節で楽しむことができます。

おわりに
奄美大島と徳之島では、アマミノクロウサギをはじめとした野生動物の交通事故が増えています。要因の一つに、外来種対策によって在来種たちの生息数が増加したことがあげられますが、世界自然遺産の島なので、将来に向けて遺産の価値を守っていく必要があります。
交通事故は、これまで目撃が少なかった大きな道路でも発生するようになっています。観察中だけでなく、観察に行く途中や帰り道、それ以外の場面でも、夜間の移動の際は上記の3つの注意点(減速、ハイビーム、かもしれない運転)を思い出してもらえるとうれしいです。
奄美大島や徳之島に観光に来られる際は、予定をぎっちり入れるのではなく、ゆとりのあるスケジュールを組むことをおすすめします。野生動物も、人間ものんびりと生活している島です。どちらにも優しい行動ができると、よりたくさんの素敵な出会いがあること間違いなしです!
【文・写真】
奄美野生生物保護センター
奄美群島の希少な野生生物に関する調査・研究、外来種の防除事業、国立公園の管理、センターでの展示や自然観察会などを通じた普及啓発、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産の価値の保全などを総合的に行う拠点。
〒894-3104 鹿児島県大島郡大和村思勝551
公式サイト:https://kyushu.env.go.jp/okinawa/awcc/index.html
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!