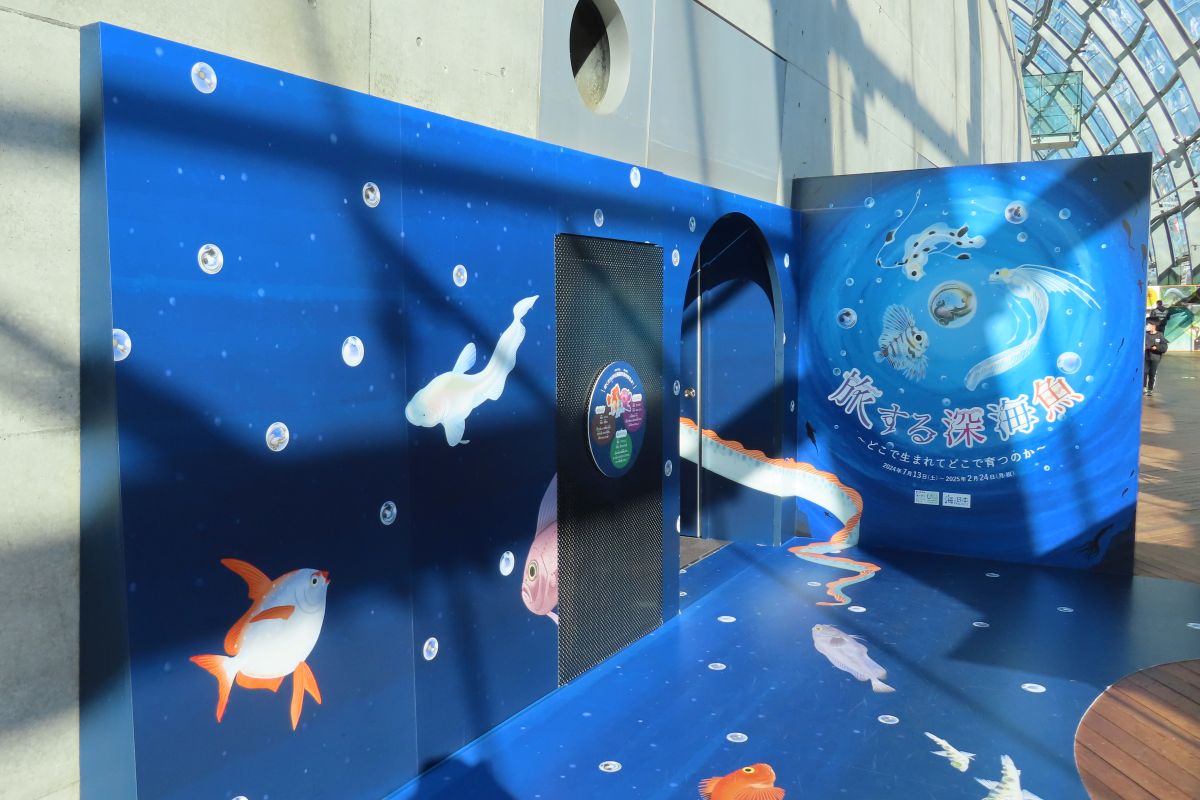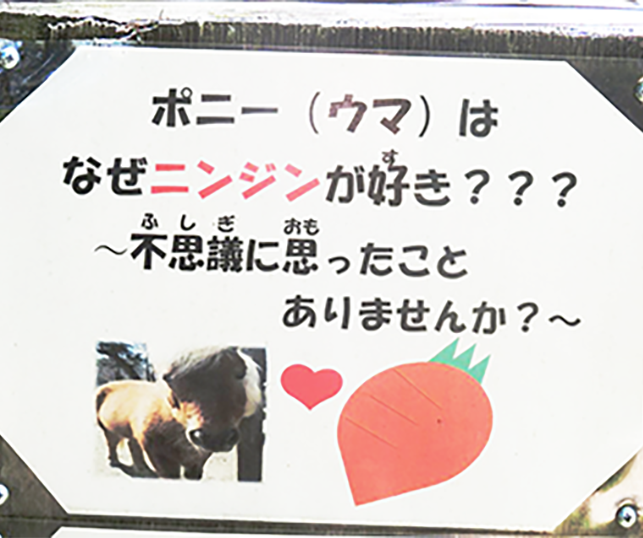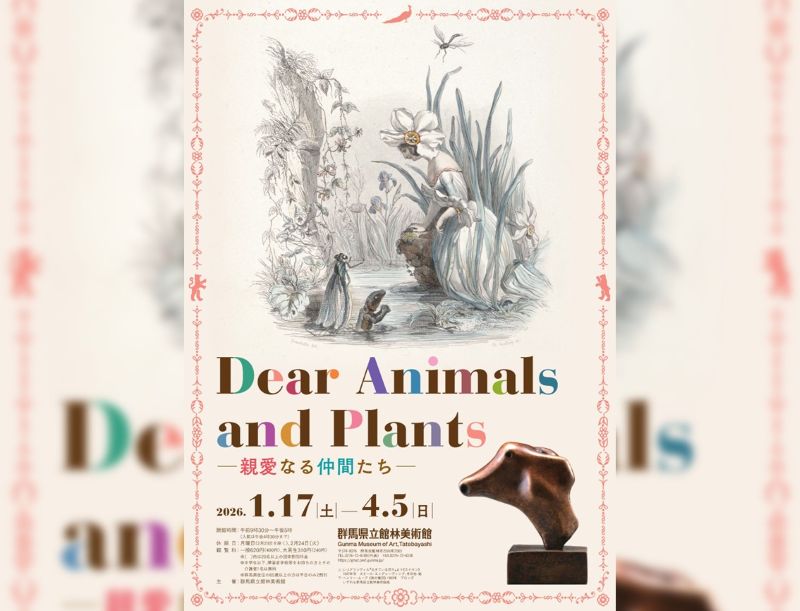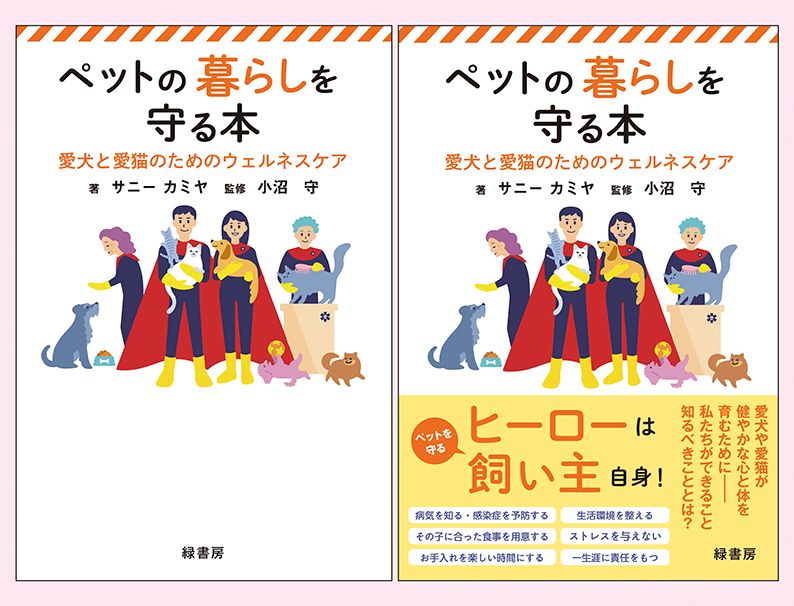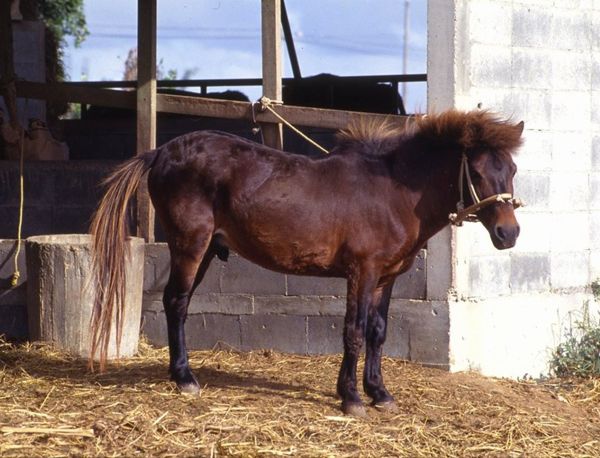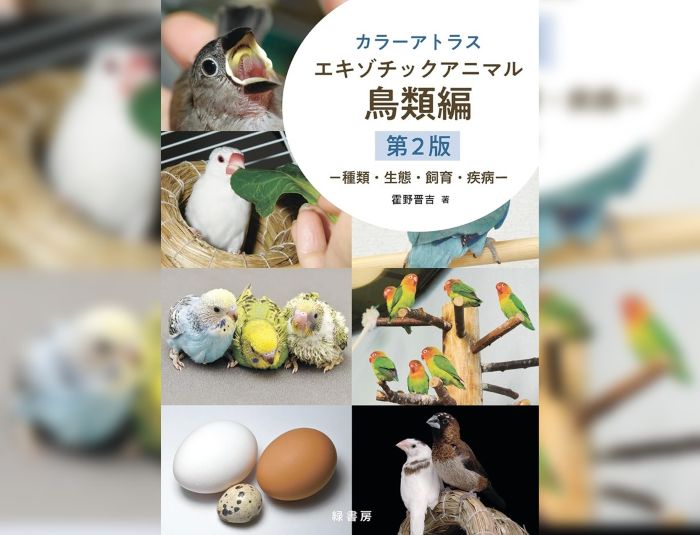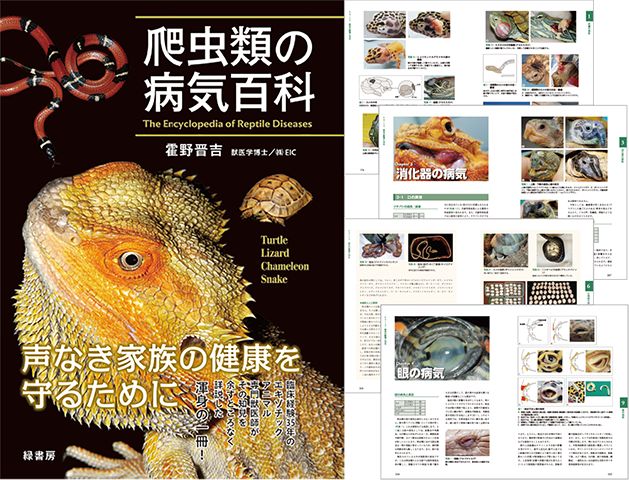鼻先からの丸みを帯びつつもすっきりとしたライン、まっすぐなまなざしを宿した目。この写真だけで、その美形ぶりを納得していただけるでしょう。

彼は、2024年7月にシンガポールから来日したコモドオオトカゲのオスの「タロウ」です。シンガポールから来たのになぜ日本名なのかと思うかもしれませんが、タロウの母親のヨーコはもともと上野動物園で飼育されていました。(ヨーコは、1994年8月18日にアメリカのワシントン国立動物園で生まれました)、2008年に繁殖を目的としてシンガポール動物園へ貸し出され、2011年にタロウが誕生しました*¹。今回、国内での調整の結果、受け入れの意志に加えて施設・設備の面も考慮され、東山動植物園が飼育展示を行うこととなりました。


*¹ 2025年6月に行われた、来日後初めての誕生祝いの様子はこちらです(丸鶏や解凍済の冷凍マウスなどが登場します。ご注意ください)
【東山動植物園公式】6/2はタロウの誕生日!スペシャルメニューをあげました
ひととき瞼を閉じて何を想っているのでしょうか。わたしたちがトカゲに感情移入をしてしまうのは、こんなちょっとした共通点をきっかけにしてのことかもしれません*²。

*² ヤモリもヘビも大きくはトカゲのなかま(有鱗目)ですが、それらには瞼はなく、代わりに透明な鱗が眼球を覆って保護しています。つまり、コモドオオトカゲを含む他のトカゲ類のように目を閉じることはありません
一方で、トカゲやヘビならではの先が割れた舌。これらの動物は、空気中に漂う物質を舌で捉えて、上顎にあるヤコブソン器官という部位でそれを感知します(ヤコブソン器官はほ乳類にもしばしば見られます)。空気中の物質の感知という意味では、一種の嗅覚と見なすことができるでしょう。先ほどご紹介した誕生祝いの動画でも、タロウは盛んに舌を出し入れしています。きっと、段ボールの中に仕込まれた餌のにおいを感知しているのでしょう。コモドオオトカゲは、生息地であるインドネシアのコモド島などでは、シカやイノシシ、スイギュウなどの大型哺乳類まで食べてしまう、食物連鎖のトップの捕食者です。数キロメートル先のにおいまで感知するという舌の機能は、狩りの中で大きな役割を果たしていると考えられます*³。

*³ コモドオオトカゲは視力も優れており、300メートルほど先のものも認識できるといわれています。
東山動植物園では、そんなタロウの能力を踏まえて「環境エンリッチメント」を行っています*⁴。
【東山動植物園公式】タロウに2つのエンリッチメントをしてみました
タロウの飼育展示場と観覧路を挟んだはす向かいのボルネオテナガザルが、「遊具」として利用して、そのにおいがついていると考えられるボールをタロウのところに入れてみたのです。タロウは盛んに舌を出し入れし、ボールに触れて噛みつこうとしました。このような噛みつきの行動は、普段は食べものに対してしか発生しません。ボールについた他の動物のにおいを感じ取り、狩りの欲求に反応したのではないかと考えられます。これは、飼育下の生活に良い刺激をもたらしているであろうと思われ、動物福祉にかなうものとして評価されます。


*⁴ 動物福祉の観点から、飼育動物の環境をより豊かにすることを目指したさまざまな施策のことです。そこでは、それぞれの動物種の生態や能力が重視されます。
動画では、ボールのほかに山状に積んだヤシ殻のチップも用意され、タロウは盛んに突き崩しています。ヤシ殻を食べることはありませんが、こちらでも舌を出す様子が観察できます。
なお、誕生祝いの際の試みも、採食にまつわる環境エンリッチメントとしての意義を持っていることになります。
コモドオオトカゲは、歯と歯の間から毒を分泌することが知られています。ヘビ類を除けば、トカゲのなかまで毒を持つものはごくわずかですが、コモドオオトカゲはこの毒を狩りに役立てていると考えられます。毒が無くても、大きな体や口、鋭い爪などで十分に優位だと思うのですが、この毒は獲物の出血を止まらなくする効果があるとされ、嚙まれた相手が徐々に弱って仕留めやすくなります。
環境エンリッチメントの動画でも、ボールに嚙みつくタロウの顎からは涎が垂れていますが、あれも一種の毒液なのかもしれません。

飼育展示場の構成自体にも、野生下の環境を加味したいろいろな工夫がされています。アーチ状の木はその一つで、タロウはそこをくぐるのがお気に入りのようです。

帰りは植木ポッドの向こうをすり抜けることが多く、タロウなりのこだわりがあるのかもしれません。

コモドオオトカゲは、その異形ともいうべき姿から「現代の恐竜」などと称されることもあります。しかし、現生する唯一の恐竜は鳥類です*⁵。鳥類に見られる恐竜としての特徴のひとつである「体の真下にまっすぐに伸びた肢」は、トカゲ類にはないものです。いくら体が大きくて怪物的な迫力があっても、四肢を体の両側に張り出して歩くコモドオオトカゲは、あくまでもトカゲなのです。
*⁵ 詳しくはこちらをご覧ください。
「動物園は出逢いの場【第8回】恐竜じゃありません! 首長竜とオオトカゲ」
気が向けば、奥の高いところにも上っていきます。どんな足掛かりを伝っていくのか、現地でじっくりと観察してみてください。

この水場では、水を飲むだけではなく、体を浸すこともあります。野生下でも、川などで泳ぐことがあるそうです。
そして、さらなる出入り口に向かうタロウ。

先ほどまでの場所を「大きな部屋」と呼ぶとしたら、こちらは「小さな部屋」です。

どちらの部屋も、床には土とウッドチップが広がっています。ここはもともと、ゴリラたちの屋内展示場で、現在の床の仕様はタロウの足の保護を配慮しつつ、森などの本来の野生環境を模したものとなっています。最初は土やチップを山にして入れ、それをタロウが突き崩して、いまのありさまとなりました。ヤシ殻チップを与える動画にも見るように、土やチップを広げて環境づくりをする活動そのものが、タロウの環境エンリッチメントになったのだと考えられます。
タロウのお気に入りらしいアーチ型の木などは、さらにその後に足されたものです。
広さに加え、「大きな部屋」のみが紫外線ライトを備えています。これは、大小の部屋で日向と日陰(木陰・草むらや林床など)の環境をつくり分け、タロウが自由に選択できるようになっているのです。

タロウとまなざしを交わすと、さまざまな飼育的配慮に支えられた「タロウの世界」へと誘われるように感じます*⁶。

*⁶ タロウは担当飼育員などを見分けることができるようです。顔なのかユニフォームなのか、どんな尺度で認知が行われているのかはわかりません。
あなたもタロウの瞳に出逢ってみませんか?

【名古屋市東山動植物園】
https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/
【文・写真】
森 由民(もり・ゆうみん)
動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物表象に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』『ウソをつく生きものたち』(いずれも緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。
動物園エッセイhttp://kosodatecafe.jp/zoo/
「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!
メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!
登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!