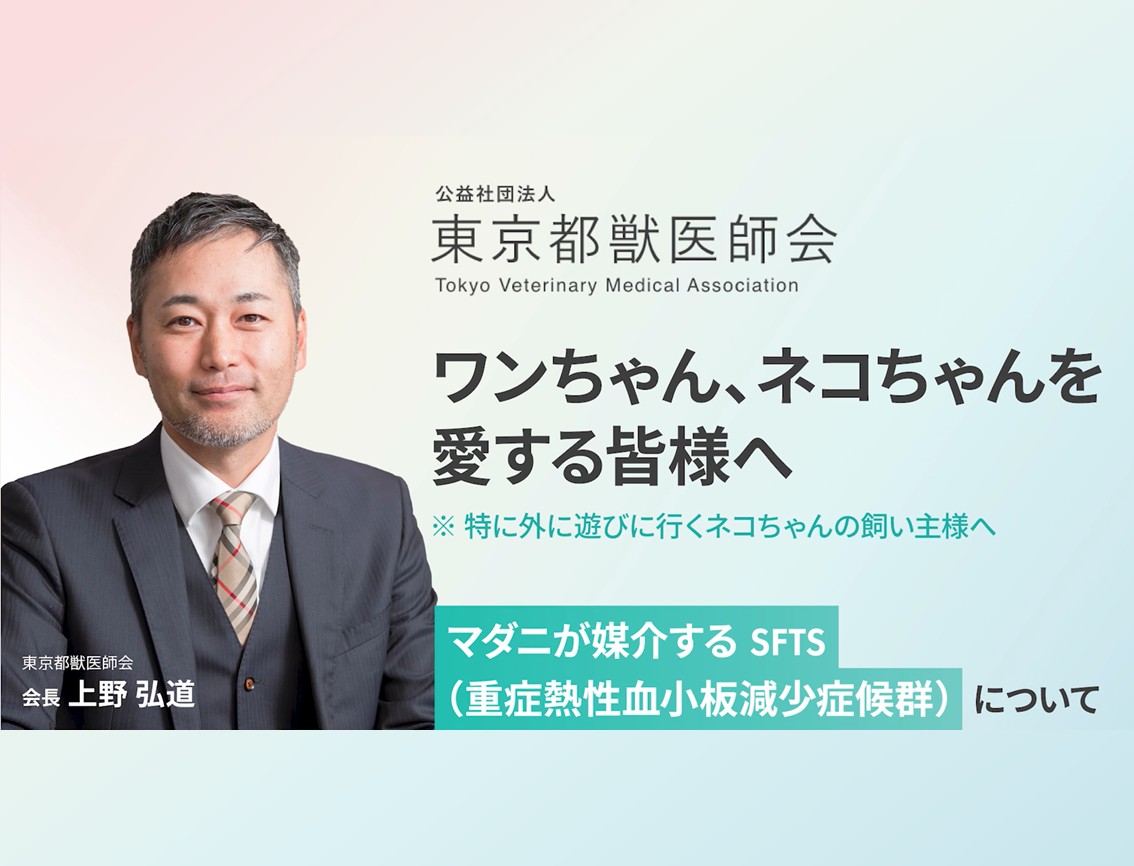『七つの子』は、多くの日本人が子どものころによく聞いた覚えのある童謡です。歌われている情景を含め、日本人の心に深く染み入る情緒がある詩です。
作詞は野口雨情(1882~1945年)、作曲は本居長世(1885~1945年)で、1921年(大正10年)に発表されました。広く歌われた童謡ですが、若い方の中には知らない人もいるかもしれません。念のため歌詞の一部を紹介しておきます。
カラス なぜ啼(な)くの
カラスは山に 可愛七つの 子があるからよ
可愛 可愛と カラスは啼くの
可愛 可愛と 啼くんだよ
山の古巣へ 行ってみてごらん
丸い眼をした いい子だよ
『七つの子』の歌詞の違和感
カラスの研究を始めて間もなく、この歌詞の違和感や不思議に思う部分が2点ほどありました。その一つは題名で、もう一つは古巣です。
まず、題名において気づいた点についてお話しします。『七つの子』という題名から、読者のみなさんはどのようなことを連想しますか?
「7歳の子」「7羽の子」などと想像する人は多いと思います。一方、自然界のカラスを考えますと、多くの場合でヒナは2~5羽です。7羽ではありません。

また、カラスは満2年で大人になりますので、7歳の子も現実とは合いません。さらに「古巣」とありますが、カラスの巣は毎春新しく造られます。野口雨情はどのような気持ちでこの詩を作ったのでしょうか……。不思議に思うのは私だけでしょうか。
単純に考えれば、野口雨情はカラスの生態を考えずに、理想や思いの数値を現したとも考えられます。私なりに解釈してみました。
この詩が発表された大正10年ごろの日本は、決して豊かとはいえず医療も発達していませんでした。そんな中で子どもを健康に育てることは、大変なことだったと思います。ちなみに、大正10年の乳児死亡率は出生1,000人中約170人です(2024年:1,000人中約2人)。ですから、7才まで育つと体力も向上し、成人を迎える可能性がぐんと高くなります。七五三は、そのような節目まで成長できたお祝いです。
このような時代背景もあり、童謡「七つの子」は「ようやく七つになったかわいい子供が家で待っている」という子煩悩な親の愛情をうたい、夕方になると帰巣するカラスに、家族思いの親を重ね合わせたのではないだろうかと考えました。しかし、確認するすべもなく、しばらくは自分なりの解釈でした。ところが、雨情のお孫さんである野口不二子の著書『郷愁と童心の詩人 野口雨情伝』(講談社、2012年)に偶然出会い、謎が解けました。
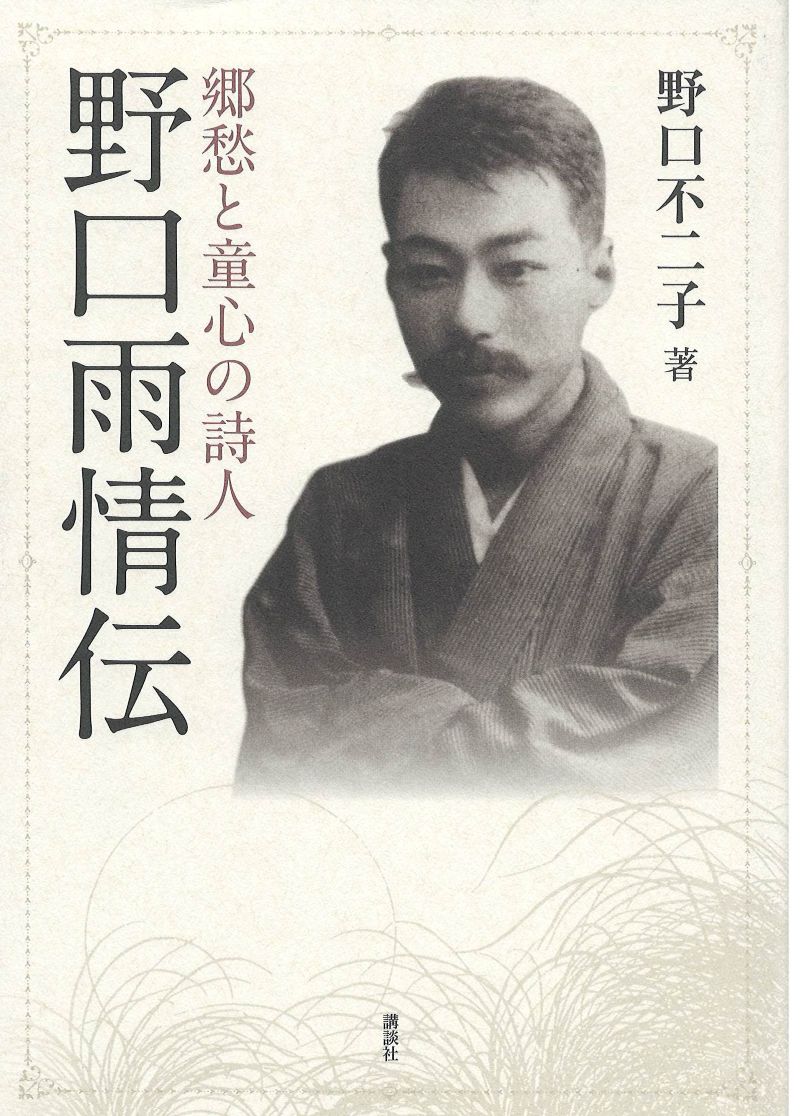
この本には、雨情の長男・雅夫の話として、先の疑問が解ける当時の雨情と雅夫の会話や様子が出てきます。雨情は詩人を目指し実家の稼業を顧みなかったようですが、実母の死を契機に実家の林業に専念した時期があったそうです。このころ、雨情は当時7歳の雅夫を連れてよく山に出かけたようです。昼食をとる山小屋には、よくはぐれたカラスがやってきたそうで、カラスを話題にすることも多かったようです。
ある日、雨情が山小屋にやってきたカラスを指し、「このカラスはお母さんをさがしているのか、お父さんをさがしているのか」と雅夫に尋ねたことがあったそうです。そんな問いかけに雅夫は、当時家を空けがちだった父がまた旅に出ると悟ったようです。
雨情が家族をのこして単身でどこかへ旅立つ際に、7歳の雅夫に家族を託すという思いと、故郷に家族をおいて一人旅に出る寂しく辛い心境が「七」、「古巣」、「可愛」という言葉を繋げた歌詞になったそうです。
カラスの子育てを観察していると、親ガラスの面倒見が良いので、思わず擬人化して愛情表現をあてはめたくなります。そのため、カラスが登場する絵本は「カラスのパンやさん」(かこ さとし、偕成社、1973年)など、数多くあります。
野口雨情に限らず、カラスの営みを人の営みに重ねて考える人は多いのだと思います。野生のいきものであるカラスが、それだけ身近で、日常の生活に入り込んでいるからだと思います。
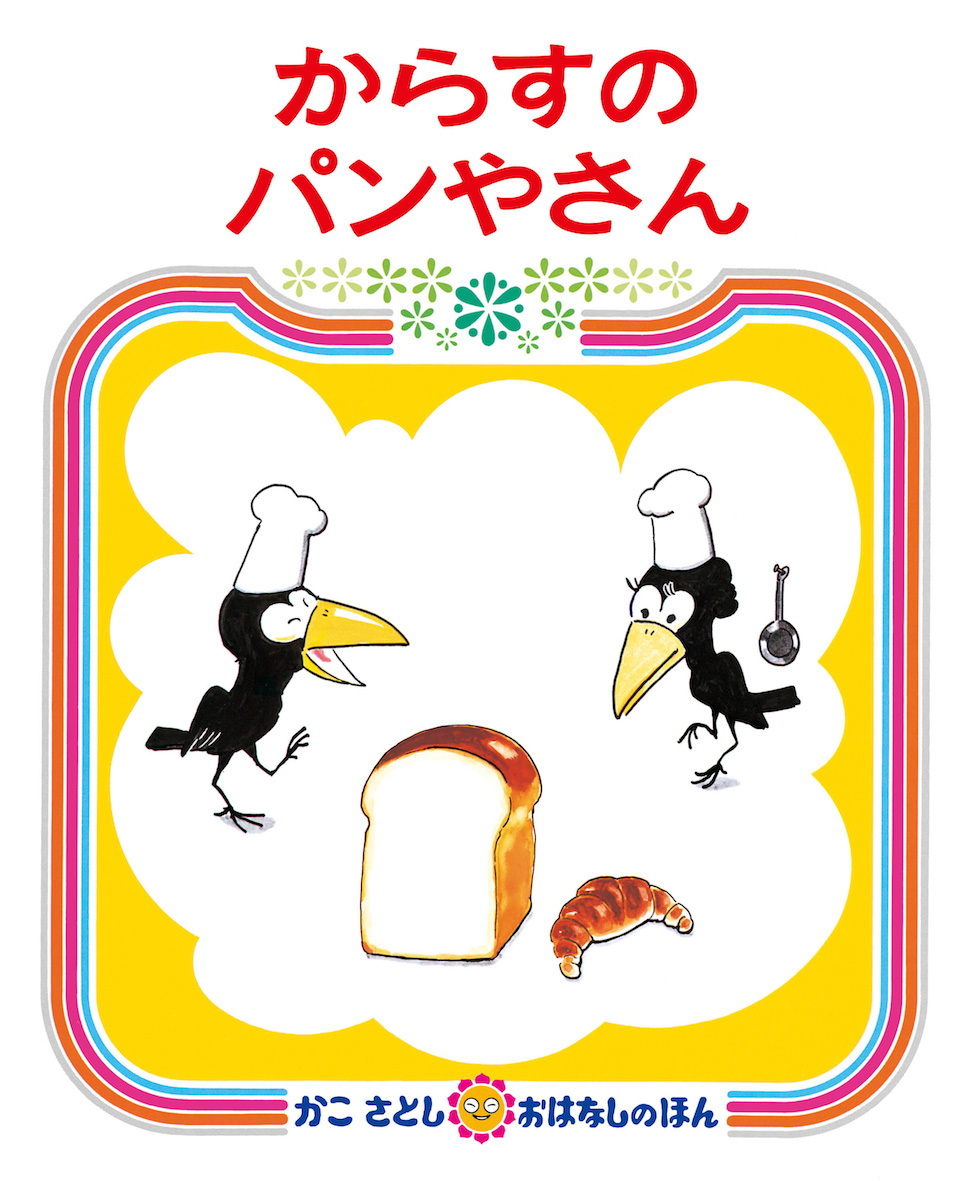
[参考文献]
・厚生労働省、「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」、
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/index.html
【執筆者】
杉田昭栄(すぎた・しょうえい)
1952年岩手県生まれ。宇都宮大学名誉教授、一般社団法人鳥獣管理技術協会理事。医学博士、農学博士、専門は動物形態学、神経解剖学。実験用に飼育していたニワトリがハシブトガラスに襲われたことなどをきっかけにカラスの脳研究を始める。解剖学にとどまらず、動物行動学にもまたがる研究を行い、「カラス博士」と呼ばれている。著書に『カラス学のすすめ』『カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記』『もっとディープに! カラス学 体と心の不思議にせまる』『道具を使うカラスの物語 生物界随一の頭脳をもつ鳥 カレドニアガラス(監訳)』(いずれも緑書房)など。
「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!